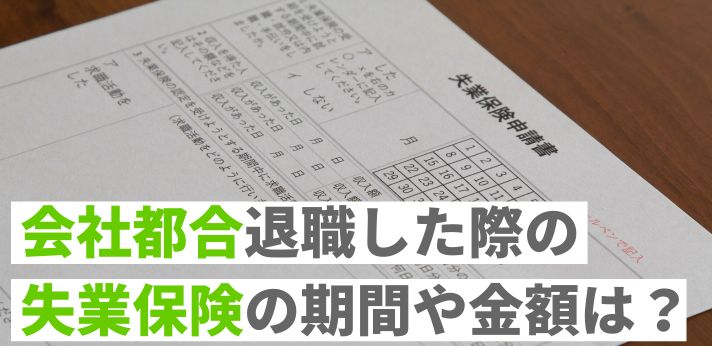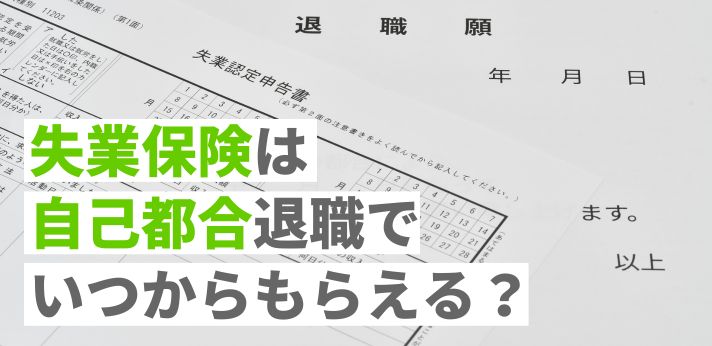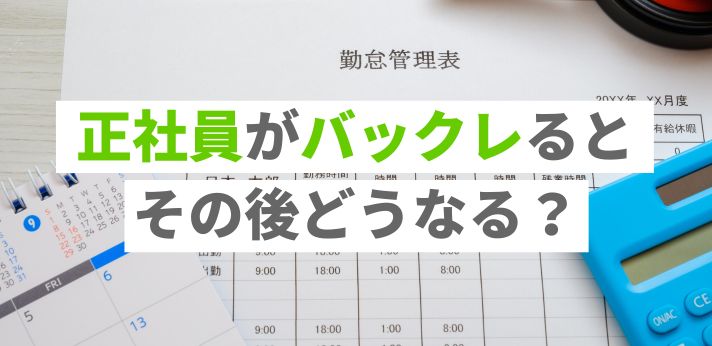退職前にやることリスト!会社への返却物と受け取る書類や公的手続きを確認退職前にやることリスト!会社への返却物と受け取る書類や公的手続きを確認
更新日
公開日
対応漏れがないよう事前に退職前にやることリストを作って、必要な手続きを確認しよう
退職前後の手続きや手順が分からず、やることリストが欲しい!と考える方もいるでしょう。退職日までの手続きや受け取るべき書類など、確認が必要な項目は多くあります。
このコラムでは、自己都合退職をする際のやることリストをご紹介。会社に返却するものや受け取る書類、退職後に行う必要がある公的手続きもまとめました。チェックリストを活用して効率良く手続きを完了し、円満退社を目指しましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
退職前にやることリスト
退職前にやるべきことを、以下のチェックリストに沿って紹介します。スムーズに手続きを進めるため、退職することを決めたら以下を参考に「やることリスト」を作っておくと便利です。退職日までのスケジュールと照らし合わせて忘れている手続きがないかを都度確認してください。
退職前にやることリスト
- 1~3ヶ月前:上司に退職したい旨を伝える
- 1~2ヶ月前:上司に相談して退職日を決める
- 1ヶ月前~:後任者への引き継ぎを行う
- 2週間前~:取引先へ退職のあいさつを始める
- 最終出社日:書類の受け取りや社内でのあいさつを行う
1~3ヶ月前:上司に退職したい旨を伝える
退職希望日の1〜3ヶ月前までに、直属の上司に退職したい旨を伝えましょう。手続きをスムーズに進めるにあたり、まず直属の上司に退職の意思を伝え、了承を得る必要があります。いきなり退職願を提出することは一般的にマナー違反とされているため、避けましょう。
退職の意思を伝えた際、上司に引き止められる可能性もあります。事前に明確な退職理由を考えておき、伝え方を工夫しましょう。「退職を考えている」のような曖昧な言い方だと、相談だと受け取られるケースもあります。誤解を与えないよう、「△△を理由に、△ヶ月以内に退職したい」と、退職理由や退職希望日を具体的に伝えましょう。
上司への伝え方は「転職を上司に相談するのに適したタイミングはいつ?伝え方や注意点を解説」のコラムを参考にしてください。
退職の意思はできるだけ早めに伝えよう
退職の意思が固まったら、上司にはできるだけ早めに伝えることが大切です。退職の意思を早めに伝えることで、引き継ぎ期間にも余裕が生まれ、円満退職にもつながります。逆に、ギリギリになって退職の意思を伝えると、引き継ぎ期間が十分に確保できない恐れがあり、職場に混乱を起こしかねません。周囲の理解を得て、気持ち良く退社するためにも、退職の意思が固まったらすぐに伝えましょう。
1~2ヶ月前:上司に相談して退職日を決める
退職に関して上司の了承が得られたら、相談のうえ退職日を決めます。退職日を決定する際は、会社側の都合や手続きに必要な時間に配慮しなければなりません。自身の希望を押し通すのではなく、両者にとって良いタイミングにすることが大切です。業務を後任者へ引き継ぐために必要な期間や、残っている有給休暇の日数などを考慮して、退職日を決定しましょう。
1ヶ月前~:後任者への引き継ぎを行う
退職日が決まったら、1ヶ月ほど前から後任者への引き継ぎを開始します。周囲に迷惑を掛けることなく退職するためにも、次のポイントを意識して手続きを進めましょう。
引き継ぎの計画を立てる
まずは退職日までの引き継ぎ計画を立てます。自分が担当していた業務を洗い出し、引き継ぎに必要な時間を考えましょう。業務量や後任者のスキルを考えて臨機応変に計画を調整することが大切です。退職日の数日前までに引き継ぎが完了するよう余裕を持って計画を立てておくと、途中で予期せぬ出来事が起こり手続きが滞った場合にもリカバリーしやすいでしょう。
資料やマニュアルを作成して残す
退職時の引き継ぎは、資料やマニュアルなどの目に見える形で内容を残しておくことも大切です。引き継ぎを口頭だけで行うと伝達ミスが起こりやすく、後任者にも不安が残る恐れがあります。後任者が途中で交代する場合にも対応できるよう、できるだけ分かりやすい資料やマニュアルを用意しましょう。
2週間前~:取引先へ退職のあいさつを始める
退職日の2週間ほど前からは、社内での手続きだけでなく取引先へのあいさつを開始します。後任者が決まっている場合は、できるだけ同行してもらいましょう。次の担当者を直接紹介することで取引先に安心感を与えられ、後任者も仕事をスムーズに進めやすくなります。
なお、あいさつする際に退職理由を聞かれても、具体的に答える必要はありません。「一身上の都合により」「私事により」などと簡潔に伝えましょう。
最終出社日:書類の受け取りや社内でのあいさつを行う
最終出社日(退職日当日)は、会社から退職手続き時に必要な書類を受け取り、不備がないかチェックします。また、社員証や業務で使用した備品などを忘れずに返却し、デスク周りを整理しましょう。
また、引き継ぎについて、「漏れがないか」「後任者や上司などが疑問に思っている点はないか」などを最終確認することも大切です。最終日の業務が終了したら、お世話になった上司や同僚などにあいさつをして感謝の気持ちを伝えましょう。
円満退職をしたい方は、「退職時にやるべきことは?手続きの流れやトラブルを避けるポイントを解説」も参考にしてみてください。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職届を作成する際のポイント
続いて、退職届を作成する際のポイントを紹介します。作成方法や使用する用紙・封筒のサイズ、退職願との違いなどを事前に確認し、不備がないようにしましょう。
1.会社指定の方法で作成する
退職届は、会社指定の方法で作成しましょう。指定がない場合は、一般的なフォーマットを利用して作成するのがおすすめです。退職届の作成方法を手書きとパソコンの2通り紹介するので、参考にしてください。
手書きの場合:黒の万年筆などを使用し縦書きで記入
退職届を手書きする場合、白地でB5かA4サイズの便箋を用意しましょう。罫線の有無は問われません。黒色のボールペンか万年筆を使用し、基本的に縦書きで記入します。インクの色が摩擦で消えるボールペンや鉛筆など、文字の書き換えができる筆記用具の使用は控えましょう。
パソコンの場合:縦書きで作成しコピー用紙に印刷
パソコンで退職届を作成する場合、B5かA4サイズの白い紙に黒インクで印刷します。使う紙は、コピー用紙で問題ありません。より丁寧な印象を与えたい場合は上質紙を使いましょう。会社からフォーマットの指定がない場合、文章は縦書きにするのが一般的です。
2.白色で無地の封筒を選ぶ
退職届の用紙サイズがB5の場合は「長形4号」、A4の場合は「長形3号」の白い無地の封筒を使うと、用紙を三つ折りにしたときにちょうど入れられます。郵便番号枠などの図柄が入った封筒や、茶封筒の使用は控えましょう。二重構造の封筒を選ぶと、中の文字が透けるのを防げます。
退職届と退職願の違いとは?
退職願は、従業員が会社に対して「退職したい」と願い出るための書類です。状況によっては却下される可能性があり、提出後の撤回もできます。一方で、退職届は退職日が確定したあと、自身の意思を会社に通告するための書類です。「△月△日をもって退職いたします」と言い切る形で書きます。退職日の1ヶ月前には提出しなければならないのが一般的で、提出後は基本的に撤回できません。退職届を提出したあと、本格的な退職手続きを開始します。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
退職前に会社へ返却するもののチェックリスト
退職前に会社へ返却するもののチェックリストは以下のとおりです。
- ・健康保険被保険者証
- ・社員証や社章
- ・自身と取引先の名刺
- ・払い戻し可能な通勤定期券
- ・業務で使用していたデータやマニュアル
- ・パソコンや携帯電話などの備品
1.健康保険被保険者証
会社を通じて加入していた健康保険は、退職と同時に脱退となります。健康保険被保険者証は使用できなくなるので、退職手続きの際、速やかに返却しましょう。
退職後、すぐに転職して転職先の健康保険に入る場合は、そちらに切り替えられます。切り替えの手続きは、転職先に入社後に人事担当者が進めてくれるでしょう。
一方、転職まで間が空く場合は、ほかの健康保険に加入する手続きを自分で行う必要があります。
退職後の健康保険については、「健康保険は仕事を辞めたら手続きが必要?切り替えの方法や注意点を解説!」を参考にしてみてください。
2.社員証や社章
社員証や社章など従業員であることを証明するものも、退職手続き時に返却しましょう。従業員が退職後に社員証を持ったままだと、セキュリティ面での深刻な問題に発展する恐れがあるからです。取引先の入館証が手元にある場合も、忘れずに返却しましょう。
3.自身と取引先の名刺
自身の名刺だけでなく、取引先の名刺も返却対象です。業務で得た取引先の情報を利用し、転職先で営業活動を行うことを防ぐ目的があります。円満に退職するためにも、在職中に得た情報を持ち出したり口外したりしないよう、細心の注意を払いましょう。
4.払い戻し可能な通勤定期券
通勤用の定期券を現物支給されていた場合は、退職する際に返却が必要です。ただし、有効期限まで残り1ヶ月を切っており、払い戻しが不可能な場合は返却しなくても良いケースがあります。通勤手当に関する規定は企業によって異なるため、事前に自社のルールを確認しておきましょう。
5.業務で使用していたデータやマニュアル
業務で使用していたデータは、種類によって対応方法が異なります。業務で社内システムのパスワードを使用していた場合は、必ず後任者へ引き継いでおきましょう。会社から支給されていたUSBメモリは、退職日までに確実に返却します。
個人の判断でデータを削除すると、業務の遂行や引き継ぎが困難になってしまう恐れがあるため、上司に確認したうえで対応しましょう。マニュアルも会社の大切な資産なので、データ・紙を問わず返却するのが基本です。
6.パソコンや携帯電話などの備品
業務で使用していたパソコンや携帯電話などの備品も会社に返却しましょう。会社から支給された備品はもちろん、経費で購入した文房具や資料なども会社の所有物です。トラブルを避けるためにもすべて返却するのが無難といえます。返却するべきか迷う備品がある場合は、上司に確認しましょう。
退職時に会社から受け取るもののチェックリスト
退職手続きでは、会社から受け取らなければならないものも複数あります。チェックリストで確認しておきましょう。
退職日までに受け取れるもの
退職日までに受け取れるものは「退職証明書」「年金手帳」「雇用保険被保険者証」の3つです
退職証明書
退職証明書とは、退職した事実を証明するための書類のこと。退職者から申請があった場合に会社から発行されます。転職先から提出を求められた場合や、雇用保険(失業保険)の手続きで離職票が届くまでの代わりとして使用したい場合などは、退職日までに発行申請をしておきましょう。
退職証明書の詳細は「退職証明とは?何に使う?もらい方やいつもらえるのかも解説!」のコラムで確認してみてください。
年金手帳
年金手帳を会社に預けている場合も、退職日までに受け取る必要があります。年金手帳は、転職先で厚生年金に加入する際や年金種別の切り替え手続きを行う際に必要です。
なお、年金手帳は、2022年4月から「基礎年金番号通知書」に切り替わりました。そのため、年金手帳を紛失した場合は、基礎年金番号通知書の再発行を申請しましょう。再発行の申請手続きの詳細は、日本年金機構の「基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき」でご確認ください。
また、会社で厚生年金基金にも加入していた場合は、加入歴を証明できる厚生年金基金加入員証の受け取りも必要です。
参照元
日本年金機構
年金の制度・手続き
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、ハローワークから、雇用保険に加入した人に発行される証明書です。雇用保険被保険者証の発行後、加入した従業員本人に手渡す企業もありますが、会社で保管して退職時に本人に渡すのが一般的。また、企業によっては、退職後に離職票や源泉徴収票などとともに送付される場合もあります。
退職後に送付されるもの
「離職票」や「源泉徴収票」は、退職日以降に送付されます。「健康保険資格喪失証明書」も、保険証の返却後に発行が可能です。到着にかかる日数を考慮したうえで、手続きのスケジュールを立てておきましょう。
離職票
離職票は、離職したことを証明する公的書類です。ハローワークで雇用保険(失業保険)の給付申請手続きをする際に必要となります。転職の予定がない人や、ブランクができる人は確実に受け取りましょう。
離職票は、従業員が退職後、会社がハローワークに必要な書類を提出すると発行され、会社宛てに交付されます。その後、会社から従業員本人へ送付されるという流れです。
退職後、離職票が本人に届くまでの目安は10日前後といわれています。退職から2週間経っても届かない場合は、前職の担当者に確認しましょう。自分で催促するのが難しい場合は、まず、ハローワークに「離職票の発行と、会社への交付が済んでいるか」を問い合わせることをおすすめします。会社への交付が済んでいる場合は、ハローワークから会社に連絡して自身への交付を促してもらいましょう。
源泉徴収票
源泉徴収票は、退職した年の1月1日から退職した月までの給与額と、所得税の支払額などが記載された書類です。通常、退職日から1ヶ月以内に発行されます。転職先での年末調整や、同年内に再就職しない場合の確定申告手続きで使用するので、忘れずにもらっておきましょう。
健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書とは、健康保険の被保険者や被扶養者が加入者資格を喪失したことを証明する書類です。退職に伴い会社の健康保険を脱退して国民健康保険に加入するときや、任期継続被保険者として引き続き会社の健康保険に加入するときに使用します。
健康保険資格喪失証明書は、従業員が健康保険証を返却し、会社が資格喪失手続きを完了したあと、年金事務所や健康保険組合から発行されます。通常は会社が手続きを完了してから3日以内に発行されますが、状況によっては1週間以上要する場合もあるようです。
会社側で証明書の発行手続きがされない場合は、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書」の交付を求める請求書を提出しましょう。提出手続きの詳細は、日本年金機構の「国民健康保険等へ切り替えるときの手続き」をご覧ください。
参照元
日本年金機構
年金の制度・手続き
退職後に行う公的手続きのチェックリスト
退職後に行う公的手続きには、健康保険や年金、雇用保険(失業保険)などの手続きがあります。
退職後、すぐに転職するかどうかによって必要な公的手続きの種類が異なるので、自分の状況に合う手続きを把握してから進めましょう。
ここでは、退職後の公的手続きのチェックリストを紹介します。
1.健康保険に関する手続き
退職したら、健康保険に関する手続きを必ず行いましょう。
退職後、すぐに転職して転職先の健康保険に加入する場合は、前職の退職時に会社から受け取った健康保険資格喪失証明書を転職先に提出すれば、健康保険証を発行してもらえます。
退職後、転職する予定がない場合や、転職先が決まっているものの入社までに間が空く場合は、以下の3つの方法のうち、いずれかで健康保険に加入しましょう。
- ・国民健康保険に加入する
- ・退職前の健康保険を任意継続する
- ・家族の健康保険の扶養に入る
国民健康保険への加入手続きの期限は退職日の翌日から14日、任意継続は20日以内と決まっています。手続きをしないままだと、病院を利用した際に医療費を全額自己負担しなければならない可能性があるため、退職したらすぐに手続きを行いましょう。
2.年金の切り替え手続き
日本の公的年金には大きく分けて、20歳以上・60歳未満のすべての人が加入する「国民年金」と、会社員や公務員が国民年金に加えて加入する「厚生年金」の2種類があります。
退職した月と同じ月に転職先に入社する場合は、国民年金への切り替えは不要です。転職先の会社に年金手帳を提出すると、担当者が厚生年金に加入し続けるための手続きを行ってくれます。
一方、転職する予定がない場合や、転職先が決まっているが退職後、月をまたいで入社した場合は、以下の2通りから年金の切り替え先を選びます。
- ・国民年金へ切り替える
- ・家族の厚生年金の扶養に入る
3.雇用保険(失業保険)の給付申請手続き
雇用保険(失業保険)の給付申請手続きは、ハローワークで行いましょう。ハローワークで求職申し込みを行い、条件が満たされていることが確認できると受給資格が得られます。自己都合で退職した場合は、7日間の待期期間と2ヶ月間の給付制限期間を終えたあとに給付されるのがルールです。
4.住民税の支払い手続き
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得額に応じて課され、今年6月から来年5月までの12回に分けて支払います。徴収方法は、納税者本人が納める「普通徴収」と、給与から天引きされる「特別徴収」の2つです。
すぐに転職する場合は、退職する会社と転職先の会社の間で継続手続きをしてもらうことで、特別徴収を継続できます。退職する会社に手続きをしてもらうのが難しい場合は、一旦、普通徴収に切り替えて、転職先で特別徴収へ切り替えることも可能です。
転職する予定がなかったり、転職先が決まっているものの入社まで間が空いたりする場合は、「1~5月に退職する場合」と「6~12月に退職する場合」で必要な手続きが異なるので注意しましょう。
1~5月に退職する場合は、原則として、退職する月の給与から住民税が一括で徴収されます。
一方、6~12月に退職する場合は、退職する月までは給与から住民税が天引きされ、その後は自分で納めます。なお、希望すれば、退職する月から翌年5月分までを一括で納税することも可能です。
5.所得税の手続き
所得税は、予測される年間の給与額に応じて課され、毎月の給与から前払いで納めます。企業に務めている人の場合、会社が従業員本人に代わって納付するのが一般的です。
年間の給与の総額と、それに応じた所得税額が確定する12月に、「年末調整」として所得税額の過不足を計算して追加徴収や返還が行われます。
退職後、年内に転職する場合は、基本的に転職先に年末調整の手続きをしてもらえます。
一方、年内に転職しない場合や、年内に転職したものの入社が社内の年末調整の期限に間に合わなかった場合は、翌年、自分で確定申告をする必要があるので注意しましょう。
転職活動は会社を辞める前に始めるのがおすすめ
退職前にやることリストを準備したら、会社を辞める前に転職活動を始めるのがおすすめです。転職先を決めないまま退職すると、収入がないことにストレスを感じたり、焦って転職してミスマッチが生じたりする恐れがあるでしょう。
在職中に転職活動を行う場合、限られた時間を効率的に使うため、ハローワークや転職エージェントを活用してサポートしてもらうのも手です。以下で、これらのサービスの特徴を紹介します。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、雇用に関するさまざまなサービスを無償で提供している、厚生労働省が運営する機関です。就職・転職活動を行う人に対して、求職相談や職業紹介、雇用保険の手続きなどのサポートを実施しています。
ハローワークは全国500ヶ所以上に設置されており、「新卒応援ハローワーク」「わかものハローワーク」といった若年層向けの支援窓口もあります。これらの窓口の詳細は、厚生労働省の「若者への就職支援」をご覧ください。
参照元
厚生労働省
雇用
転職エージェント
退職手続きを確実に終わらせたいなら、チェックリストを使って確認するだけでなく転職エージェントに相談することも視野に入れてみましょう。転職エージェントは、民間企業が運営する就活支援サービスです。サービス内容はエージェントによって異なりますが、求人の紹介や、複雑な退職手続きに関するアドバイス、転職活動のスケジュール管理をしてもらえる場合もあるでしょう。
就活でハローワークやエージェントを活用する人は多い
ハタラクティブが公表した若者しごと白書2025の「
3-6. 就職先探しの手段・利用サービス」によると、就職先探しで最も利用したサービスを正社員とフリーターに聞いたところ、「ハローワーク」「就職・転職エージェント」が上位にランクインしました。この結果からも、ハローワークやエージェントが就活の手段として一定の人気があることが分かるでしょう。
限られた時間のなかで退職手続きを効率的に進めたい方は、ぜひハタラクティブをご利用ください。ハタラクティブは、若年層の支援に特化した転職エージェントです。専任のキャリアアドバイザーが、丁寧なカウンセリングや強みを引き出す自己分析で、一人ひとりに最適な転職先を見つけられるようお手伝いします。
求人紹介や選考対策はもちろん、企業とのやり取りもすべてキャリアアドバイザーが代行します。内定が出るまで最短2週間と、効率的に就活できるため、退職前の忙しい時期でも安心です。
サービスはすべて無料ですので、「職場の雰囲気を知りたい」第三者のサポートを受けながら円満退職や転職の成功を目指したい方は、お気軽にご相談ください。
退職の手続きに関するFAQ
退職時の手続きについてよくある相談や質問に回答します。
自己都合退職に必要な手続きのチェックリストには何を書けばいい?
まず、退職日までに社内で行う手続きとして、退職届の提出や、引き継ぎなどがあります。また、退職日までに会社に返却するべきものや、退職前後に会社から受け取る書類もリストアップしましょう。さらに、退職後に行う雇用保険(失業保険)や年金といった公的手続きについても把握しておく必要があります。
雇用保険の手続きについては、「失業保険は会社都合と自己都合退職で給付金額や期間が違う?手続き方法は?」で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
仕事を辞める前にハローワークで転職先を探すのはアリ?
退職届の提出や引き継ぎといった社内での手続きを怠ってはいけません。これらを確実に完了しないと会社や上司などに迷惑を掛けてしまうからです。
また、退職後、雇用保険(失業保険)や年金、健康保険といった公的手続きも忘れないようにしましょう。
具体的なリスクについては「退職後の手続きを忘れたらどうなる?失敗を回避するための方法を紹介」で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
退職後に転職の予定がない場合は、市区町村の役所で健康保険への切り替えや、国民年金への加入申請が必要です。退職時期や再就職するまでの期間によっては、税金の手続きが必要になる場合もあります。詳細は「退職後に市役所の手続きでやることは?必要書類や持ち物も解説」でご確認ください。
「退職時の手続きに不安がある」「仕事を辞める前に転職先を見つけたい」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。転職支援の経験豊富なキャリアアドバイザーが丁寧にアドバイスし、仕事と就活の両立を手厚くサポートいたします。