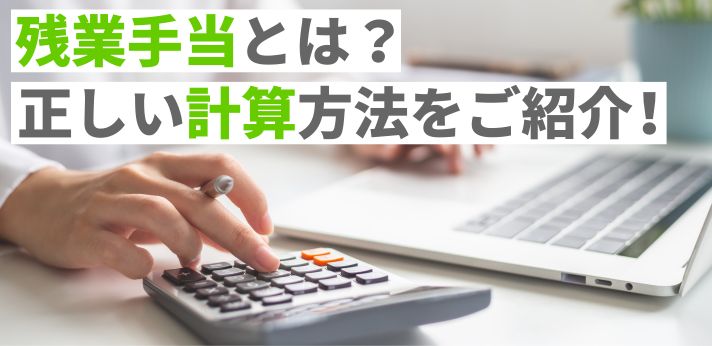平均収入の実態を年代・男女・地域別に紹介!年収アップの方法も解説
平均収入を知り、自分の年収と比べてみたいという方もいるでしょう。日本人の平均収入は、年齢や性別、職種、都道府県などの違いによって差があるのが実態です。
このコラムでは、各カテゴリーごとの平均収入をまとめました。また、平均収入以上の年収を目指す方法や、転職先選びで注目したいポイントについても解説しているので、給与アップしたい方はぜひご覧ください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断

日本人の平均収入は458万円

国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、2022年の1年を通して働いた日本人の平均年収は458万円です。男女別に見ると、男性は563万円、女性は314万円でした。
平均収入はどのように計算して算出しますか?
平均収入は給与所得者の全員の額面年収を合算し、人数で割った金額です
給料やボーナスを会社から受け取っている人を「給与所得者」と呼びます。給与所得者の年収(額面年収)は、「税金や社会保険料が控除される前の1年間の総収入」です。
平均収入は「給与所得者全員の額面年収を合算し、合算した人数で割った金額」です。
一例として、給与所得者が5人の年収が下記の場合の平均収入を算出します。
社員A:700万円
社員B:300万円
社員C:450万円
社員D:470万円
社員E:670万円
<社員5人の年収合計>
700万円+300万円+450万円+470万円+670万円=2,590万円
<5人の年収平均>
合計年収の2,590万円を5(合算した人数)で割ります。
2,590万円÷5人=518万円
つまり、平均収入は「518万円」となります。
平均収入458万円の手取り額は約344万円
先述したように、日本人の1年間の平均収入は458万円です。この平均収入から、社会保険料や税金を引いた実際の手取り額を算出すると、約344万円(7.5割で計算)となります。月々の割合を単純計算すると、1ヶ月の平均手取り額は約29万円です。
なお、年収には賞与も含まれるため、賞与の支給がある月とない月で収入に差が出るでしょう。
日本人の平均収入の推移
同調査によると、日本人の平均収入はここ10年間で増加傾向にあり、2014年と2022年を比較すると37万円ほど上がっています。以下は、平均給与の推移を表にしたものです。
| 調査年 | 平均年収 |
|---|---|
| 2014年 | 421万円 |
| 2015年 | 423万円 |
| 2016年 | 425万円 |
| 2017年 | 434万円 |
| 2018年 | 439万円 |
| 2019年 | 438万円 |
| 2020年 | 435万円 |
| 2021年 | 446万円 |
| 2022年 | 458万円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査((第9図)平均給与及び対前年伸び率の推移)(p.16)」
表を見ると、2014年から2018年までは平均収入が上昇していることが分かります。しかし、新型コロナウイルス感染症が蔓延していた2019年からの2年間は、前年比を下回る調査結果です。
同調査では感染症による影響について明記されていませんが、「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」で多様な対応が示されていることから、経済へマイナスの影響を与えた可能性は否定できないでしょう。
参照元
国税庁
民間給与実態統計調査
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
平均収入で見るポイントは平均値と中央値
多くのデータでは、全体を足して個数で割る「平均値」の結果が採用されています。平均収入の平均値も、年収をすべて足し総労働人口数で割った数値です。年収1億円を超える人がいれば、それに応じて平均値が大きくなる性質があります。
そのため、平均収入が458万円という結果を見て、「これほど高いのはおかしいのでは?」と思った方は、年収の「中央値」を見てみましょう。中央値とは、小さい数から大きい数を順番に並べたときに、その真ん中に位置する数値です。大小さまざまなデータがあってもその中心を見るため、極端な影響は受けません。平均値を見るより中央値を参考にするほうが、より現実的な数字となります。
なお、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査の概況(p.9)」の結果から、企業規模合計の年収の中央値を単純計算すると、男性が約394万円、女性が約307万円でした。年収の中央値については、「26歳の平均年収を解説!大卒と高卒で差はある?」でも紹介しているので、参考にしてみてください。
※国税庁と厚生労働省では抽出条件が異なるため、両者間での単純な比較はできません。
参照元
厚生労働省
令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況
年収は個人の1年間の収入額です。一方、平均年収は対象者全員の年収を合計し、人数で割ったもの。高年収の人がいると平均値が上がりやすいのが特徴です。
これに対して、中央値は全員の年収を並べたとき、真ん中にくる値を指します。例えば、年収300万円、400万円、1,000万円の3人がいる場合、平均は約566万円、中央値は400万円です。高収入層の影響を受けにくいぶん、中央値のほうが「一般的な年収の実態」に近いといえるでしょう。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
平均収入に関連する言葉の意味の違い

収入・月収・手取りなど、給与に関する基本的な用語への理解があいまいだと、効果的な収入アップ方法を見つけるのが難しくなります。ここでは、平均収入に関連する言葉の意味の違いを解説するので、自信のない方はぜひチェックしておきましょう。
収入とは
収入とは、労働の対価として受け取る報酬のことで、年収や月収を指す言葉です。「額面給与」ともいわれ、内容によって年収か月収かを判断します。よく耳にする「額面」とは、基本給に加えて各種手当や賞与、残業代などを含めた給与の総支給額です。社会保険料や住民税、所得税などが差し引かれる前の金額となります。
年収・月収とは
年収とは、1年間で会社から支払われる総支給額のことです。基本給に各種手当や諸費用をすべて含み、社会保険料や税金が引かれる前の金額を指します。
月収とは、年収を12ヶ月で割って1ヶ月分に換算した金額で、平均収入を算出するときの「賃金」は月収を表す場合が多いようです。
また、「基本給」は手当などを含まない、給与のベースになるもので、職種や勤続年数をもとに会社が規定した賃金を指します。企業によって異なる場合もありますが、手当には役職手当・通勤手当・資格手当など金額が固定されているものと、残業代や早朝・深夜手当といった変動するものがあるようです。
月給とは
月給とは、毎月固定で支払われる給与を指します。計算式で表すと「基本給+固定手当」となり、時間外手当や皆勤手当などの変動手当は含まれません。固定手当とは、家族手当や役職手当のように毎月支払われる一定額の変動しない手当のことを指します。
手取りとは
手取りとは、総支給額から保険料や税金などの費用を差し引いた金額です。実際に、自分の銀行へ振り込まれる金額と考えると分かりやすいでしょう。一般的に、手取りは年収や月収の75~85%程度といわれており、給与明細書の「差引支給額」の欄に記載されていることが多いようです。
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
年齢階層別・男女別による平均収入
ここでは、年齢階層別・男女別における平均収入の違いを解説します。国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」のデータをもとに表を作成したので、年齢階層と性別で平均年収にどのような特徴があるかを確認しましょう。
【20代の場合】男性・女性の平均収入
20代の男性・女性の平均年収は、以下のとおりです。
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20~24歳 | 291万円 | 253万円 |
| 25~29歳 | 420万円 | 349万円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査(〔年齢階層別の平均給与〕)(p.21)」
社会人になりたての20代前半は、これからスキルや経験を積んでいく成長段階のため、給与が低めに設定される傾向にあります。そのため、国内における給与の中央値よりも収入が下回りやすいのが現状です。
【30代の場合】男性・女性の平均収入
30代の男性・女性の平均年収は、以下のとおりです。
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 30~34歳 | 485万円 | 338万円 |
| 35~39歳 | 549万円 | 333万円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査(〔年齢階層別の平均給与〕)(p.21)」
30代に突入すると、ある程度の経験を重ね、専門的なスキルが身につくことから、年収アップが見込めます。男女間の収入差が開いていく要因としては、女性が結婚・出産・育児などのタイミングで休職や退職をしたり、非正規雇用勤務を選んだりすることが挙げられるでしょう。
「30歳の平均年収はどれくらい?必要なお金や収入アップのコツを解説」では、30代の平均収入の詳細をまとめています。ぜひご一読ください。
【40代の場合】男性・女性の平均収入
40代の男性・女性の平均年収は、以下のとおりです。
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 40~44歳 | 602万円 | 335万円 |
| 45~49歳 | 643万円 | 346万円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査(〔年齢階層別の平均給与〕)(p.21)」
年齢を重ねるごとに年収が増えている男性に対し、女性は20代後半から40代前半にかけて、ほぼ横ばいとなっています。女性の活躍を推進する企業は年々増えてきており、今後収入格差が改善していく可能性はありますが、現段階では女性の平均収入は男性より低いのが実態です。
【50代の場合】男性・女性の平均収入
50代の男性・女性の平均年収は、以下の表をご確認ください。
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 50~54歳 | 684万円 | 340万円 |
| 55~59歳 | 702万円 | 329万円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査(〔年齢階層別の平均給与〕)(p.21)」
55~59歳のデータを見ると、男性と女性の収入差は373万円と大きく開いています。これらの金額はあくまでも平均のため、職種や勤務地域、勤続年数などによって収入は変化するでしょう。
参照元
国税庁
民間給与実態統計調査
勤続年数別の平均収入
平均収入に影響する要素として、勤続年数も挙げられます。国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」のデータをもとに表にまとめたので、以下で勤続年数と収入の相関関係を見ていきましょう。
| 勤続年数 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1~4年 | 410万円 | 260万円 |
| 5~9年 | 480万円 | 292万円 |
| 10~14年 | 553万円 | 325万円 |
| 15~19年 | 632万円 | 363万円 |
| 20~24年 | 704万円 | 392万円 |
| 25~29年 | 756万円 | 450万円 |
| 30~34年 | 789万円 | 495万円 |
| 35年以上 | 684万円 | 388万円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査(〔年齢階層別の平均給与〕)(p.22)」
平均収入が最も高くなるのは、男女ともに勤続30~34年という結果でした。一方、勤続35年を超えると収入が減少しています。主な理由として、定年退職後に同じ会社で引き続き勤務する場合、正社員以外の雇用形態で働くケースが多いことが考えられるでしょう。
参照元
国税庁
民間給与実態統計調査
都道府県別の平均収入
平均収入は、地域によっても異なります。この項では、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況 都道府県別」を参考に、都道府県別の平均収入(賃金)をまとめました。自分が住んでいる場所の平均収入を確認したり、収入アップを目指して就職・転職先を探したりする際の参考にしてみてください。
平均年収は「地域ごとの経済状況」や「地域ごとに発展している産業の違い」などにより、地域差が生まれるでしょう。
首都圏などの都市部には多くの企業があります。労働者を増やしたい企業は「年収を上げてでも人を雇いたい」と考えるため、結果的に高収入の仕事が多くなり、平均年収が高くなる傾向があるようです。一方で、企業が少ない地域は平均年収が低くなる傾向があります。
また、家賃や物価などの生活費の地域差も年収に影響するでしょう。
北海道・東北の平均収入
北海道と東北地方の平均賃金は、以下のとおりです。
| 都道府県 | 平均賃金 |
|---|---|
| 北海道 | 28万8,500円 |
| 青森県 | 24万9,900円 |
| 岩手県 | 25万9,600円 |
| 秋田県 | 26万1,400円 |
| 宮城県 | 28万8,900円 |
| 山形県 | 25万5,800円 |
| 福島県 | 27万9,400円 |
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況((10) 都道府県別にみた賃金)」
全国の都道府県と比較すると、青森県の平均賃金は最も低いことが分かります。とはいえ、平均賃金が低めの地域は物価が安かったり、独自の産業が発展したりしている場合もあるため、収入面だけで良し悪しを判断するのは難しいでしょう。
関東の平均収入
関東地方の平均賃金は、以下のとおりです。
| 都道府県 | 平均賃金 |
|---|---|
| 茨城県 | 31万1,900円 |
| 栃木県 | 32万3,000円 |
| 群馬県 | 29万6,700円 |
| 埼玉県 | 31万7,200円 |
| 千葉県 | 30万9,500円 |
| 東京都 | 36万8,500円 |
| 神奈川県 | 35万400円 |
| 山梨県 | 29万2,200円 |
| 長野県 | 28万7,700円 |
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況((10) 都道府県別にみた賃金)」
都道府県別の平均賃金を見ると、東京都の収入が一番高いことが分かります。神奈川県と栃木県も平均賃金が高いことから、関東圏は国内でも比較的高収入を見込めるエリアだといえるでしょう。
東海・北陸の平均収入
東海・北陸地方の平均賃金は、以下のとおりです。
| 都道府県 | 平均賃金 |
|---|---|
| 新潟県 | 27万200円 |
| 静岡県 | 30万5,300円 |
| 岐阜県 | 29万2,400円 |
| 愛知県 | 32万1,800円 |
| 三重県 | 30万4,800円 |
| 富山県 | 29万3,900円 |
| 石川県 | 29万400円 |
| 福井県 | 28万5,300円 |
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況((10) 都道府県別にみた賃金)」
東海・北陸地方では、愛知県の平均収入が最も高いと判断できます。そのほかの県では、賃金の差がそれほど大きくないことが東海・北陸地方の特徴です。
近畿の平均収入
近畿地方の平均賃金は、以下の表をご覧ください。
| 都道府県 | 平均賃金 |
|---|---|
| 滋賀県 | 30万2,900円 |
| 京都府 | 31万6,000円 |
| 奈良県 | 30万2,100円 |
| 和歌山県 | 29万8,100円 |
| 大阪府 | 34万円 |
| 兵庫県 | 31万6,800円 |
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況((10) 都道府県別にみた賃金)」
近畿地方では大阪府の平均賃金が高く、全国的に見ても東京、神奈川に続いて3番目に高収入です。同エリア内で収入アップを図るなら、基本給が高めの地域に引っ越し・転職を検討するのも良いでしょう。
中国・四国の平均収入
中国・四国地方の平均賃金は、以下のとおりです。
| 都道府県 | 平均賃金 |
|---|---|
| 鳥取県 | 25万8,300円 |
| 島根県 | 26万8,700円 |
| 岡山県 | 29万800円 |
| 広島県 | 29万6,900円 |
| 山口県 | 29万100円 |
| 徳島県 | 27万1,300円 |
| 香川県 | 27万9,400円 |
| 愛媛県 | 27万9,600円 |
| 高知県 | 27万3,000円 |
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況((10) 都道府県別にみた賃金)」
中国・四国地方では、鳥取県の平均収入が低くなっています。なお、データ上では賃金が少なめであっても、実際は家賃や物価の安さから、収支のバランスを取りやすい可能性も考えられるでしょう。
九州・沖縄の平均収入
九州地方と沖縄県の平均賃金は、以下のとおりです。
| 都道府県 | 平均賃金 |
|---|---|
| 福岡県 | 29万7,300円 |
| 佐賀県 | 26万9,400円 |
| 長崎県 | 25万7,300円 |
| 大分県 | 27万1,400円 |
| 熊本県 | 26万9,000円 |
| 宮崎県 | 25万4,300円 |
| 鹿児島県 | 26万8,300円 |
| 沖縄県 | 26万5,400円 |
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況((10) 都道府県別にみた賃金)」
九州地方・沖縄県においては、福岡県の平均収入が高いことが窺えます。給料が高めの地域に加え、どのような業界なら高収入を得やすいかを知っておくと、効率良く年収アップを目指すことが可能です。
参照元
厚生労働省
令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況
業種・職種別の平均収入
ここでは、業種や職種によって、平均収入がどれほど異なるのかを解説します。業種・職種別に、ランキング形式で平均収入を確認してみましょう。
比較的平均年収が高い業種・職種にはどのような特徴がありますか?
専門性や成果で決まる!高年収職種の特徴とは
比較的平均年収が高い業種や職種にはいくつかの共通点があります。まず、専門性が高い仕事ほど高年収の傾向があるでしょう。たとえば、ITや金融、医療業界では専門的な知識や技術が求められ、経験や資格が年収に反映されやすい傾向があります。また、マネジメント職や営業職では、結果に応じた報酬が得られるため、実力次第で年収が大きく伸びる可能性があるでしょう。
さらに、グローバルなビジネスが関わる職種、例として外資系企業や海外との取引が多い業界も高年収の傾向があります。これらの職種では、語学力や異文化理解といったスキルが求められるため、特定のスキルが加味されることで給与が上昇する場合もあるでしょう。
一方で、年収が高い職種では責任やプレッシャーが大きくなる可能性も考えられます。そのため、ご自身の性格や価値観、ライフスタイルに合った業界・職種を選ぶことをおすすめします。
業種別の平均収入ランキング
国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、業種別の平均年収は以下のとおりでした。
| ランキング | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 747万円 |
| 2位 | 金融業・保険業 | 656万円 |
| 3位 | 情報通信業 | 632万円 |
| 4位 | 学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業 | 544万円 |
| 5位 | 製造業 | 533万円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査(〔業種別の平均給与〕)(p.20)」
平均年収が最も高い業種は「電気・ガス・熱供給・水道業」で747万円。次いで、「金融業・保険業」が656万円、「情報通信業」が632万円でした。これらの結果から、人々の生活を支えるインフラ業界は平均年収が高い傾向にあることが分かります。
なお、同調査の結果は正社員のみではなく、非正規雇用社員も含めたものです。平均収入が最も低いとされる「宿泊業・飲食サービス業」は、アルバイト・パート社員の比率が高い傾向にある業種のため、金額が低くなっているとも考えられます。
「平均年収を比較!年齢・業界別の金額や給与アップの方法をご紹介」のコラムでも、業種別の平均収入をご紹介しているので、ぜひご覧ください。
職種別の平均収入ランキング
厚生労働省の「労働統計要覧」をもとに、2022年における職種別の平均収入を、上位5位までランキングでまとめました。どのような職種が高収入で、職種ごとに平均収入はどれほど異なるのかについて、以下を参考にしてみてください。
| ランキング | 職種 | 所定内給与額(男女計:2022年6月) |
|---|---|---|
| 1位 | 航空機操縦士 | 128万5,400円 |
| 2位 | 医師 | 97万800円 |
| 3位 | 大学教授(高専含む) | 65万8,600円 |
| 4位 | 歯科医師 | 61万4,300円 |
| 5位 | 法務従事者 | 54万9,800円 |
参照:厚生労働省「労働統計要覧 令和5年度(E 賃金 24_職種、性別所定内給与額)」
平均年収が高い職種は、航空機操縦士や医師、大学教授など専門職が多い傾向にあります。特別なスキルや資格が必須となる職種は、簡単に目指せる仕事ではないものの、年収アップを図りたい方はチャレンジしてみるのも手です。
高収入の職種に興味のある方は、「高収入の仕事29選!無資格・未経験から年収アップを目指す方法を解説」をご参照ください。平均収入より高い給与を得るためのヒントが見つかるでしょう。
参照元
国税庁
民間給与実態統計調査
厚生労働省
労働統計要覧
事業所・企業規模別の平均収入
事業所規模や企業規模の違いによっても、平均収入が異なる場合があります。ここでは、国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」をもとに、事業所・企業規模別の平均収入を確認してみましょう。
事業所規模別の平均収入
事業所規模別の平均年収は以下のとおりです。なお、平均年収額には平均賞与額も含まれています。
| 事業所規模 | 平均年収 | うち平均賞与 |
|---|---|---|
| 10人未満 | 371万1,000円 | 23万7,000円 |
| 10~29人 | 424万8,000円 | 44万7,000円 |
| 30人以上 | 477万7,000円 | 84万3,000円 |
| 合計平均 | 457万6,000円 | 71万6,000円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査(〔事業所規模別の平均給与〕)(p.18)」
同調査では、事業所規模が大きいほど、平均年収と平均賞与は高くなるという結果になりました。主な理由として、事業所規模が大きいと生産性が上がり、利益につながりやすくなることが考えられます。
企業規模別の平均収入
次に、企業規模別の平均年収を見ていきましょう。前の項目と同様、平均年収額には平均賞与額が含まれています。
| 企業規模(資本金) | 平均年収 | うち平均賞与 |
|---|---|---|
| 2,000万円未満 | 391万2,000円 | 33万9,000円 |
| 2,000~5,000万円未満 | 425万5,000円 | 56万4,000円 |
| 5,000万~1億円未満 | 428万7,000円 | 66万7,000円 |
| 1~10億円未満 | 473万円 | 83万4,000円 |
| 合計平均 | 479万2,000円 | 78万円 |
参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査(〔企業規模別の平均給与〕)(p.19)」
企業規模別に見た場合、資本金の金額が上がるほど従業員の平均年収も高くなるようです。平均収入より高い給与を目指すなら、大手企業へ就職するのも方法といえるでしょう。
参照元
国税庁
民間給与実態統計調査
収入を考えたら大手企業に就職したほうが良い?
大手企業だからといって、必ずしも優良企業とは限りません。事業所・企業規模は、収入面で見る際の要素の一つと判断しましょう。大手企業にも中小企業にも、それぞれ就職するメリット・デメリットがあります。自分に合った企業選びに悩む方は、「大企業と中小企業の違いは?両者に就職するメリット・デメリットもご紹介」のコラムを参考にしてみてください。学歴別の平均収入
最終学歴も、収入に影響する要素の一つです。ここでは、厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査 (3) 学歴別にみた賃金」をもとに、学歴別の平均収入(賃金)を見ていきます。
| 学歴 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 高校 | 30万6,100円 | 23万500円 |
| 専門学校 | 32万5,600円 | 27万1,800円 |
| 高専・短大 | 35万4,900円 | 27万3,500円 |
| 大学 | 39万9,900円 | 29万9,200円 |
| 大学院 | 49万1,100円 | 40万7,800円 |
参照:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 (3) 学歴別にみた賃金」
男女ともに、大学院卒の平均賃金が最も高いことが分かりました。また、高卒と大卒の男性を比較したとき、平均賃金が9万円以上異なることから、給与を決定する際に学歴を指標とする企業が多いとも考えられるでしょう。
参照元
厚生労働省
令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況
雇用形態別(正社員・非正規雇用社員)の平均収入
この項では、正社員と非正規雇用社員の平均収入の違いをまとめました。国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、それぞれの平均年収は以下のとおりです。
| 雇用形態 | 平均年収(全体) | 平均年収(男性) | 平均年収(女性) |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 523万円 | 584万円 | 407万円 |
| 非正規雇用社員 | 201万円 | 270万円 | 166万円 |
参照:国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査(2 平均給与)(p.15)」
男女合わせた全体の平均年収では、正社員と非正規雇用社員の差は約320万円と非常に大きいのが分かります。また、男女別に見ると、どちらの雇用形態においても女性に比べて男性のほうが平均年収が高い傾向にあるようです。
ただし、アルバイトの収入は時給か月給かによっても変わります。非正規雇用社員の収入について詳しく知りたい方は、「フリーターの平均年収は?20代・30代の年齢別に正社員の収入と比較」をご覧ください。
参照元
国税庁
民間給与実態統計調査
日本人の平均収入で実現できる生活レベル

日本人の平均収入である458万円で、どのような暮らしを叶えられるのか気になる方もいるでしょう。下記では、単身や2人以上といった、生活スタイル別の暮らしのポイントと貯蓄について解説します。
単身で暮らす場合
家賃相場の高い東京都であっても、正社員で1人暮らしの場合、比較的余裕のある生活を送れるでしょう。ただし、時給制で働くフリーターや派遣といった非正規雇用社員は、病気や自然災害などのトラブルがあると収入が減る恐れもあるため、日ごろから節約しておくと安心です。
自分らしい生活を続けられるか不安に思う方は、「フリーターの一人暮らしはきつい?審査や家賃の気になる疑問を解決!」で、必要な費用を確認してみましょう。
フリーターの方が貯蓄するコツは「先どり貯蓄」
貯蓄は、結婚・出産・教育費などのライフイベントに備えるほか、夢や目標を実現するための資金になります。
フリーターの方が貯蓄するには、毎月の収入と支出を把握し、余分な支出を減らす工夫が必要です。たとえば、外食を減らして自炊したり、ネットショッピングやサブスクなどサービスの利用による無駄な支出がないかをチェックしたりと、お金の使い方を見直すことがポイントです。
「生活費にお金がかかり、貯蓄ができない」とお悩みの場合は「先取り貯蓄」をおすすめします。貯蓄専用の口座を開設し、バイトなどの収入を受けとったら、あらかじめ決めておいた額を貯蓄専用の口座に入金し、専用口座のお金は使わずに貯めておく……という簡単なものです。貯蓄する習慣をつけることが、貯金を増やすコツです。
また、正社員として就職する道もあります。正社員となって収入を増やせると、貯蓄しやすくなります。生活が安定することに加え、キャリアアップすることで収入を増やすチャンスも広がるでしょう。
2人以上で暮らす場合
2人とも正社員同士で暮らす場合は、経済的に安定して過ごせる可能性が高いようです。貯蓄もしやすいため、将来的に出産・育児を考えている方も安心できるでしょう。
どちらかが正社員で、どちらかが非正規雇用社員の場合は、ある程度の節約が求められます。また、家庭に子どもや介護が必要な家族が含まれる場合は、無理のない生活をするためにも、イベントや治療に向けて、あらかじめ出費のスケジュールを考えておくのがおすすめです。
1世帯あたりの平均貯蓄
厚生労働省の「2022年 国民生活基礎調査の概況 II 各種世帯の所得等の状況」によると、1世帯当たりの平均貯蓄額は以下のようになっています。
| 世帯 | 平均貯蓄額 |
|---|---|
| 全世帯 | 1,368万3,000円 |
| 高齢者世帯 | 1,603万9,000円 |
| 高齢者世帯以外の世帯 | 1,248万4,000円 |
| 児童のいる世帯 | 1,029万2,000円 |
| 母子世帯 | 422万5,000円 |
参照:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況(5 貯蓄、借入金の状況)(p.12)」
上記のデータを参考にすると、平均貯蓄額は高齢者世帯が高く、母子世帯は低いのが現状です。世帯年齢を重ねるにつれて昇給・昇進を目指せるほか、原則60歳以上は定年退職の対象となるため、退職金を受け取った高齢者を含む世帯は、まとまった貯蓄を確保しやすいと考えられるでしょう。
参照元
厚生労働省
2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況
平均収入をアップさせるための4つの方法

平均収入よりも高い給与を目指す方法として、「昇給」「副業」「資産運用」「転職」などが挙げられます。これから給与アップを狙いたい方は、以下の方法を参考にしてみてください。
年収を引き上げるには「実績」と「ネットワーク」が大切
平均年収を引き上げるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。まずは、「スキルの向上」が大きな要素となるでしょう。特に市場で需要の高いスキルを習得することで、年収は上がりやすくなります。
たとえば、ITやデータ分析、AI関連などの技術的スキルや、営業力やマネジメント力も高評価されるスキルです。それらのスキルを高めることで、キャリアの選択肢は広がり、昇進や転職時の交渉で有利になるでしょう。
次に重要なのは、ネットワークの構築です。業界内での人脈を広げ、情報収集を行うことで、より高収入のチャンスを得られる可能性が高まります。成果主義の職場環境であれば、実績を上げることで年収アップが期待できるでしょう。特に営業職やマーケティング職では、成果に応じた報酬体系が多いため、結果を出すことが直接的な年収アップにつながります。
最後は、転職やキャリアチェンジによる年収の引き上げです。自分に合った業界・職種で経験を積み、待遇の良い企業に移ることで年収を上げるのも手段としてあります。
平均収入をアップさせるための方法
- 昇給を目指す
- 副業で収入を得る
- 資産運用を行う
- 転職する
1.昇給を目指す
平均収入よりも高い給与を目指すなら、今の会社で昇給のチャンスを狙いましょう。給与アップと聞くとすぐに転職を考える方も少なくありませんが、経験が浅い場合は、まず現職で収入を増やす手段を考えるのが賢明です。
たとえば、資格手当がある会社なら、対象となる資格を取得するという方法があります。また、実力が給与に反映される環境では、実績を積んで賞与アップや昇進を目指すこともできるでしょう。昇進すれば、基本給が上がったり、役職手当を得られたりする可能性が高まります。
2.副業で収入を得る
本業にプラスして副業を行うのも、平均収入をアップさせるための方法の一つです。今の仕事のすきま時間や休日に副業をする場合、体力面や精神面で一定の大変さがありますが、働けば働いたぶん収入に反映されるという魅力があります。ただし、従業員の副業を認めていない会社もあるため、実施の可否を必ず就業規則で確認してください。
3.資産運用を行う
貯蓄額に余裕のある方は、資産運用で収入アップを目指すのも手です。最近では、NISAのような初心者向けの投資方法が展開されているので、自分に合った運用方針を検討してみましょう。
なお、資産運用には期待以上のリターンを受けられないまま損失したり、利子や元本が支払われなかったりと、いくつかのリスクがあります。資産運用を考えている方は、具体的な運用方法や、リスクとリターンの関係性をしっかり理解しておくことが重要です。
4.転職する
今の職場で平均収入以上の給与が見込めない場合、退職してほかの会社へ転職する道もあります。会社の業績が悪かったり評価制度が確立していなかったりする職場では、自身の頑張りが給与に反映されにくいでしょう。また、役職のポストが埋まっていると昇進が望めず、直近のキャリアアップは難しいといえます。
「努力に見合った収入が欲しい」という方は、実力主義の職場へ転職するのがおすすめです。
非正規雇用社員の収入アップは正社員を目指そう!
フリーターや派遣といった非正規雇用社員は、今より給与が良いアルバイト先(派遣先)を探すよりも、正社員を目指して収入アップを図るのがおすすめです。有期雇用契約の場合、たとえ高時給の職場に出会えても長期的に働けるとは限りません。年齢が若いほど正社員就職のチャンスは豊富なため、現在の収入に不安がある非正規雇用社員の方は、早めに行動するのが良いでしょう。「フリーターから就職する方法は?正社員になるメリットとおすすめの職種!」のコラムでは、正社員を目指すためのノウハウを解説しています。未経験から育成できる若手が欲しい企業は多いため、ぜひ正社員就職に向けてチャレンジしてみてください。
転職先選びで注目したい収入以外の4つのポイント

収入アップを目指して転職する場合、「勤務形態」「環境」といった、基本給や手当以外のポイントにも目を向けましょう。収入面だけで転職先を選ぶと、入社後に「思っていた会社と違った」「収入は良くても人間関係が良くない」などのミスマッチを起こす恐れがあります。早期退職を防ぐためにも、以下の項目をしっかり確認することが重要です。
転職先選びで注目したい収入以外のポイント
- 福利厚生が整っているか
- 実現したい働き方が叶えられるか
- 職場の立地や雰囲気が自分に合っているか
- 自分の能力や経験を活かせるか
1.待遇面:福利厚生が整っているか
求人を見る際は、給与だけでなく待遇面も確認しましょう。働き方が多様化する昨今では、従業員の生活をサポートする独自の福利厚生を設ける企業が増えています。
たとえば、食事補助や家族手当が充実している企業であれば、求人ページに記載されている給与以上の収入になり、ゆとりをもった生活が叶う可能性も。場合によっては、「福利厚生が充実している企業」のほうが高い収入を得られることも考えられます。
2.勤務形態面:実現したい働き方が叶えられるか
求人票を確認するときは、賃金欄に「みなし残業代」や「固定残業代」が含まれているかどうかもチェックが必要です。このような表記がある場合、基本的に残業込みの賃金で設定されているため、時間外労働をしたくないと考えている方には不向きといえます。仕事とプライベートにメリハリをつけた働き方を希望するなら、「完全週休2日制」「年間休日120日以上」といった表記にも着目しましょう。
3.環境面:職場の立地や雰囲気が自分に合っているか
勤務地や職場の雰囲気のように、応募先企業の環境面を見ることも大切です。たとえ高給であっても、通勤に多大な時間がかかってしまっては、プライベートとの両立は難しいといえます。
また、職場の雰囲気が合わなかったり、実力をきちんと評価してもらえなかったりする環境下では、ストレスが溜まりやすく、結果的に早期退職につながる恐れも。転職の際は、「自分にとって働きやすい環境かどうか」をしっかり見極めましょう。
4.スキル面:自分の能力や経験を活かせるか
平均収入アップを目的とした転職では、これまでの経験やスキルを活かせる職場を選ぶのも重要なポイント。即戦力としてやりがいをもって働けるだけでなく、より専門性を高めることで、将来的に役職に就ける可能性もあるでしょう。目の前の給与だけに注目するのではなく、長期的に力を発揮できる仕事かを吟味するのが大切です。
転職活動のコツも押さえよう
転職を成功させるには、応募書類の作成や面接対策といった基本を丁寧に行いましょう。作り込まれた応募書類は採用担当者の目に留まりやすくなるほか、面接で定番の質問に対する回答をあらかじめ用意しておけば、本番でも迷うことなく自分をアピールできます。これから転職を検討する方は、「転職のありがち失敗例を紹介!後悔しない選択と成功のコツとは」で成功のポイントをチェックしましょう。仕事探しや転職準備を不安に思うなら、転職エージェントに相談するのもおすすめですよ。ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
平均収入の実態を知り、「より良い職場へ転職したい」「フリーターから正社員に就職したい」とお考えの方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
ハタラクティブでは、最初のカウンセリングで「平均収入より高い収入」「スキルを活かせる仕事」などの希望条件を確認したうえで、あなたに合った求人をご紹介します。専任のキャリアアドバイザーが、就職・転職活動で悩みがちな応募書類の作成や面接対策を手厚くフォローするため、初めて求職活動する方も安心です。
また、直接企業側に聞きにくい給与面や待遇面については、ハタラクティブが会社とのやり取りを代行します。サービスはすべて無料のため、一人での就職・転職活動が不安な方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
平均収入に関するQ&A
ここでは、平均収入について想定される疑問をQ&A形式で回答いたします。
平均収入が高い都道府県はどこですか?
平均収入が高い都道府県は、東京都・神奈川県・栃木県・大阪府・愛知県などが挙げられます。反対に平均年収が低いのは、青森県・宮崎県・山形県などです。地方都市に比べて、関東圏や関西圏の大都市のほうが平均収入は高い傾向にあります。
詳しくは「都道府県別の平均収入」で解説しているので、参考にしてみてください。
正社員の平均収入はいくらですか?
正社員の平均収入は523万円です。雇用形態別で相対的に見た正社員の年収は、このコラムの「雇用形態別(正社員・非正規雇用社員)の平均収入」をご参照ください。
また、「正社員の平均給料はどれくらい?フリーターとの差は?年齢別の給与も紹介」のコラムでも正社員の平均月収について解説しています。あわせてご一読ください。
平均収入より稼げる業種を教えてください
平均収入より稼ぎやすい業種には、「電気・ガス・熱供給・水道業」「金融業・保険業」「情報通信業」などが挙げられます。「製造業」や「建設業」なども、比較的収入が高い傾向にあるようです。詳しくは「業種・職種別の平均収入」をご確認ください。
ほかにも、「高収入を目指せる正社員求人とは?給料が高い職種ランキングも紹介」では、高収入を目指しやすい職種をまとめているので、参考にしてみてください。
平均収入より自分の給与が低くて不安です…
20代前半で入社して間もない方は、平均収入より給与が下回ることはよくあります。スキルアップや経験を積むうちに収入アップしていくでしょう。入社してしばらく経ち、努力しても収入が上がらない場合は、転職するのも一つの手です。
就職・転職支援サービスのハタラクティブでは、収入アップを叶えやすい求人をご紹介。経験豊富なキャリアアドバイザーが転職活動の基本をお教えするだけでなく、応募から内定獲得まで手厚いサポートを行います。ぜひお気軽にご相談ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
この記事に関連する求人
未経験の方も開発の上流工程からデビュー可能◎半導体エンジニアの求人
半導体エンジニア職(長崎県諫早…
長崎県
年収 251万円~388万円
未経験から始められる研修体制◎通信環境の点検などを行うルート営業☆
ルート営業
滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県…
年収 228万円~365万円
未経験者が多数活躍★人材紹介会社で営業職として活躍しませんか?
営業
東京都
年収 328万円~374万円
未経験OK◎開業するクリニックの広告全般を担当する企画営業職の募集
企画営業職
大阪府
年収 252万円~403万円
語学力を活かしたい方必見!外資系・グローバル系企業の事務職を募集◎
貿易事務
埼玉県/千葉県/東京都/神奈川…
年収 258万円~295万円
- 「ハタラクティブ」トップ
- 就職・再就職ガイド
- 「お悩み」についての記事一覧
- 「仕事の悩み」についての記事一覧
- 「給料の悩み」についての記事一覧
- 平均収入の実態を年代・男女・地域別に紹介!年収アップの方法も解説