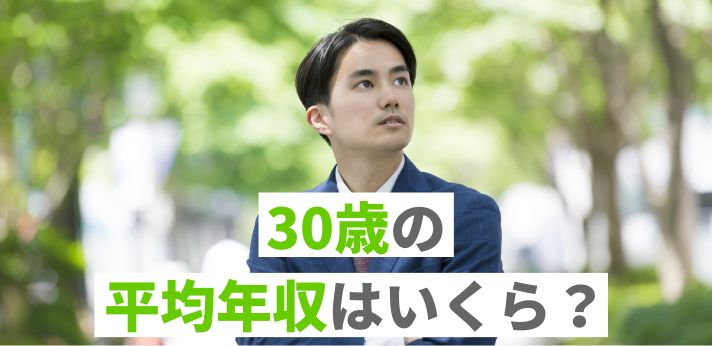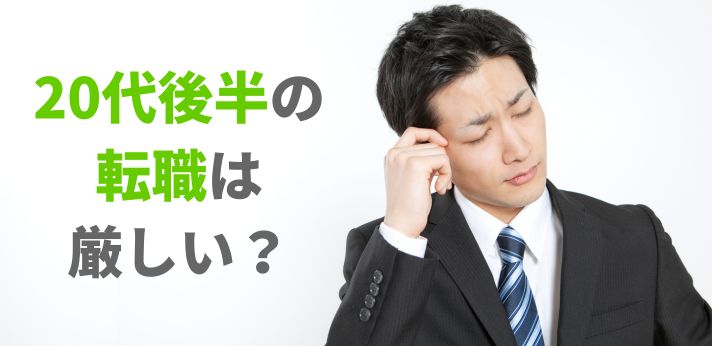27歳の平均年収は?男女別の年収や収入を上げる方法をご紹介!27歳の平均年収は?男女別の年収や収入を上げる方法をご紹介!
更新日
公開日
27歳を含む20代後半の平均年収は394万円で、手取り年収に換算すると312万円ほど
働くなかで、「27歳の平均年収はどれくらい?」「自分の年収は平均と比べて低い?高い?」と疑問をもつ方もいるでしょう。20代後半の平均年収は約390万円です。ただし、平均年収は雇用形態や学歴、地域によっても異なるため、自分の年収と比較する際は雇用形態や学歴といった条件もチェックしておきましょう。
このコラムでは、27歳を含む20代後半の平均年収や手取りに換算した場合の年収・月収を解説します。また、雇用形態や性別、事業所規模など条件別の平均年収や、年収を上げる主な方法もご紹介。自分に合ったやり方で年収を上げるために、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
27歳の平均年収(ボーナス込み)は390万円前後
27歳の平均年収は、390万円前後といわれています。年収は給料や手当、ボーナスを含んだ合計額です。
| 年齢階層 | 男性 | 女性 | 男女計 |
|---|
| 20~24歳 | 279万円 | 253万円 | 267万円 |
| 25~29歳 | 429万円 | 353万円 | 394万円 |
| 30~34歳 | 492万円 | 345万円 | 431万円 |
| 35~39歳 | 556万円 | 336万円 | 466万円 |
正規雇用・非正規雇用を含めた25〜29歳の平均年収は、男性429万円、女性353万円、全体で394万円でした。20代後半を対象にしたデータではあるものの、27歳の平均年収も上記の数字に近いと考えられるでしょう。
27歳正社員の平均年収
※想定年収は「きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額」で計算
【正社員・正職員の想定年収】
| 正社員・正職員 | 男性 | 女性 | 男女計 |
|---|
| きまって支給する現金給与額 | 31万9,300円 | 28万9,100円 | 30万6,200円 |
| 年間賞与その他特別給与額 | 80万9,100円 | 68万3,500円 | 75万4,500円 |
| 想定年収 | 464万700円 | 415万2,700円 | 442万8,900円 |
25~29歳の正社員・正職員の想定年収は、男女計で442万8,900円でした。男女別ではいずれも平均年収は400万円を超えているものの、男性のほうがきまって支給する現金給与額・年間賞与ともに高い傾向があると分かります。
【正社員・正職員以外の想定年収】
| 正社員・正職員以外 | 男性 | 女性 | 男女計 |
|---|
| きまって支給する現金給与額 | 26万5,800円 | 23万5,400円 | 24万7,700円 |
| 年間賞与その他特別給与額 | 11万1,300円 | 9万8,700円 | 10万3,800円 |
| 想定年収 | 330万900円 | 292万3,500円 | 307万6,200円 |
正社員・正職員以外の想定年収は、男女計で307万6,200円でした。内訳を正社員と比較すると、きまって支給する現金給与額は6万円ほど、年間賞与は65万円ほどの差があることに。結果的に、雇用形態によって平均年収に100万円以上の違いが生じています。
27歳以降の男性・女性ごとの平均年収の推移
なかには、「27歳以降の平均年収はどのように増えていくのか」と疑問に思っている方もいるでしょう。国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、27歳以降の男性・女性ごとの平均年収は以下のように推移します。
| 男性 | 男性 | 女性 | 男女計 |
|---|
| 30~34歳 | 492万円 | 345万円 | 466万円 |
| 35~39歳 | 556万円 | 336万円 | 466万円 |
| 40~44歳 | 612万円 | 343万円 | 501万円 |
| 45~49歳 | 653万円 | 343万円 | 521万円 |
| 50~54歳 | 689万円 | 343万円 | 540万円 |
| 55~59歳 | 712万円 | 330万円 | 545万円 |
| 60~64歳 | 573万円 | 278万円 | 445万円 |
| 65~69歳 | 456万円 | 222万円 | 354万円 |
| 70歳以上 | 368万円 | 197万円 | 293万円 |
男性は年齢を重ねるにつれて平均年収も上がっていく傾向があり、一番高いのは55~59歳の712万円でした。一方、女性は年齢による差があまり大きくなく、330~340万円前後を推移しています。
ただし、上記のデータは正社員・正社員以外の年収を合算して求められたものです。そのため、正社員として働き続けた場合に上記のような差が生じるとは限らない点に注意が必要といえます。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
27歳の平均手取り年収はおよそ312万円
27歳の平均年収の場合、手取り年収はおよそ312万円です。月々の給与からは税金や社会保険料が控除されるもので、一般的に手取り額は額面の80%前後といわれています。住んでいる自治体によって細かい控除額は異なるものの、390万円の80%である312万円前後が27歳の手取り年収の目安となるでしょう。
手取り月収に換算するとおよそ26万円
27歳の平均年収に近い年収390万円の場合、手取り月収はおよそ26万円と考えられます。毎月もらっている給与と比較することで、自分の年収が平均より高いか低いかおおよその判断ができるでしょう。
ただし、上記は想定される手取り年収を12で割って求めているので、ボーナスが考慮されていない点に注意が必要です。手取り月収が26万円より低くても、ボーナスを合わせれば手取り年収が312万円以上になる可能性は十分にあるため、あくまでも目安としてご覧ください。
20代の手取り月収の中央値は?
ハタラクティブの独自調査「若者しごと白書2025 雇用形態別手取り月収の分布」によると、20代の手取り月収の中央値は正社員が「20~23 万円未満」、フリーターが「10~15 万円未満」でした。調査対象は18~29歳のため一概に比較はできないものの、どちらも27歳の平均手取り月収より低いことが分かるでしょう。
平均値はすべてのデータを足してデータの数で割ったもので、データを均等にならした数値が求められます。一方、中央値はデータを小さい順に並べたときに、ちょうど真ん中にくる数値のこと。極端に高いデータや低いデータの影響を受けにくいため、中央値のほうが実態に即していると考えることもできます。
参照元
ハタラクティブ
若者しごと白書2025 あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
27歳の平均年収を決める主な6つの要因
一口に27歳の平均年収といっても、性別や雇用形態、学歴、会社の規模など、さまざまな要因により数値は変わります。この項では、27歳の年収を決める主な要因と、それぞれの平均年収について詳しく解説しています。自分の状況に当てはめ、今の年収が適切かどうか確認する参考にしてみてください。
1.性別
性別によって、27歳を含む20代後半の平均年収に差が出ることがあります。このコラムの「27歳以降の男性・女性ごとの平均年収の推移」で紹介したように、男性の平均年収は年齢を重ねるにつれ高くなっていく一方で、女性の平均年収は年齢にかかわらず330~340万円前後でした。
性別によって平均年収が異なる主な理由として考えられるのは、女性のほうが結婚や出産、子育てといったライフイベントによる影響を受けやすいことです。正社員から非正規雇用に切り替えたり、時短勤務で働き方をセーブしたりすることで収入が下がり、平均年収に差が生じていると推察できます。
実際、総務省統計局の「労働力調査(詳細集計) 2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、非正規の職員・従業員についた理由として「家事・育児・介護等と両立しやすいから」と回答した割合は、男性が1.4%、女性が15.5%でした。近年女性の働き方は多様化してきているものの、ライフスタイルの変化が女性に与える影響は、男性と比べて大きいと考えられるでしょう。
2.雇用形態
27歳の平均年収は、雇用形態によっても異なります。このコラムの「27歳正社員の平均年収」で紹介したように、27歳を含む20代後半の平均賃金から想定される年収は、正社員が442万8,900円、非正規社員が307万6,200円。正規雇用かそうではないかによって、想定年収に100万円以上の差がある結果になりました。
雇用形態によって年収に差が出るのは、給与形態やボーナスの有無が要因と考えられます。正社員は1ヶ月ごとに決められた給与が支払われる月給制のことが多く、月収が安定している傾向があります。勤続年数やスキル、評価によっては1万円単位での昇給が望め、27歳で収入アップを実現することも可能です。また、ボーナスが支払われる会社に就職すれば、月収以外にまとまった収入を得られます。
一方、非正規社員の場合、働いたぶんだけお金を稼げる時給制であることが一般的。休んだぶん給与が下がってしまうほか、昇給したとしても時給が数十円上がる程度なので、大きな昇給にはつながらないことも。また、非正規社員にはボーナスを支給しない会社がほとんどのため、その差が平均年収に大きく影響していると考えられます。
20代の雇用形態別の年収については「20代フリーターの年収はどのくらい?正規・非正規雇用(正社員)の収入差も紹介」のコラムで詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。
3.学歴
大卒や高卒などといった学歴によって、基本給(手当を含まない基本賃金)に差が出る場合もあります。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、25~29歳の学歴別の平均賃金は以下の通りでした。
| 最終学歴 | 男性 | 女性 | 男女計 |
|---|
| 高卒 | 25万2,600円 | 22万3,700円 | 24万3,000円 |
| 大卒 | 29万300円 | 27万6,700円 | 28万3,900円 |
| 大学院卒 | 31万6,300円 | 29万6,100円 | 31万1,600円 |
男女ともに、高卒より大卒や大学院卒のほうが平均賃金が高いことが分かります。また、大卒と大学院卒を比べると、大学院卒のほうが平均賃金が高いようです。学歴によって平均賃金が異なる理由としては、大学入学のための努力や、教育機関で得た専門知識や教養が評価されていることが考えられます。
4.地域
地方よりも、大都市のほうが平均年収は高い傾向があります。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況(11)都道府県別にみた賃金」によると、平均賃金がもっとも高いのは東京都で、40万3,700円。また、2位の神奈川県が35万5,800円、3位の大阪府が34万8,000円と続きます。一方、もっとも低い宮崎県は25万9,800円となっており、15万円近くの差があることが分かります。
都心部や大都市には大きな企業や優秀な人材が集まりやすく、そのぶん平均年収も高くなりやすいようです。
5.資格
特定の資格をもつ社員に、資格手当を支給する企業もあります。企業や資格の種類によって手当の金額は異なりますが、毎月数千〜数万円支給されることもあり、資格の有無によって同じ27歳でも年収に差が生じる可能性があるでしょう。
なお、手当を支給される資格は企業によって決められており、その業界や職種に必要な知識・技術を証明できるものや、取得することで業務の幅が広がるものなどが挙げられます。具体的には、介護職なら介護福祉士、経理職なら日商簿記1級などが対象となるでしょう。
6.事業所規模
事業所規模によっても、平均年収は異なります。以下の表は、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」にて、事業所規模別に算出した27歳前後(25~29歳)の平均年収のデータです。
| 事業所規模別 | 年収額 |
|---|
| 10人未満 | 316万3,000円 |
| 10人以上 | 325万9,000円 |
| 30人以上 | 361万5,000円 |
| 100人以上 | 380万4,000円 |
| 500人以上 | 412万8,000円 |
| 1,000人以上 | 441万1,000円 |
| 5,000人以上 | 438万5,000円 |
事業所規模が5000人以上と10人未満の企業では、年収に100万円以上の違いがあることが分かります。一般的に、企業規模が大きいほど原料を大量に安く仕入れられたり大量生産できたりして、安定した利益や売上を実現しやすいもの。そのぶん従業員の給与やボーナスに還元できるため、平均年収も上がる傾向があるようです。
27歳の業種別平均年収
生活に欠かせない商品やサービスを提供する業界は平均年収が高い
応募する会社を検討する際に「少しでも多くの給料を手にしたい」と考えるなら、その会社の平均年収は気になるものですね。
平均年収が高い業界には「専門性が高い」「付加価値が高い」「生活に必要なサービスを提供している」など、いくつかの特徴があります。
具体的には、私たちの暮らしに欠かせないライフラインを支える電気・ガス・水道などの業界、お金の取り扱う金融業界や保険業界、スマートフォンやパソコンなどの通信を支えるIT業界や情報通信業界、住宅やビル、施設などの建築・維持を担う建設業界などが挙げられます。
平均年収の高い業界は、私たちの生活に欠かせない商品やサービスを提供し、経済の発展を支えていることから、仕事に求められるスキルや知識レベルが高くなりやすいでしょう。そうした業界に未経験で就職を目指すには、資格取得などの自己研鑽とともに、自己分析を深めて強みを具体的にアピールすることがポイントです。
| 業種 | 年収額 |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 513万9,000円 |
| 金融業・保険業 | 503万5,000円 |
| 情報通信業 | 467万4,000円 |
| 建設業 | 439万2,000円 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 438万4,000円 |
| 運輸業・郵便業 | 422万8,000円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業 | 422万8,000円 |
| 製造業 | 414万8,000円 |
| 複合サービス事業 | 376万4,000円 |
| 医療・福祉 | 365万2,000円 |
| サービス業 | 365万1,000円 |
| 卸売業・小売業 | 356万6,000円 |
| 農林水産・鉱業 | 332万9,000円 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 296万6,000円 |
上記より、「電気・ガス・熱供給・水道業」「金融業・保険業」「情報通信業」の順に平均年収が高いことが分かりました。一方で、サービス業や医療・福祉業界、農林水産業といった業界は、27歳の平均年収である390万円よりも低い数値となっています。
27歳の平均年収で一人暮らしすることは可能
| 項目 | 月平均額 |
|---|
| 食料 | 4万8,204円 |
| 住居 | 2万3,373円 |
| 光熱・水道 | 1万2,817円 |
| 家具・家事用品 | 5,938円 |
| 被服及び履物 | 5,175円 |
| 保険医療 | 8,502円 |
| 交通・通信 | 2万564円 |
| 教育 | 9円 |
| 教養娯楽 | 2万375円 |
| その他の消費支出 | 2万4,592円 |
| 消費支出 | 16万9,547円 |
上記より、単身世帯の1ヶ月の消費支出金額は、およそ17万円と分かります。先述したとおり、27歳の平均年収を手取り月収に換算すると約24万円なので、上記の金額を基準とすれば一人暮らしは実現できるでしょう。
結婚や子育てをするには余裕がない可能性もある
27歳の平均年収では、結婚や子育てに掛かるコストをすべてまかなうのは難しい可能性があります。先述の総務省の統計によると、単身世帯の消費支出はおよそ17万円だった一方で、2人以上の世帯は約30万円でした。家族が増えると光熱費や食費、医療費といった支出が増えるのが一般的。27歳の平均年収では、まかないきれない可能性があります。
結婚や子育てを実現するには、「パートナーと共働きで稼ぐ」「実家で同居して固定費を抑える」といった対策が必要になることも。パートナーと今後の収入や見通しについて話し合い、無理のないプランを立てる必要があるでしょう。
パートナーの年収によっては配偶者控除が受けられる
パートナーの年収によっては配偶者控除が受けられ、税負担を軽くできる可能性があります。国税庁の「No.1191 配偶者控除」によると、配偶者控除とは「納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられ」る制度のこと。所得税の基礎控除の見直しにより、パートナーの収入が給与だけの場合、年収123万円以下なら控除が受けられるようになりました。控除されるぶん所得税の負担が軽くなるため、生活にゆとりができる可能性があるでしょう。
配偶者控除について、詳しくは「
配偶者控除とは?計算方法や対象条件などについて紹介!」のコラムで解説しています。あわせて参考にしてみてください。
27歳の平均年収で無理なく生活するための3つのポイント
ここでは、先述した27歳の平均手取り月収26万円を基準に、無理なく生活するための3つのポイントを紹介します。経済的な不安を解消してゆとりのある一人暮らしを実現するために、参考にしてみてください。
1.支出を把握して家計のバランスを考える
まずは支出を把握して、家計のバランスを考えることが大切です。最初に家賃や通信費、生命保険など毎月決まった金額が掛かる固定費を把握し、今のままで良いか考えてみましょう。たとえば、電気やガスの基本料金や携帯の定額サービスなどのプランを変更できないか見直すことで、支出を抑えられる可能性があります。
また、被服費や交際費などそのときどきで金額が変わる変動費は、日々の生活のなかで節約することが可能です。「服は季節の変わり目に整理して必要なぶんだけ買う」「遊びの予定は月に×回までにする」などの対策を試してみましょう。
2.家賃の目安は手取り額の3分の1を意識する
賃貸住宅においては、家賃を手取り額の3分の1に抑えるのが望ましいとされています。手取り月収が26万円の場合、家賃の目安は約8万6,000円です。
若い世代は手取り額が少ないことから、消費支出のなかでも家賃が特に割合を占めがちといえます。3分の1を上回ってしまうとほかの項目を削らなくてはならず、経済的にも精神的にも余裕のない一人暮らしになってしまうリスクがあるでしょう。
一人暮らしで物件を借りる場合、家賃以外にも共益費や駐車料金などが掛かる可能性があります。物件情報を確認したり不明点は不動産会社で質問したりして、トータルで手取りの3分の1に収まる物件を選ぶことが大切です。
3.外食を控えて食費を節約する
27歳の平均年収で無理なく一人暮らしを続けるには、外食を控えることも有効です。前の項で紹介したように、単身世帯の場合の食費は5万円ほどが目安。1日あたり1,600円ほどなので、外食を繰り返すとすぐにオーバーしてしまうでしょう。
27歳で年収アップを目指す7つの方法
ここでは、27歳の方が年収アップを図る方法を6つご紹介します。「自分の平均年収が思ったよりも低い…」とお悩みの方は、ぜひ下記の内容を参考にしてみてください。
年収アップを目指すには、戦略的に行動することが大切です。まず、自分の市場価値を把握しましょう。転職サイトや業界の情報を活用して、自分のスキルや経験がどの程度評価されるかを調べてみてください。市場価値が分かれば、現職での交渉や転職活動に活かせます。
次に、専門性を高めるスキルアップがおすすめです。資格取得や新しいスキルの習得は、競争力を高め、より高い年収を得られるポジションへの道を開きます。また、成果を数字や具体例で示せるようにすると、評価されやすくなるでしょう。
さらに、社内で昇進を目指す場合は、上司や同僚との関係性を良好に保ちながら、目標達成に貢献する姿勢をアピールすることも重要といえます。
年収アップには短期的な成果だけでなく、長期的なキャリアプランも大切です。自分の強みを活かしながら、着実に行動を積み重ねていきましょう。
1.昇進・昇給を図る
昇進して役職がつくと、基本給アップや役職手当の支給により年収が増える場合があります。昇給には「定期昇給」と「臨時昇給」の2つがあり、前者は年齢や勤続年数に応じて、後者は会社や個々の実績によって給与が増える仕組みです。27歳で新卒入社した会社を続けている場合は定期昇給が望めるほか、転職歴がある場合も成果や実績を挙げれば臨時昇給が期待できます。
ただし、昇給制度の有無や評価方法は会社によって異なるもの。27歳で年収アップを目指す場合は、勤務先の就業規則を確認したり上司に質問したりして、昇進・昇格する方法や具体的な昇給額を把握しておくのがおすすめです。
2.業務に役立つ資格を取得する
業務に関する資格を取得すれば「資格手当」の支給対象となる可能性があり、平均年収アップが期待できます。また、身につけたスキルによって成果を出せば、実績が認められて昇進・昇給に一歩近づける場合もあるでしょう。
3.副業を始める
昇進昇級が望めない、あるいは資格を取得しても収入アップが見込めないのであれば、副業で収入源を増やすのも選択肢の一つ。好きなことや得意なことを活かせる仕事や挑戦してみたかった分野の仕事を選べば、収入が増えるだけでなく自分の新たな可能性や適性を探れるでしょう。また、今の仕事に関連する副業を選べば、スキルアップや人脈を広げるメリットが期待できます。
しかし、解禁に向けた動きはあるものの、現段階では副業を禁止している会社も一定数あるようです。就業規則を読み込んだり上司に質問したりして、副業の可否や注意点をしっかり把握したうえで副業を始めるようにしましょう。
4.起業・フリーランスも視野に入れる
自分で起業をしたり、フリーランスとして働いたりすることも、年収アップを目指す方法の一つです。現代はインターネットの普及によって、起業やフリーランスのハードルが下がりつつあります。今の会社で学んだことを活かしたり、Webデザインやプログラミングなどの知識やスキルを身につけたりして独立することも可能でしょう。
しかし、独立後は営業や顧客対応、事務作業などすべて自分で行う必要があります。また、事業が軌道に乗るまでは仕事が少なく、収入が安定しない恐れも。まずは副業として仕事を始め、見通しが立ってから現職を退職するのがおすすめです。
5.資産運用を始めてみる
年収アップではなく貯蓄や長期的な資産形成で手元のお金を増やす方法として、20代のうちから預貯金や株式投資、投資信託などの資産運用を始めてみる選択肢もあります。少額であっても長い時間をかけて資産形成ができるため、若いうちから始めるメリットは大きいといえるでしょう。
つみたてNISAやiDeCoなどの制度を使えば、投資をしながら貯蓄できるだけでなく所得控除の対象にもなるため、お得に資産運用が可能です。ただし、投資である以上損失が生じるリスクがあるほか、iDeCoの場合は60歳になるまで引き出せない点がデメリットといえます。
「貯金額の平均はどのくらい?おすすめの貯金方法を紹介」のコラムでは貯蓄方法について紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
6.フリーターから正社員就職をする
現在フリーターの場合は、正社員就職をすることで年収アップを実現することが可能です。このコラムの「27歳の平均年収を決める主な6つの要因」で述べたように、雇用形態は年収を決めるうえで大切な要素の一つ。アルバイトよりも、毎月安定した給与を得られる正社員になったほうが収入アップを実現しやすいでしょう。
7.好条件の会社へ転職する
「今の職場では昇進・昇給の見込みがない」「会社の給与制度に不満がある」という場合、そのまま仕事を続けていても年収アップを目指すのは難しい可能性があります。そのようなときは、より自分の希望に合う条件の企業へ転職を検討するのも手です。
ただし、十分な企業研究を行わないまま給与面の不満だけで退職を決めてしまうと、入職後「仕事内容が自分に向いていない」「社風が合わず毎日通うのがつらい…」といったミスマッチにつながる恐れも。転職を成功させて年収アップやキャリアビジョンの実現を叶えるには、自分のスキルやなりたい姿を明確にしておくことが大切です。
次の項でキャリアを見つめ直す方法を紹介しているので、ぜひ読み進めてみてください。
キャリアを見つめ直して27歳からの年収アップを目指そう
年収アップを目指すなら、キャリアを見つめ直して自分らしく働ける仕事を選ぶことが重要です。いくら年収の高い仕事でも、自分のスキルや将来像とずれた職業だと、モチベーションを保って仕事をするのが難しく感じてしまうでしょう。
この項では、自分に合ったキャリアを見つけて年収アップを目指すための方法を紹介します。
自分のスキルや経験の市場価値を知る
キャリアを見つめ直すときは、まずは自分のスキルや経験の市場価値を知ることから始めましょう。27歳は中堅社員と位置づけられ、得意なスキルや分野を定めて伸ばしていく段階ともいえます。自分のスキルや経験を活かせる転職先を選ぶために、市場価値を客観視することは重要です。
具体的には「営業職で××業界の知識とコミュニケーション能力を身につけた」「事務職でPCのスキルや処理能力を習得した」など仕事で身についたものを言語化し、転職サイトで求人情報を調べてみるのがおすすめ。自分のスキルで挑戦できる仕事や年収、待遇などを知ることで、「どのようなキャリアアップが望めるか」「スキルを評価してくれそうな業界・職種はあるか」などを調べられます。
「自分の強みの見つけ方!面接時の例文やアピールできる書き方を紹介」のコラムでは自分の強みの見つけ方を解説しているので、参考にしてみてください。
将来なりたい人物像を思い描く
キャリアアップして年収アップを実現するには、自分が将来どうありたいかを詳細に思い描く必要があります。「今の職種で専門性を高めたい」「マネジメントに携わりたい」など将来の目標や理想が明確になれば、目標達成に必要な努力やキャリアアップの方向性が明らかになるでしょう。
転職エージェントに相談すれば効率的に仕事探しができる!
「今の収入が平均年収より低くてつらい」「27歳のタイミングでキャリアを見つめ直したい」という場合、転職が有効な手段といえます。ただし、初めての転職活動だと勝手が分からず、自分に合った仕事を見つけられるか不安に感じてしまう方もいるでしょう。
そのような場合は、転職エージェントに相談するのがおすすめです。
転職エージェントとは、民間企業が運営する就職支援機関のこと。転職活動に詳しいキャリアアドバイザーのサポートを受けられるため、一人での転職活動が不安な場合も安心です。エージェントには「若年層向け」「××職向け」など特定の年齢層や業界・職種に特化しているサービスもあるので、自分の状況に合ったものを選べばより効率的に転職活動を進められるでしょう。
27歳での転職を決意した方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、20代を中心とした若年層に特化した支援を行っています。
専任のキャリアアドバイザーが希望や適性を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合った求人情報を厳選してご紹介。業界や職種を問わず、若手人材や未経験者を積極的に採用している企業の求人を中心に扱っているので、初めての転職活動や未経験の業界・職種への転職を考えている方も、安心して仕事を探せるでしょう。
また、紹介した求人に合わせた応募書類の書き方や、面接でのアピール方法などもアドバイスします。サービスはすべて無料のため、まずはお気軽にご相談ください。
こんなときどうする?27歳の平均年収に関するQ&A
ここでは、収入が気になる27歳の方の疑問や悩みをQ&A形式で解消します。
平均年収は、業界や企業規模によって異なります。たとえば業界では、電気・ガス・水道業界やIT業界などの生活に欠かせない業界や、金融業・保険業や不動産業など専門性の高い業界は平均年収が高い傾向があるようです。
詳しくは、このコラムの「27歳の業種別平均年収」で解説しています。
地方より東京をはじめとする都市部のほうが年収が高いのは本当?
27歳で平均年収より稼げる可能性のある職種はありますか?
「専門的な資格やスキルが必要な仕事」「歩合制で努力次第で稼げる仕事」などの仕事は、27歳の平均年収である390万円より稼げる可能性があります。未経験から挑戦できる仕事の具体例としては、建設・土木作業員やIT系の技術職、営業職などが挙げられるでしょう。
「稼げる仕事ランキング!男女別に給与の高い職種や就職のポイントを紹介」では、未経験から稼げる可能性のある仕事を紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。
28歳の平均年収は、27歳の平均年収である約390万円と大きな違いはないと考えられます。ただし、1歳年を重ねているぶん経験やスキル、勤続年数が評価されて昇給やボーナスアップを叶えられる可能性もあるでしょう。28歳の平均年収については、「28歳の平均年収はどれくらい?中央値・手取りの目安や条件別データも紹介」のコラムで詳しく解説しています。
20代後半で転職活動を考えている方は、若年層向け就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。