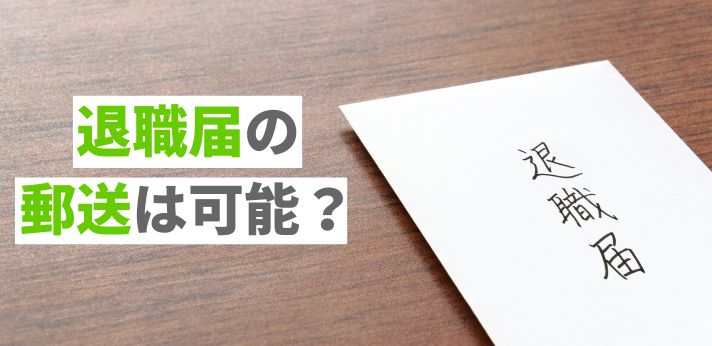退職時期のおすすめはいつ?ボーナスや求人事情を考慮したタイミングを解説
更新日
公開日
「退職時期のおすすめはいつ?」「どのタイミングで伝えるのがベスト?」と悩んでいる方もいるでしょう。円満に退職するためには、手続きや引き継ぎに必要な時間を考慮して早めに伝えることが大切です。このコラムでは、求人事情や税金の支払い、ボーナスの時期を踏まえ、退職におすすめの時期を詳しく解説。退職時期の伝え方も例文を交えて紹介します。自分にとって適した退職時期を見極めて、円満退社を目指しましょう。
退職理由の伝え方については「
」でも解説しています。ぜひ参考にしてください。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
おすすめの退職時期は、求人の多い時期やボーナスを受給したあとのタイミング
退職時期はいつがおすすめ?
退職にふさわしいタイミングは、人や企業、業界、職種などによって異なるため、退職するなら何月が良いとは一概に言えません。ただし、ボーナスの支給後や、年末、年度末といった区切りの良いタイミングを選んで退職する人が多い傾向です。一般的におすすめといわれる4つの退職時期を紹介します。
1.求人が多い時期
転職先を決めてから退職したい場合は、求人が多い時期に合わせて12月末を選ぶのがおすすめです。一般的に区切りをつけやすい年末や年度末に辞める人が多いので、10月から3月ごろに求人が増える傾向があります。転職活動には2〜3ヶ月の期間を要するため、10月前後に動き始める場合は、12月ごろが退職に適したタイミングといえるでしょう。
10月の求人数が増えるころを狙って9月中に転職活動を始め、11〜12月前半に内定を獲得できれば、12月末に退職が叶います。スケジュールに余裕を持って進めたい場合は、3月末の退職を目指すのも一つの手です。
2.年度末
区切りの良い年度末に合わせて、3月末に退職する人も多くいます。年度末に退職すると社会保険料や住民税の計算がしやすいので、手続きがスムーズです。3月末での退職を希望する場合は、企業の就業規則を確認したうえで、年末か1月中には直属の上司に退職の旨を伝えましょう。
ただし、3月は入退職者の手続きが多く、人事が忙しくなりやすい時期です。3月末での退職を目指す場合は、転職先の選考がスムーズに進みにくいデメリットがあります。転職活動や退職の準備は、早めに取り掛かると良いでしょう。
3.ボーナス受給のあと
ボーナスが支給されるタイミングに合わせて退職時期を決めるケースも少なくありません。ボーナスのタイミングは企業によって異なりますが、夏(6月下旬〜7月中旬)と冬(12月上旬)が一般的です。夏のボーナスのあとなら8月末や9月末、冬のボーナスのあとなら1月末あたりが目安になります。
退職後に転職を希望するなら、夏よりも求人が多い冬の方がおすすめです。ボーナス支給直後のタイミングで退職すると印象が悪くなる恐れがあるので、最低でも1〜2週間は期間を空けるのが望ましいでしょう。
4.閑散期
円満退職を望むなら、業務が落ち着いている閑散期に退職時期を調整するのが賢明です。閑散期は通常業務も落ち着いているので、選考や引き継ぎをスムーズに進められるでしょう。退職を引き止められるリスクを減らしつつ、企業への業務上の負担も最小限に抑えられます。閑散期は所属する企業や部署によって異なるので、これまでの経験を振り返ってタイミングを伺いましょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
退職時期を決める前に押さえておきたい4つの注意点
退職時期の目安が分かったら「△△のタイミングで退職しよう」と考える人もいるでしょう。しかし、退職時期を決める前に知っておくべき注意点があります。ポイントをしっかり把握して退職の時期を検討することが重要です。
1.退職時に転職先が未定だと空白期間が生じる
転職を前提に辞めるなら、翌日から転職先で働けるタイミングで退職するのが理想的です。転職先が決まっていない状態で退職日を迎えると、辞めた次の日から空白期間となります。空白期間が長くなれば、転職活動時に企業側から「この期間は何をしていたのか」「働く意欲はあるのか」と思われかねません。
空白期間は社会保険の資格が喪失するため、国民健康保険や国民年金への切り替えが必要です。退職の翌日に新しい企業へ入社できれば、社会保険への加入が継続されるため、国民年金などに切り替える必要はありません。社会保険の引き継ぎなども転職先が行ってくれるので、手間が掛からないこともメリットです。
2.退職時期によって税金の支払方法が異なる
退職時期によって住民税の支払方法が異なります。たとえば、1〜5月に退職する場合、退職月の給与もしくは退職金から1〜5月分の住民税をまとめて支払わなければなりません。
一方、6〜12月に退職する場合、いくつかの方法から選択できます。退職月分のみ給与から天引きして翌月以降は自身で納付する方法、あるいは退職月から翌年5月分までを退職月に天引きで一括徴収する方法です。退職後すぐに転職する場合、退職月分のみ天引きされ、翌月以降は新しい勤務先で徴収されます。支払い方法の違いも考慮して、退職の時期を検討しましょう。
3.退職時期によっては確定申告が必要になる
退職するタイミングによっては、自分で確定申告を行わなければなりません。通常、会社は1月から12月までの給与所得をもとに年末調整を行い、税金の計算を代行します。しかし、年の途中で退職し、再就職せずに年末を迎えた場合、年末調整が行われないので確定申告が必要です。
一方、12月末に退職した場合、前職の会社が年末調整を行うため、基本的に確定申告は不要です。年の途中で退職し、年内に再就職した場合も、転職先で年末調整が行われることが多いでしょう。ただし、10月〜12月に再就職した場合、手続きが遅れる場合があります。12月分の給与を受け取る前に退職した場合も、年末調整の対象外となるケースがあるので注意が必要です。
4.退職日によってはボーナス受給が難しい場合がある
退職時期を検討するときは、ボーナスの査定期間と支給条件を確認しましょう。退職日のタイミングによっては、ボーナス支給の対象外になる場合もあります。ボーナスの支給対象は、支給日に在籍していることが一般的な条件です。しかし、なかには「支給日の数日〜数週間後に在籍がある」と定めている企業もあります。
辞めるタイミングによっては、退職を理由にして査定を下げられ、ボーナスの不支給もしくは減額される可能性もゼロではありません。ボーナスを満額で受給したい場合は、就業規則を確認したうえで退職時期を決めることが重要です。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
会社に退職時期を伝えるときの3つのポイント
退職時期を伝えるときのポイントを解説します。想定可能な事態に備えつつ、現職でのトラブルを回避して円満退社を目指しましょう。
1.退職希望日の1~2ヶ月前に申告する
退職時期が決まったら、退職予定日の1〜2ヶ月前には直属の上司へ退職の意思を伝えます。たとえば、3月末に退職を希望する場合は、1月末から2月中に伝えるのが望ましいでしょう。就業規則で退職の申し出について定めている場合は、内容に従って申告することが原則です。
2.退職の意思を伝えるときは繁忙期を避ける
退職の意思を上司に伝えるときは、繁忙期を避けるのがおすすめです。たとえば、年度末となる3月は繁忙期のため、上司に退職の相談をしたくても、忙しいことを理由に時間が取れない場合があります。繁忙期は企業によって異なるため、状況を見て判断することが重要です。上司の様子も伺いながら都合がつきやすいタイミングで相談しましょう。
3.引き止められたら退職意思の強さを示す
上司に退職の意思を伝えたときに引き止められたとしても、退職の意思が強いことを示しましょう。「今より良い待遇にするから残って欲しい」などと言われ、交渉された条件で揺らいだり、あいまいな反応をしたりすると引き止められる可能性があります。万が一引き止められたら、これまでの感謝の気持ちを言葉で伝えつつ、退職の意思は変わらないとはっきり伝えることが大切です。
退職時期を決めたあとの6つの流れ
退職時期を決めたら、必要な手続きを進めていきましょう。スムーズに退職するためには、上司や人事に任せきりにせず、自発的な行動をすることが大切です。
1.直属の上司に退職の意思を伝える
退職の意思が固まったら、直属の上司に直接伝えましょう。上司が忙しくないときを見計らって相談するのがポイントです。上司の手が空いているように見えても、その場ですぐに切り出すのは望ましくありません。「ご相談したいことがあるのですが、今△分ほどお時間あるでしょうか」「△日の△時から△分ほどお時間いただけますか」など、上司に確認を取ってから相談するのがマナーです。
退職の意思は、個室などの一対一で話せる場で伝えましょう。上司には「△月△日付けでの退職を希望している」と具体的な退職時期を示します。業務の引き継ぎや今の仕事内容も加味して、現実的な日程を出すようにしてください。
直属の上司以外へ先に退職の意志を伝えるのは避けよう
先に直属の上司に伝えず、さらに上の立場の上司や同僚に退職の意向を伝えるのは避けるべきです。社会人としてのマナー不足とみなされ、直属の上司の管理責任を問われたり、トラブルにつながったりする可能性もあります。退職の意思はまず直属の上司に伝え、その後の展開は上司の指示に従いましょう。直属の上司への伝え方は「
直属の上司とは?退職の意思を伝えるにはどうしたら良い?」も参考にしてください。
2.退職日を決めて退職届を提出する
直属の上司と相談のうえ、退職時期や具体的な日程が確定したら退職届を提出します。上司に退職の意志を伝えるタイミングでは、退職届は必要ありません。退職届の提出時期は、1ヶ月前や2ヶ月前など就業規則で決められている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
退職届には上司と相談して決めた退職日を西暦で記入し、文末には「退職いたします」と事実報告の形で記します。退職届を渡すときは、人目に気をつけたうえで直属の上司に手渡ししてください。退職届の書き方は「退職届は横書きでもいい?退職願や辞表との違いも解説」で詳細をまとめています。あわせて参考にしてください。
3.有休消化の計画を立てる
退職日が決まったら、有給休暇の残日数を確認して計画的に消化しましょう。有休の残日数によっては、最終出勤日まで日数がない場合もあるので、引き継ぎなどの予定にも影響します。退職時期が繁忙期と重なると変更を促される可能性もあるため、前もってスケジュールを立てておくことが重要です。なお、有給休暇は身体を休める目的で支給されているので、多忙を理由に買い取ることは基本的に認められません。
4.引き継ぎや残務整理をする
退職日が確定したら、担当業務の引き継ぎ準備を始めましょう。スケジュールを立てて行い、退職日の3日前までに引き継ぎを終えるのが理想です。業務の後任者に向けて、分かりやすい資料を作っておくと、効率よく引き継ぎができます。
資料には、業務の進行状況やクライアントの特徴、段取りなどの情報を入れておくのがおすすめです。引き継ぎを行いながら、退職までに自分が担当している残務も責任を持って終わらせましょう。引き継ぎが完了しないまま退職すると、誰も担当業務の状況を理解できず、後任者や取引先に迷惑を掛けてしまいます。引き継ぎを行う際は、後任者によるフローの確認や質疑応答の時間も含めて予定を立てるのがおすすめです。
5.会社への返却物と受領物を確認する
退職にあたり、会社から支給されている物品はすべて返却します。保険証や社員証、名刺、制服などは、すぐに返却できるように前もって準備しておきましょう。退職に合わせて会社から受け取るものは、離職票や雇用保険被保険者証、源泉徴収票です。会社が準備する書類は退職後に郵送される場合が多いので、受け取り時期や方法は、在職中に人事や担当者に確認しておくことをおすすめします。
6.お世話になった人へあいさつする
引き継ぎなどが済んだら、退職日までにお世話になった方々へあいさつをしましょう。お世話になった社内の人だけでなく、取引先や顧客など、社内外問わずにあいさつするのがマナーです。特に、退職後も同じ業界で働く場合は、以前の取引先や顧客と再び仕事をする可能性も考えられます。良好な関係を維持しておけば、将来的に仕事につながる可能性もあるでしょう。
退職前に取引先や顧客に直接会えるなら、これまでのお礼と退職する旨を伝えることが大事です。今後の業務がスムーズになるように後任者を連れてあいさつに伺いましょう。目上の方にあいさつをする場合は、必要に応じて上司に同行してもらいます。会うのが難しい方にはメールや電話であいさつをしてください。
退職時期を伝えるときの例文
上司に退職時期を伝えるときの例文を、辞める理由別に紹介します。退職の意思を固めたけれど、上司へどのように伝えて良いか分からないという方は、ぜひ参考にしてください。
スキルアップ・キャリアアップを目的に退職する場合
スキルやキャリアアップのために退職する場合は、前向きな理由として受け取られるでしょう。上司に伝えるときは「今の会社ではスキルアップが望めない」「理想のキャリアアップができない」などの愚痴や不満を理由に含めず、ポジティブに伝えることが重要です。
「業務で△△に関わる機会があり、自分も△△に挑戦してみたいと考えるようになりました。今後は△△としてキャリアを形成していきたいと考え退職を決意いたしました」
家庭の事情を理由に退職する場合
結婚や育児、介護など、家庭の事情で退職する場合、深く理由を追及されることは少ないでしょう。特に「地元に帰る」「家族の転勤で引っ越す」のように、物理的に遠方となる場合は、納得してもらいやすいといえます。
「このたび結婚を機に引っ越すことになりました。引っ越し先が遠方となるため、通勤することが難しく、退職したいと考えております」
退職時期や転職活動にお悩みの方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、キャリアアドバイザーがマンツーマンで応募書類の添削や面接対策を行い、退職・転職に関する不安を抱いている方をサポートします。
非公開求人や優良企業の求人も取り扱っており、一人ひとりに合った求人をご紹介。面接日の調整や応募先企業との連絡は担当のキャリアアドバイザーが代行しているため、お仕事をしながらの転職活動でも安心です。所要時間1分程度でできる適職診断も用意しています。サービスの利用や登録は無料なので、円満退職を叶え希望の転職先を見つけたい方は、ハタラクティブにお任せください。
退職時期に関してよくある質問
退職時期に関するお悩みや疑問にQ&A形式で回答します。
退職の意思を伝えるタイミングが早すぎるとどうなる?
あまりにも早いタイミングで退職の意思を伝えてしまうと、引き止めの期間が長引く可能性もあります。場合によっては、周囲から「あの人は退職するから」と扱われ、職場の居心地が悪くなることもあるでしょう。就業規則に従いながら、早すぎず遅すぎずのタイミングで退職の意思を伝えるよう調整することをおすすめします。
退職の意志を早めに伝えたことによる影響が気になる方は「退職までの過ごし方を知りたい!円満に辞めるためにすべきことを解説」のコラムをご覧ください。退職までに起こり得る影響や、退職までの期間を上手に過ごすコツを紹介しています。
公務員は民間企業と異なり、退職時期の申し出について明確な規定はありません。ただし、一般的には、1〜3ヶ月前には申告することが推奨されています。円満に退職するためにも、引き継ぎや欠員補充を考慮して退職日を決めるのが良いでしょう。公務員で退職を考えている方は「公務員は失業保険をもらえる?退職後に受け取れるお金と手続きの方法を解説」のコラムもご参考ください。
就業規則に従い前もって伝えているなら、基本的には会社の要望に従う必要はありません。退職の時期の希望は、口頭で伝えるのではなく退職届を提出しましょう。退職届を提出すれば会社は拒否できないのがルールです。退職日まで業務に励み、円満に退職できるように努めましょう。
退職の交渉でお困りの方は「仕事を辞めさせてくれないのは違法?対処法や相談先を紹介」を参考にしてみてください。
会社を辞めて無職になるなら退職日はいつが得ですか?
退職して無職になる場合、12月末がおすすめです。12月末に退職すると会社で年末調整が行われるので、確定申告の手間がかかりません。翌年5月分までの住民税を12月分の給与や退職金から一括で天引きしてもらえば、普通徴収の開始が遅くなるため、短期間ではあるものの支払いの負担を抑えられるでしょう。
退職後の住民税についての詳細は「退職後の住民税はどうなる?納付方法や注意ポイントについて解説!」のコラムで確認してください。
10月に退職するデメリットは、年末調整が受けられず確定申告が必要になる可能性があることです。退職後すぐに転職しても、転職先での手続きが間に合わないケースも少なくありません。また、冬のボーナスの査定期間に含まれず、支給されない可能性もあります。
ボーナスの査定期間を考慮して退職日を決めたい方は「ボーナスの支給はいつ?時期や転職するときの注意点を解説」のコラムもチェックしておきましょう。
退職の意思を固め、理由を明確にしておくと上司に伝えやすいでしょう。繁忙期や上司が忙しいタイミングは避け、相談したいことがある旨を伝えて時間を確保してもらいます。ほかの人がいない環境で相談すれば、退職したい理由をしっかり聞いてもらえるはずです。退職の切り出し方にお悩みの方は「仕事を辞めると決めたらどうする?退職意思の伝え方や転職のステップを紹介」のコラムもご覧ください。
就活・転職エージェントのハタラクティブでは、専任のアドバイザーが退職時期や転職活動に悩んでいる方をサポートします。あなたの希望をヒアリングしながら、条件に適した求人のご提案が可能です。