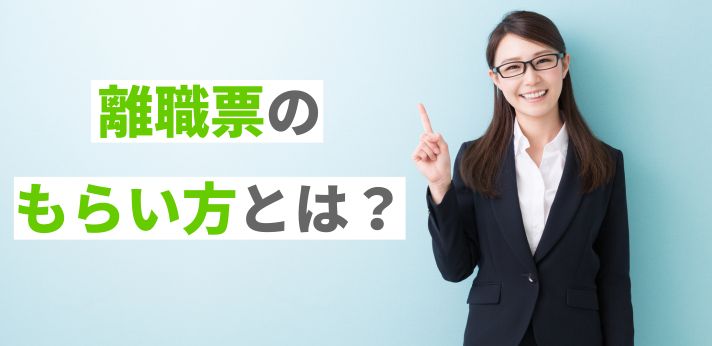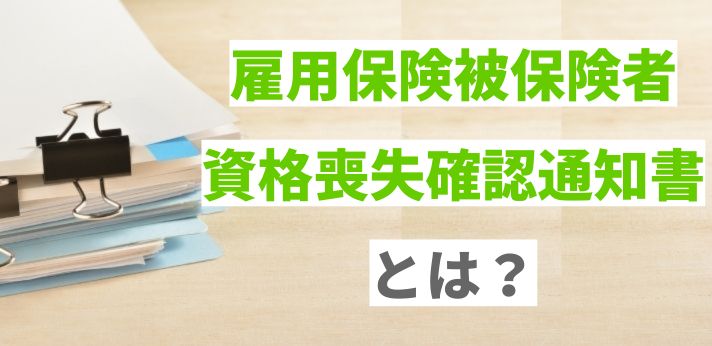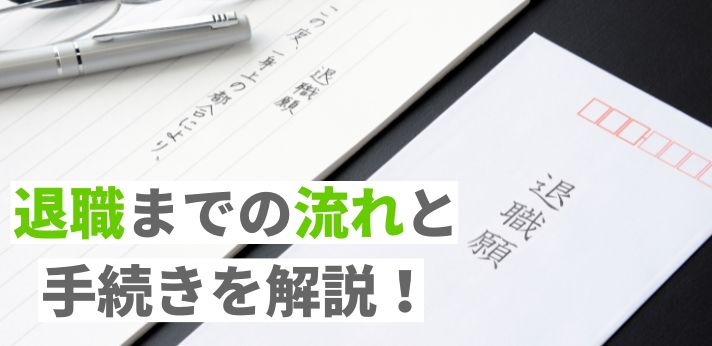仕事を辞めさせてくれないのは違法?対処法や相談先を紹介仕事を辞めさせてくれないのは違法?対処法や相談先を紹介
更新日
公開日
上司や会社が仕事を辞めさせてくれない場合、法律違反の可能性がある
上司や会社が仕事を辞めさせてくれない状況に悩んでいる方もいるでしょう。法律上は、正社員は辞める意思を伝えてから2週間が経過すれば退職でき、仕事を辞めさせてくれないのは違法にあたる可能性があります。
このコラムでは、違法な引き止めの事例や仕事を辞めさせてくれない場合の対処法、退職する際にやるべきことなどをまとめました。退職について困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
仕事を辞めさせてくれないのは法律違反にあたる
上司に退職願を提出したのに、仕事を辞めさせてくれない場合は法律違反にあたる可能性があります。そのため、上司や会社が退職を認めてくれないからといって、仕事を辞めることを断念する必要はありません。退職については民法上で定められているので、チェックしていきましょう。
労働者には辞める権利が認められている
では、雇用期間の定めがない場合は、労働者はいつでも雇用の解約を申し入れられると定められています。つまり、
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
雇用期間の定めがない正社員には退職の権利があり、会社が仕事を辞めさせてくれない場合は違法です。
引き止めやお願いだけなら違法にあたらない
退職を引き止める行為自体は違法ではありません。退職の意思を伝えた際、人手不足の会社では引き止められることがあるでしょう。「後任が決まったあとに退職してほしい」のような条件を提示されても、強要ではなくお願いの段階であれば違法とはいいきれないのです。
しかし、条件を承諾し退職を先延ばしにすると、そのままズルズルと働き続けてしまうこともあるので注意しましょう。退職の意思が固い場合はしっかりとその旨を伝え、後任決定の期限を設けるといった先を見越した行動をとるのがおすすめ。もちろん、引き止めを断って退職することも労働者の自由です。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
仕事を辞めるための法律上の条件
民法では、労働者が仕事を辞めるための条件について定められています。正社員のように雇用期間に定めがない場合とアルバイトやパート、契約社員など雇用期間に定めがある場合に分けて法律上の条件を確認しましょう。
辞める2週間前に意思を伝えれば退職できる
民法第627条によると、「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」とされています。よって、退職の意思を表示してもいきなり次の日から仕事を辞められるわけではありません。在職中に必要な手続きや現場の引き継ぎ作業もあるため、病気やケガなどやむを得ない事情がない限り、基本的には退職を申し出てから2週間は仕事を継続しなければならない点に注意しましょう。
就業規則と民法はどちらが優先される?
厚生労働省大阪労働局の「よくある質問」によると、就業規則が民法と異なる場合、基本的には就業規則が優先されるようです。たとえば、「退職希望日の2ヶ月前に申し出ること」と就業規則で定められている場合、2週間前ではなく2ヶ月前の申し出が必要でしょう。ただし、労働者の退職の自由が極度に制限される状況では、就業規則が無効になる可能性もあります。
就業規則を無視して退職しようとすると、上司や同僚との間でトラブルが発生する場合も。「パワハラに悩んでいる」「仕事がつらく心身に支障をきたしそう」といったやむを得ないケースを除き、就業規則に従って退職を申し出るのが無難でしょう。
参照元
厚生労働省大阪労働局
よくあるご質問(退職・解雇・雇止め) パートや契約社員などは雇用期間内の退職に注意
パートやアルバイト、契約社員のように雇用期間に定めがある場合、契約期間中は会社側が労働者を解雇できないと同時に、労働者側も退職できません。そのため、非正規雇用の方は雇用期間中、正社員の場合と同じように仕事を辞められるわけではない点に注意しましょう。
しかし、やむを得ない事情があるときは、非正規雇用の労働者も会社の同意を得ずに辞められます。民法の第628条が、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と規定しているためです。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
会社が仕事を辞めさせてくれない主な理由
退職したいのに会社が仕事を辞めさせてくれない場合、「離職率を気にしている」「人手不足」といった理由が考えられます。理由を知っておくことで対処法も変わるので、ぜひ参考にしてみてください。
離職率を上げたくない
離職率の高さが会社のイメージダウンにつながるのを避けるため、仕事を辞めさせてくれない場合があります。離職率が高いと求職者にネガティブなイメージをもたれやすく、採用活動に支障が出る可能性があるでしょう。そのため、在職中の社員が辞めるのを防ごうとして、退職の引き止めにつながるようです。
繁忙期で人が抜けると困る
繁忙期に人手を減らしたくないために、仕事を辞めさせてくれないことがあるようです。繁忙期に退職の意志を伝えることでトラブルにつながる恐れもあります。
円満退職するには繁忙期を避ける配慮が必要です。しかし、「今辞めると迷惑が掛かるかも...」と気にし過ぎるとタイミングを逸してしまいます。周囲に配慮しつつも、ズルズルと退職できない状況を避けるよう注意しましょう。
上司が評価を気にしている
会社によっては「部下の退職は上司の管理不足」と判断され、責任者の評価が下がる可能性もあります。そのため、評価を気にするあまり上司が仕事を辞めさせてくれないケースもあるでしょう。
採用の費用が限られている
採用や育成に掛かる費用が原因で、会社を辞めさせてくれないこともあるようです。「新しい人材を雇う余裕がない」「採用活動のためのコストが限られている」といった場合、在職中の方が退職の意志を表示しても引き止められる可能性があるでしょう。
仕事を辞めさせてくれない違法な事例と対処法
仕事を辞めさせてくれない状況は法律違反にあたるにもかかわらず、違法な引き止めにあっている方もいるようです。ここでは、仕事を辞めさせないために行われる違法な引き止めの事例と対処法をまとめました。
損害賠償を請求される
会社から「仕事を辞めるなら違約金を払え」「辞めたら損害賠償請求をする」などの支払いを強要された場合は、違法です。労働基準法の第16条には、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあります。
よって、違約金の請求をされても労働者に支払う義務はありません。ただし、重要な仕事の引き継ぎを一切行わずに退職し、それによって会社に損失が出た場合は損害賠償を請求されてしまうこともあるようです。トラブルにならないためにも退職のタイミングには注意しましょう。
また、退職後に給与や退職金が支払われないケースは違法といえます。労働基準法第24条で定められているとおり、給与の支払いは会社の義務です。退職金の規定を定めている会社であれば、退職金を支払う義務も会社にあります。
したがって、給与や退職金が満額支払われないのは違法といえるでしょう。「給与や退職金が満額支払われなかった」「給与から不当な損害賠償が引かれていた」というケースでは退職後も請求できます。
懲戒解雇扱いにしようとする
労働契約法第15条で定められているとおり、懲戒解雇とは客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合にされる解雇処分のこと。「犯罪行為をした」「経歴を詐称していた」「2週間以上会社を無断欠勤したうえ、出勤要請に応じない」などの正当な理由もなく、会社が労働者を懲戒解雇することは違法です。
懲戒解雇されると、退職金を受け取れないことがあります。また、離職票に懲戒解雇を受けたことが記載され、転職の際に不利に働く可能性もあるので注意しましょう。
なお、退職の意思を示したことが原因で会社から懲戒解雇を受けた場合、それを無効にできるほか、会社に対して損害賠償を請求できる場合があります。対処する際は法律上の知識が必要になるため、労働基準監督署(労基)や専門家に相談するのがおすすめです。
有給休暇を取得させてもらえない
労働者に有給休暇を与えることは会社の義務。退職が決まっている労働者も規定の日数の有給休暇を取得できます。
しかし、まとめて有給休暇をとり長期間仕事を休むと、業務に支障が出る可能性も。「繁忙期を避ける」「引き継ぎ業務に掛かる工数を確保する」など、計画的に休めるよう注意しましょう。
退職届を受理してもらえない
退職届を受理してもらえない場合は違法と考えられます。前述したように、労働者には仕事を辞める権利があるためです。「うちの会社には君が必要だ」といったように引き止められて退職届を受け取ってもらえない場合は、法律違反の可能性があるでしょう。
なお、退職届を受け取ってもらえないからといって、口頭での報告のみで済ませるのは避けたほうが無難です。あとから上司に「退職の話を聞いていない」と言われてしまい、トラブルになる恐れがあるため、書類で意思を表すことをおすすめします。
離職票の交付を拒まれる
離職票は、勤めていた会社を退職する際に発行される書類です。雇用保険法第76条3項では、「離職した者から求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の請求があった場合、会社は交付しなければならない」とされています。離職票がないと求職者給付(失業保険)を受け取れないため、正当な理由なく交付を拒まれるケースは違法です。
退職届を出しても長期間仕事を辞めさせてくれない
前述のように、民法に従うと退職を申し入れたあと2週間が経てば、会社の承諾なく仕事を辞められます。しかし、退職届を出しても長期間仕事を辞めさせてくれないこともあるようです。退職届の提出後、長期間辞めさせてくれない場合は違法にあたるため、「退職は人事に直接相談して良い?上司との交渉ポイントと手順も解説!」を参考に、退職交渉を進めましょう。
仕事を辞めさせてくれないときの6つの対処法
仕事を辞めさせてくれないからといって、そのまま働き続ける必要はありません。以下に紹介する対処法を参考に、スムーズに退職できる方法を考えてみましょう。
仕事を辞めさせてくれないときの対処法
- 直属の上司に退職の意思を伝える
- 退職願ではなく退職届を提出する
- 内容証明郵便で退職届を提出した証拠を残す
- 労働基準監督署(労基)に相談する
- 弁護士に退職代行の相談をする
- 退職代行サービスを利用する
1.直属の上司に退職の意思を伝える
まずは退職の意思を上司へ口頭ではっきり伝えることが大切です。「そろそろ辞めたいです」のようにあいまいな言葉で伝えると、愚痴や相談と勘違いされる可能性があるので注意しましょう。やりとりを録音しておくと、トラブルになった場合の証拠として使えます。
上司に納得してもらえない場合は、引き止められにくい理由を伝えるのも一つの手。たとえば、「育児や介護のため」「体調不良のため」「会社ではできないことに挑戦するため」などの理由を挙げると、強引な引き止めにあいにくいようです。
認められない場合は、さらに上の上司や人事部に伝える
直属の上司に退職の意志を伝えても聞き入れてもらえない場合は、さらに上の上司や人事部に伝えてみましょう。別の上司や人事担当者に相談することで、退職を認めてもらえる可能性があります。
また、ハラスメントのように上司が原因で退職したい場合も、さらに上の上司や人事部に伝えると問題解決につながることがあるでしょう。
2.退職願ではなく退職届を提出する
仕事を辞めさせてくれない場合は、「退職願」ではなく「退職届」を提出し、退職の強い意思を伝えましょう。「退職願」が退職の意思を表す一方、「退職届」は会社に対して労働者が退職を通告する書類なので、強い意思を表明できます。
退職の意思はメールで伝えるべき?
退職の意思表示に決められたルールはないので、メールでの申し出も法的には有効だと考えられます。「引き止められたときに断りきれない」「直接話すのは怖い」といった場合も、メールであれば安心して自分の意思を伝えられるでしょう。
しかし、メールのみでは未読のまま気付かれない可能性も考えられるので、意思表示したあとは直接話をするか電話で伝えることをおすすめします。退職の意思が確実に伝わる方法を選択すると、後々のトラブルも避けやすくなるでしょう。
3.内容証明郵便で退職届を提出した証拠を残す
退職届を提出しても受理してもらえず仕事を辞めさせてくれない場合は、内容証明郵便として会社に送付するという選択肢もあります。内容証明郵便とは、「いつ」「誰から誰へ」「どのような内容を送ったか」を日本郵便が証明する制度です。
内容証明郵便を送付する際は、謄本を差出人と郵便局で保管することになり、それが退職届を提出した証明になります。内容証明郵便で退職届を送られた会社は、「受け取っていない」と主張できません。
4.労働基準監督署(労基)に相談する
労働基準監督署は、労働条件や解雇といった労働問題を相談できる厚生労働省の出先機関です。「労基」「労基署」とも呼ばれる労働基準監督署は、会社が労働基準法や最低賃金法などの法律を守っているか監督する役割があります。労働基準監督署への相談は無料。対面のほか電話でも対応してもらえます。
相談後は、労働基準監督署が会社へ勧告するほか、場合によっては調査のために会社を訪問することも。会社が仕事を辞めさせてくれないときは早めに相談し、状況の改善を図りましょう。
5.弁護士に退職の相談をする
会社が仕事を辞めさせてくれない場合は、弁護士への相談も検討してみましょう。弁護士に依頼すると、以下のようなことを担当してもらえます。
- ・退職日の調整
- ・有給休暇の取得の交渉
- ・未払い賃金や残業代の支払い交渉
- ・損害賠償請求への対応
6.退職代行サービスを利用する
仕事を辞めさせてくれない場合、退職代行サービスを利用するのも一つの手です。退職代行サービスとは、費用を支払うことで会社へ退職連絡をしてもらえるサービス。退職手続き以外にも、有給休暇の取得や未払いの賃金・残業代の請求も代行してもらえます。
「会社を辞めさせてくれないから休む」のはあり?
仕事を辞めさせてくれないからといって、会社を休むのは避けたほうが無難です。「民法627条1項」のとおり、会社側には従業員の退職を拒否する権利はありません。
しかし、無理やり辞めようと会社を休んでしまうと「無断欠勤」となり、懲戒解雇や損害賠償請求をされる恐れがあります。懲戒解雇になると再就職時に影響が出る可能性があるため、正当な段階を踏んで退職手続きを進めましょう。
「ストレスで会社に行くのがつらい」「体調不良で欠勤が続いており、このまま会社を辞めたい」といった場合、
民法628条の「やむを得ない事由による雇用の解除」に該当し、すぐに退職できることもあります。
ただし、その際も医療機関から診断書をもらったり、メールや電話などで退職の意思を伝えたりと、就業規則に沿った手続きを行いましょう。
参照元
e-Gov 法令検索
民法 仕事を辞めさせてくれない状況を防ぐ4つの方法
仕事を円満に辞めたい場合は、在職中から就業規則に沿って対応したり、前もって退職の意思を表示したりしましょう。以下では、仕事を辞めさせてくれない状況を防ぐためにできる方法をまとめました。
1.就業規則に沿った対応を心掛ける
退職を希望している場合は、まず就業規則を確認しましょう。退職の際に必要な手続きや退職の意思を伝えるタイミングなどが記載されていることがあります。退職時のトラブルを避けるためには、なるべく就業規則に合わせた対応をするのがおすすめです。
2.仕事を辞める1~2ヶ月前に意思表示する
法律では雇用期間に定めがない場合、2週間前に退職の意思を表示すると仕事を辞められます。しかし、なるべく退職希望日の2~3ヶ月前、遅くとも1ヶ月前には辞めることを伝えるのが望ましいでしょう。
3.繁忙期を避けて退職や引き継ぎを行う
退職や仕事の引き継ぎの時期が繁忙期と重ならないように、仕事を辞める計画を立てるのも重要です。特に人手不足の場合、退職のタイミングと繁忙期が重なると会社が仕事を辞めさせてくれない可能性があるでしょう。退職が原因で周りの人に迷惑を掛けないためにも、繁忙期を避けるのが理想です。
4.転職先を決めてから退職の意思を伝える
会社が仕事を辞めさせてくれない場合、「もう転職先が決定している」と伝えると退職を認めてくれることがあるようです。「ほかにやりたいことがある」といった前向きな理由で転職を決めていれば、応援してもらえる可能性もあるでしょう。
転職する場合、空白期間がないと採用で有利になると考えられているので、なるべく在職中から次の職場を探すことをおすすめします。
仕事を辞める前にやるのが望ましいこと
仕事を辞める意思を伝えて了承を得たあとにも、円満退職につながる行動がいくつかあります。以下に紹介する事柄を、退職時に終えられるよう心掛けましょう。
仕事を辞める前にやるのが望ましいこと
- 後任者への引き継ぎ
- 取引先への挨拶
- 返却物や受け取る書類のチェックリスト作成
- 社会保険や税金の手続きの確認
- 雇用保険(失業保険)の申請方法の確認
1.後任者への引き継ぎ
仕事を辞めることが決まったら、在職中に業務の引き継ぎをしっかりと行っておきましょう。引き継ぎをきちんと済ませておかないと退職後に上司や同僚を混乱させ、迷惑を掛ける可能性があります。
退職時に引き継ぐ内容を漏れなく伝えられるよう、スケジュールを立てて進めましょう。引き継ぎの時間が足りなかったときに備えて、マニュアルや資料を整理したり新しく作成したりするのもおすすめです。円滑な引き継ぎを実現させるためには「辞めた会社から電話がくる理由とは?円満退職のポイントも紹介!」もご確認ください。
愚痴や不満は言わないようにしよう
退職が決まったあと、理由を聞かれても仕事や待遇、人間関係などの愚痴や不満を言うのは控えましょう。ネガティブな発言をすると、働いている人のモチベーションを下げてしまう恐れがあります。
また、愚痴や不満が原因で人間関係がこじれたり、職場で信用を失ったりする可能性も。引き継ぎや退職の手続きで協力をお願いしにくくなることもあるので、ネガティブな発言は控えましょう。
2.取引先への挨拶
取引先にお世話になっている方がいれば、挨拶を忘れずに行いましょう。挨拶なしに担当者が変わると、取引先が対応に困ってしまう場合があります。
取引先のお世話になった方と転職後に関わりをもつ可能性もあるので、誠実な姿勢を見せるよう心掛けてみてください。
3.返却物や受け取る書類のチェックリスト作成
会社から借りた備品は忘れず返す必要があります。仕事を辞める際は備品の返却や書類の受け取りに漏れがないよう、以下のようにチェックリストを作っておくと安心です。
- ・身分証明書
- ・名刺
- ・制服
- ・健康保険被保険者証
- ・その他、会社から支給された備品
- ・雇用保険被保険者証
- ・源泉徴収票
- ・離職票(転職先が決まっていない場合)
- ・年金手帳(会社が保管している場合)
源泉徴収票や離職票は、自分から発行を求めない限り会社側が送ってくれないこともあります。これらの書類は基本手当(失業手当)の受給や確定申告などで必要になるので、会社から送られてこない場合は確認の連絡をとりましょう。
なお、退職時には会社の情報を持ち出さないように注意が必要です。契約内容・売上情報・顧客情報・各媒体のパスワードなどの情報を外部に漏らすと、会社から訴えられる可能性もあります。
4.社会保険や税金の手続きの確認
会社を辞めると、健康保険と厚生年金の資格を失います。そのため、退職後は必要な手続きをとり自分で社会保険料を納めなければなりません。手続きを行わなければ、健康保険に加入できないため医療費が高額になったり、年金をきちんと納められず将来の年金受給額が減ってしまったりといった問題が発生します。
5.雇用保険(失業保険)の申請方法の確認
雇用保険(失業保険)に加入している方は、仕事を辞めたあとで基本手当(失業手当)を受け取れる可能性があります。基本手当(失業手当)とは、失業中の方が生活の心配をせず求職活動できることを目的にした給付金のことです。手続きはハローワークで行い、受給するには規定の条件を満たす必要があります。
パワハラにあっていたら証拠集めをしておくのも重要
職場でパワハラにあっていた場合、退職理由が会社都合退職となるよう証拠を集めておくことが大切です。会社都合退職とは、自身の都合ではなく会社によって退職を余儀なくされたことによる退職のこと。会社都合による退職であれば、失業手当の受給期間が延びたり、失業手当を申請してから受給できるまでの待期期間が短縮されたりすることがあります。
仕事を辞めたい理由がパワハラの場合、現場をICレコーダーで録音したり記録を文書にまとめたりして、証拠を集めておきましょう。どのような行動がパワハラにあたるのか知りたい方は、「
パワハラの定義とは?3つの要素や対処法について解説!」を参考にしてみてください。
会社を辞めたあとのプランを考えよう
退職後はどのような行動に出るべきか、プランをきちんと考えておくことが大切です。たとえば、「△△の職種に転職する」「△△の業界で仕事を探す」といったプランが考えられます。
なお、辞められないからといって、退職を強行するのは避けましょう。理想のキャリアプランを築くためにも、できる限り円満退職を目指すのが重要です。
「仕事を辞めさせてくれない」「退職に必要な手続きが分からない」などとお悩みの方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、若年層を対象にした就職・転職エージェントです。退職の相談から転職の求人紹介や面接対策まで、専任のキャリアアドバイザーが丁寧にサポートします。職場の雰囲気もお知らせするので、働きやすい会社に転職したい方にもおすすめです。
面接日程の調整や条件交渉といった応募先とのやりとりもすべて代行するため、在職中で忙しい方も安心して転職活動に集中できます。サービスのご利用はすべて無料なので、ぜひ一度ご相談ください。
仕事を辞めさせてくれないときのお悩みに関するQ&A
ここでは、仕事を辞めさせてくれない状況に関連するお悩みで、特に疑問を感じやすいことを紹介します。ぜひご覧ください。
急に仕事を辞めると会社から連絡が来ます。連絡を無視すれば上司が自宅に来たり、緊急連絡先に電話されたりすることもあるでしょう。2週間以上の無断欠勤が続くと会社は労働者を解雇できるため、最悪の場合は懲戒処分となる可能性もあります。
詳しくは「会社をバックレるとどうなる?損害賠償は請求される?転職への影響とは」を参考にしてみてください。退職させてくれないからといって仕事や会社から逃げてしまう前に、労働基準監督署(労基)や弁護士に相談しましょう。
人手不足で周囲に迷惑を掛けたくないと思う気持ちは分かりますが、辞めたい気持ちを我慢し続けると、仕事のパフォーマンスが落ちるだけではなく心身に影響を及ぼす可能性もあります。「繁忙期を避ける」「メールで伝える」など、工夫しながら早めに退職の意思を伝えましょう。
無理やり退職するのではなく、直属の上司に伝えてからが望ましいでしょう。それでもうまくいかない場合は、人事部に相談してみてください。就業規則に沿って退職できるように、相談にのってくれます。
「会社の辞め方や手順を解説!退職理由の伝え方で注意したいことも紹介」のコラムでは退職の手順を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
円満退職を目指す場合は、メールではなく直接伝えるのがおすすめです。「恫喝されて怖い」「以前退職の意思を伝えたが話が進まない」などの理由がある場合は、人事部や労働基準監督署(労基)へ相談してみましょう。
退職して転職を検討している方は、ハタラクティブにお気軽にご相談ください。