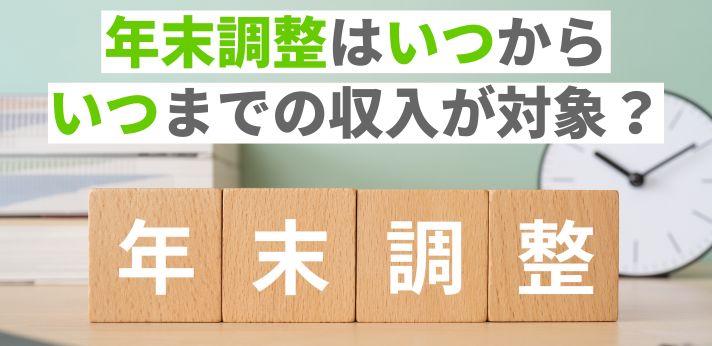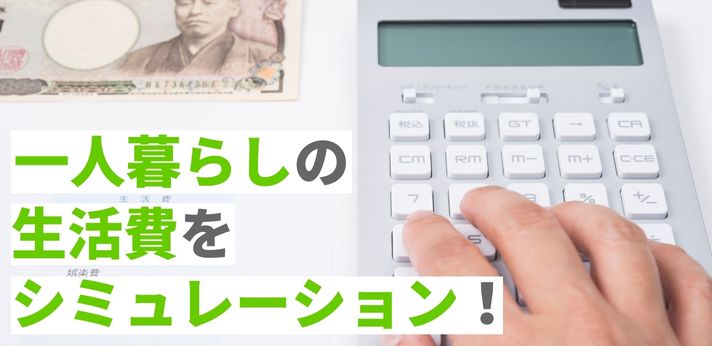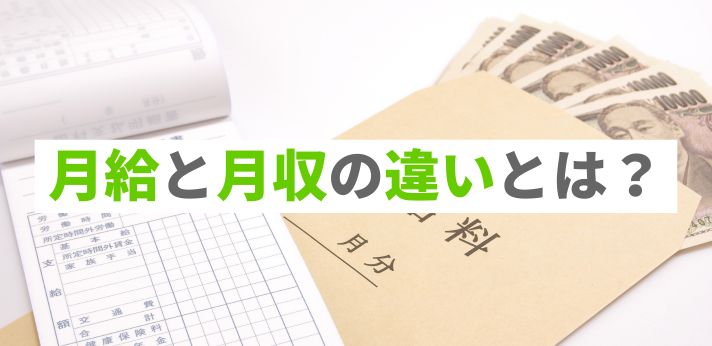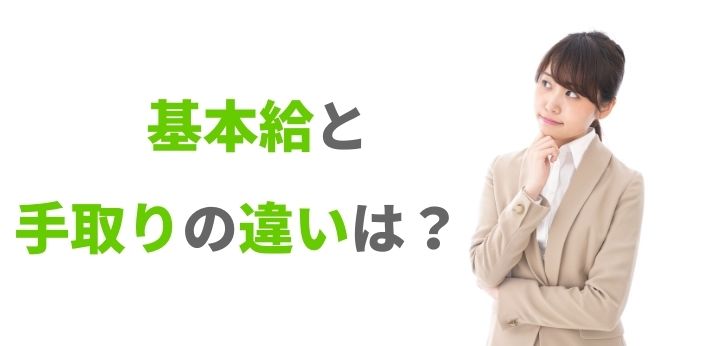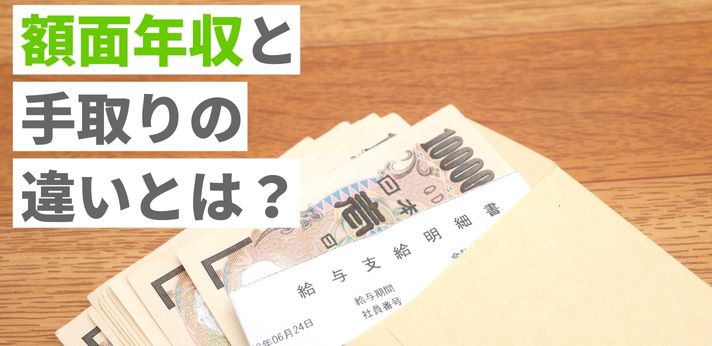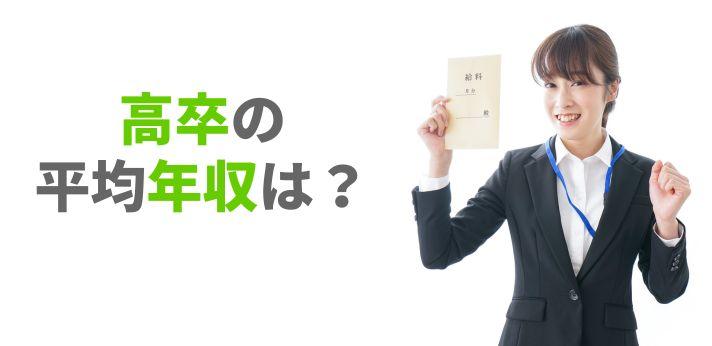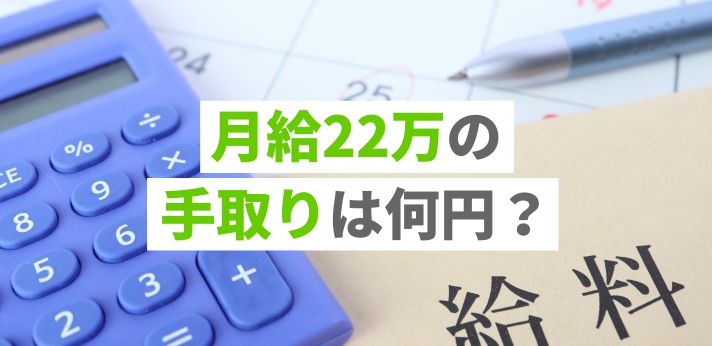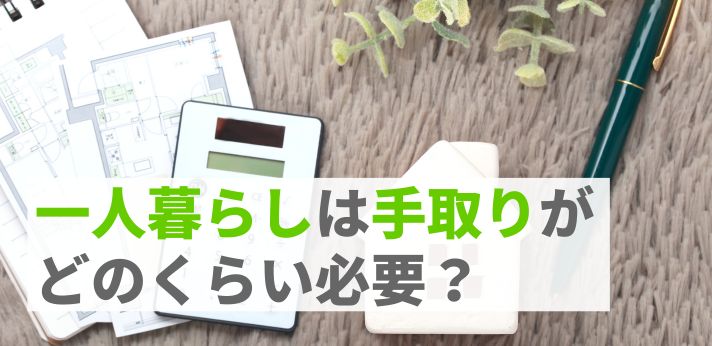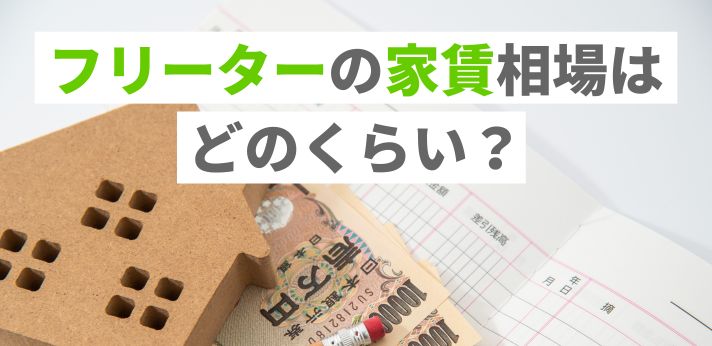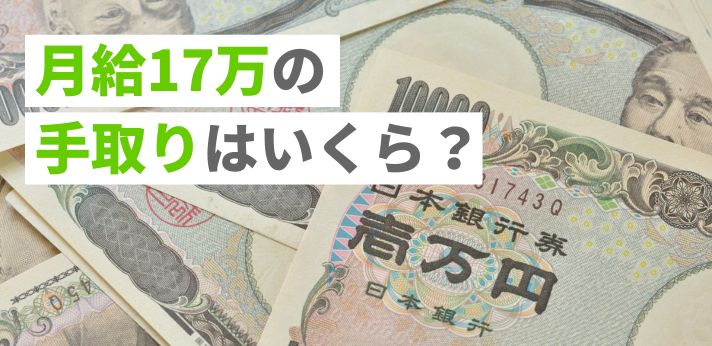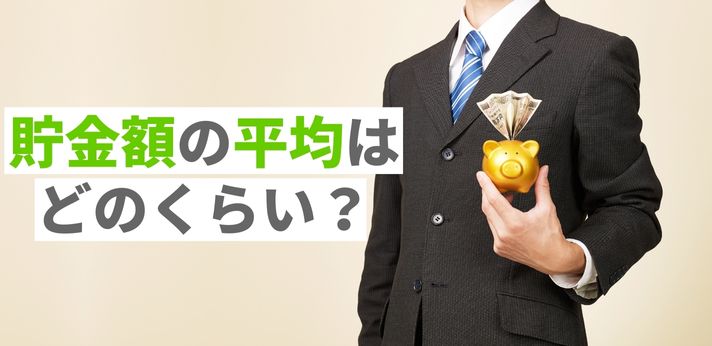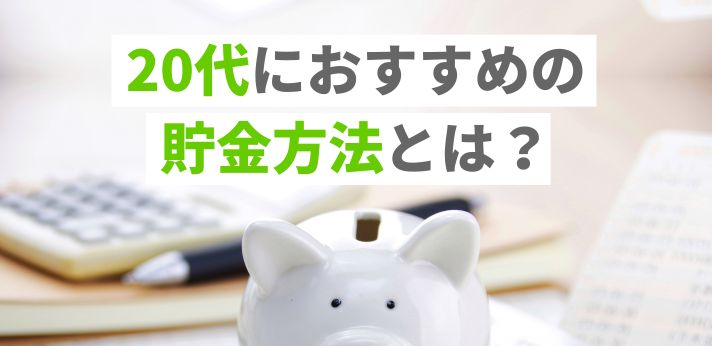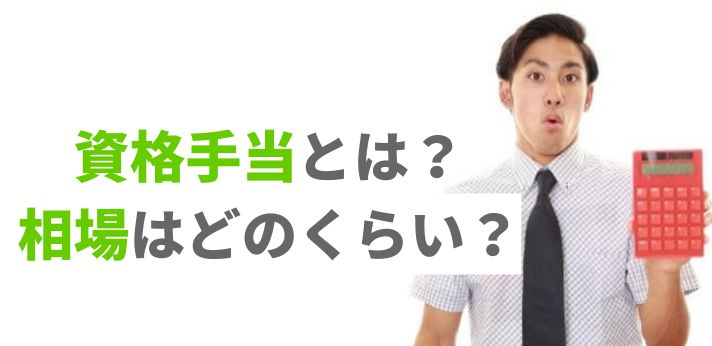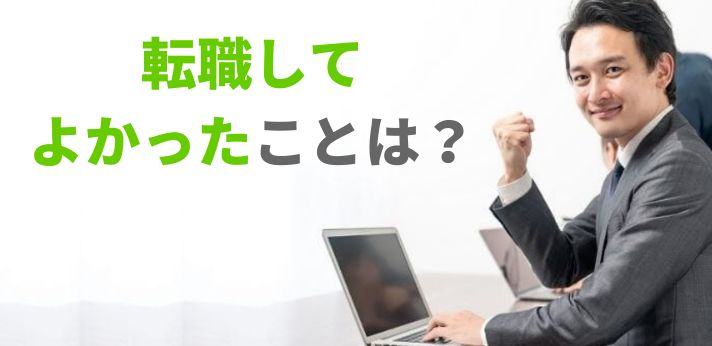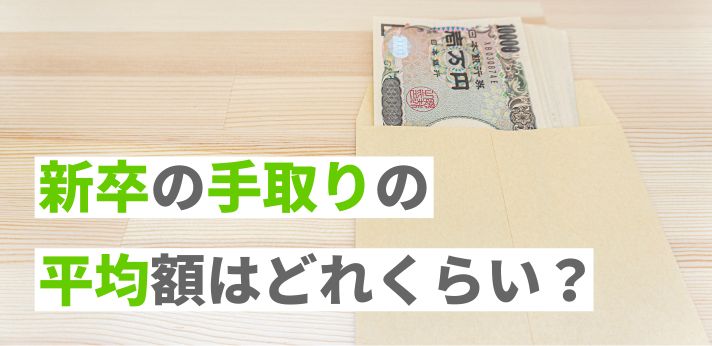月給24万の手取りは?基本給や額面などの違いとあわせて生活レベルも解説月給24万の手取りは?基本給や額面などの違いとあわせて生活レベルも解説
更新日
公開日
月給24万から税金や社会保険料を引いた手取り額は、およそ19万
「月給24万の場合の手取り額は?」と疑問を抱いている方もいるでしょう。月給は会社からの支給額であり、実際に手元に残る手取り額は税金や社会保険料を控除して求めます。
このコラムでは、月給24万の場合のおよその手取り額や年収についてご紹介。また、月給24万と年齢や学歴、雇用形態別での平均賃金の比較や、パターン別の生活レベルについてもまとめました。月給について知り、疑問や不安を解消するのにお役立てください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
この場合、年収は336万円という結果になりました。
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
月給24万の手取りはおよそ19万
月給が24万円の場合、手取り額はおよそ19万円です。手取り額とは、月の収入から保険料や税金を差し引いた、実質的に得られる金額のこと。この項では、基本給や月給といった言葉の違いや年収など、月給について知っておきたい基本的な情報をまとめました。
基本給や月給・月収の違い
基本給や月給・月収という言葉は、それぞれ指す内容が異なります。以下では、それぞれの意味についてまとめました。
月給24万円の場合の手取り額や気をつけるポイントを教えてください
手取り額は19万円前後で安定した生活は送れるものの、キャリアアップは常に意識しましょう
月給24万円の場合、手取り額は19万円前後となります。社会保険料や所得税、住民税などを合わせて、約5万円が毎月天引きされるためです。
手取り19万円前後の収入があれば、一人暮らしで家賃を支払いながら計画的に生活費を管理することでしっかり貯金もできるでしょう。家計簿アプリを活用して収支を見直し、無駄な支出を減らしながら貯金額の目標を立てるのも有効です。将来的にさらにゆとりある生活を目指すには、スキルアップや資格取得に積極的に挑戦し、自己投資を惜しまないことがポイントといえます。
また、より良い条件で働ける転職先を探すのも収入アップへの一つの手段です。多くの日本企業では、勤続年数や成果に応じて徐々に給与が上がっていきます。しかし、収入増加に伴い社会保険料や税金の負担が重くなる点も忘れないようにしましょう。資産形成は、生活水準を急激に上げずにバランスよくおこなうのがポイントです。
| 基本給 | ・年齢や経験、勤続年数など労働者本人の属性または労働者の従事する職務によって決められる賃金
・各種手当や残業代などは含まれない |
| 月給 | ・基本給に固定手当を足したもの
・固定手当とは役職手当や資格手当、住宅手当など、毎月固定で支払われる手当を指す |
| 月収 | ・基本給と固定手当、変動手当を足したもの
・変動手当とは残業代や時間外手当など、月によって支給金額が変動する手当を指す
・「年収(1年間に支払われた賃金の総支給額)÷12」の計算式でも求められる |
基本給は、支払われる給与のうちベースとなる部分を指します。月給・月収は基本給とは別に支給される手当が含まれるものの、それぞれ対象となる範囲が異なるのが特徴です。「月給24万」とは、月収のうち毎月一定して支払われる部分を指しているといえるでしょう。
ボーナスあり/なしの場合における年収
ひとくちに「月給24万」といっても、ボーナスの有無によって年収は大きく変動する可能性があります。ボーナスがある場合とない場合に分けて、それぞれの年収をシミュレーションしてみましょう。
ボーナスありの場合
ボーナスの支給は法律で定められていないため、企業によって支給の有無や1年の支給回数、支給額などは異なるものです。ここでは、月給2ヶ月分のボーナスが年に1回支給されるケースを想定して年収を求めます。
【計算式】
月給2ヶ月分+月給×12
=48万円+24万円×12
=336万円
ボーナスなしの場合
ボーナスが支給されない場合は、以下の計算式で年収を求められます。
【計算式】
月給×12
=24万円×12
=288万円
ボーナスなしの場合の年収は288万円でした。ボーナスありの年収と比較して、48万円もの差が生じます。
ただし、ボーナスあり・なしどちらの場合も、算出した年収を全額受け取れるわけではありません。控除される保険料や税金については、次の項で説明しています。あわせて参考にしてみてください。
月給ではなく手取りが24万の場合
手取りが24万円の場合、月給はおよそ30万円です。この場合、上記の計算式に当てはめると年収は以下のようになります。
- ・ボーナスあり
- 60万円+30万円×12=420万円
- ・ボーナスなし
- 30万円×12=360万円
年収を計算するときは、手取り額ではなく月給で計算するのが基本です。そのため、金額を間違えないようにしましょう。
額面から控除される保険料や税金とは
正社員に就職すると、原則として給与から社会保険料や税金が控除され、総支給額のおよそ75~85%にあたる残った額が支給されます。主な社会保険料や税金は、以下のとおりです。
- ・雇用保険
- ・健康保険
- ・介護保険
- ・厚生年金
- ・所得税
- ・住民税
- ・財形貯蓄や組合費など
社会保険とは、失業や病気・怪我、介護や定年後の生活など、いざというときのために整備されている公的な保険制度です。「雇用保険」「健康保険」「介護保険」「厚生年金」は社会保険に加入後から控除され、「介護保険」は満40歳の時点から支払い義務が生じます。
月給から控除される税金は、「所得税」と「住民税」の2種類。所得税は社会人1年目から徴収されます。一方、住民税は前年度の所得が100万円以上(居住地によって変動あり)の場合に支払うため、一般的には社会人2年目から徴収されるものです。
また、月給から一定額を貯蓄する財形貯蓄制度を利用していたり、労働組合費を徴収されたりする場合は、それらのお金も給与から天引きされるでしょう。
生活の中で工夫を行い、手取り収入のなかでやりくりする意識を持ちましょう
月給24万円の場合、天引きされる社会保険料や税金の目安は以下のとおりです。
- ・健康保険料:約1万2,000円
- ・厚生年金保険料:約2万2,000円
- ・雇用保険料:約700円
- ・所得税:約5,000円
- ・住民税:約1万円
ボーナスがないと仮定した場合、年収は約288万円となり、300万円に届きません。日常生活は満足に送れる水準とはいえ、「もう少し収入があれば楽になるのに」と感じることもあるでしょう。
先ほどはキャリアアップや自己投資の重要性について述べましたが、「生活を楽にするための工夫」を考えてみましょう。たとえば、ふるさと納税を活用して返礼品として日用品を受け取れば、家計が幾分楽になります。
また、結婚や出産などのライフイベントを想定している場合は、計画的な貯金も欠かせません。財形貯蓄による計画的な貯金やNISAを活用した資産形成を始めて、将来に備えておきましょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
月給24万はきつい?年齢別の平均と比較
月給が24万円の方のなかには、「手取りにするとあまりもらえなくてきつい…」「同世代と比較してどうなの?」と不安や疑問を感じている方もいるでしょう。
ここでは、学歴や年齢、雇用形態別の賃金をご紹介します。自分自身の月給と比較してみてください。
学歴別の給与
| 高校 | 専門学校 | 高専・短大 | 大学 | 大学院 |
|---|
| ~19歳 | 19万9,800円 | ー | ー | ー | ー |
| 20~24歳 | 21万7,300円 | 23万1,000円 | 23万400円 | 25万800円 | 28万6,200円 |
| 25~29歳 | 24万3,000円 | 25万6,100円 | 25万8,600円 | 28万3,900円 | 31万1,600円 |
| 30~34歳 | 26万5,400円 | 27万6,300円 | 27万9,600円 | 32万5,200円 | 38万8,000円 |
| 35~39歳 | 28万2,900円 | 29万6,800円 | 29万9,100円 | 37万3,200円 | 44万8,900円 |
高校や専門学校、高専・短大を卒業して就職した場合、25~29歳での平均賃金が24万円以上という結果に。また、大学を卒業して就職した場合は、20~24歳での平均賃金がおよそ25万円でした。
一方、大学院を卒業した場合は、20~24歳の時点で平均賃金がおよそ28万円です。
学歴ごとに平均賃金にばらつきがある理由として、大学や大学院に入学し勉学に励んだ努力や、そこで得た教養や専門知識を評価してもらいやすいことが挙げられます。
年齢/男女別の給与
| 男女計 | 男性 | 女性 |
|---|
| ~19歳 | 19万9,300円 | 20万3,600円 | 19万1,300円 |
| 20~24歳 | 23万2,500円 | 23万4,200円 | 23万600円 |
| 25~29歳 | 26万7,200円 | 27万4,700円 | 25万8,100円 |
| 30~34歳 | 29万9,500円 | 31万6,300円 | 27万1,600円 |
| 35~39歳 | 32万8,700円 | 35万2,300円 | 28万4,300円 |
上記より、20~24歳の平均賃金がもっとも24万円に近いことが分かります。その後は多少の差はあるものの、男性・女性ともに年齢を重ねるにつれ平均賃金も増加傾向に。勤続年数を重ねるごとにスキルや経験を評価され、昇給する機会が増えることが要因として考えられるでしょう。
そのため、年齢によっては月給24万円であることに対して、「もっと評価されても良いはず」「周りの友人と比べてもらえていない」と感じてしまう可能性があるといえます。
フリーター/正社員の手取り給与
雇用形態によっても収入は異なる可能性があります。以下は、ハタラクティブの独自調査「若者しごと白書2025」より、フリーターと正社員の月収分布を比較したものです。
※回答者数:フリーター 1,000人、正社員1,000 人
| フリーター | 正社員 |
|---|
| 10万円未満 | 38.8% | 2.2% |
| 10~15万円未満 | 21.1% | 6.1% |
| 15~20万円未満 | 14.8% | 31.3% |
| 20~23万円未満 | 4.7% | 23.5% |
| 23~26万円未満 | 1.5% | 11.2% |
| 26万円以上 | 1.7% | 14.2% |
| 答えたくない | 17.4% | 11.5% |
月給24万円が含まれる「23~26万円未満」の層を比較すると、フリーターは1.5%であるのに対し、正社員は11.2%という結果に。また、フリーターのボリュームゾーンは「10万円未満」が圧倒的な一方で、正社員は「15~20万円未満」でした。
月給24万前後の手取り額一覧
ここでは、月給22万円から28万円までの手取り額の目安をご紹介します。月給が増えた場合も、全額が給料としてもらえるわけではありません。月給ごとのおよその手取り額について確認しておきましょう。
なお、ここでは手取り額を額面の80%として計算しています。
| 額面 | 手取り |
|---|
| 22万円 | 17万6,000円 |
| 23万円 | 18万4,000円 |
| 24万円 | 19万2,000円 |
| 25万円 | 20万円 |
| 26万円 | 20万8,000円 |
| 27万円 | 21万6,000円 |
| 28万円 | 22万4,000円 |
先述したように月給24万円の手取り額は、およそ19万円です。住んでいる地域や世帯構成などによって手取り額が変動する可能性はあるものの、目安として把握しておきましょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
月給24万の生活レベルとは?パターン別に紹介
月給24万円の手取り額と必要な生活費を比較して、「余裕をもった一人暮らしはできる?」「実家にいたほうが良い?」と悩んでいる方もいるでしょう。この項では、パターン別の生活レベルについてご紹介します。
月給24万円の場合の生活レベルや、できることできないことを教えてください
月給24万円は実家暮らしや節約により、旅行や趣味を楽しめる可能性も。場合により貯蓄がなかなか難しい場合も考えられます
月給24万円と聞くと、一見それなりに稼いでいるように感じるかもしれません。ですが、実際の手取りは19万円前後であることが多く、思った以上に余裕がありません。
特に東京や大阪といった都市部で一人暮らしをしている場合、家賃の相場が高いため、生活費の多くが固定費となります。駅からのアクセスといった利便性やセキュリティなどを重視すると家賃は8万円〜9万円程度になり、水道光熱費や通信費を含めると、手取りの大半が「自由に使えないお金」として消えてしまうのが現実です。
さらに、通常の暮らしにかかせない食費や水道光熱費、通信費に加え、友人との飲み会や外食、洋服代、突然の冠婚葬祭など突発的な支出もあるでしょう。場合によってはギリギリの生活になってしまい、貯金や投資に回す余裕がほとんどなくなってしまいます。
ただし、家賃を抑えたり実家に暮らしたりと、住まいの費用を抑えられる場合は自由に使えるお金を増やせる可能性があります。節約することで旅行や趣味、レジャーなどを楽しむ余裕が生まれることも考えられるでしょう。
1.一人暮らし
| 項目 | 月平均額 |
|---|
| 食料 | 4万8,204円 |
| 住居 | 2万3,373円 |
| 光熱・水道 | 1万2,817円 |
| 家具・家事用品 | 5,938円 |
| 被服及び履物 | 5,175円 |
| 保険医療 | 8,502円 |
| 交通・通信 | 2万564円 |
| 教育 | 9円 |
| 教養娯楽 | 2万375円 |
| その他の消費支出 | 2万4,592円 |
| 消費支出 | 16万9,547円 |
上記より、一人暮らしに必要な費用はおよそ17万円と分かります。月給24万円の手取り額である19万円なら、生活費に加えて数万円ほど貯金できる余裕もあるでしょう。
ただし、居住地によって家賃や交通費などは異なります。都市部に住んでいる場合は家賃が高い傾向があるほか、地方であれば自家用車の維持費が必要な場合もあるでしょう。上記はあくまで参考にしつつ、自分の状況にあわせてシミュレーションしてみるのがおすすめです。
月給24万の場合における家賃の目安とは
月給24万円で一人暮らしをする場合、家賃は6万円を目安に考えるのがおすすめです。家賃は一般的に、手取り額の3割が適切といわれています。月給24万円の手取りである19万円を当てはめて考えると、6万円ほどが基準になるでしょう。
2.実家暮らし
月給24万円で実家暮らしをする場合、金銭的に余裕のある暮らしを実現可能といえます。先述した家計調査報告の単身世帯での消費支出を参考に、実家暮らしの場合の支出額についてシミュレーションしてみましょう。
| 項目 | 月平均額 |
|---|
| 食料 | ー |
| 住居 | ー |
| 光熱・水道 | ー |
| 家具・家事用品 | 5,938円 |
| 被服及び履物 | 5,175円 |
| 保険医療 | 8,502円 |
| 交通・通信 | 2万564円 |
| 教育 | 9円 |
| 教養娯楽 | 2万375円 |
| その他の消費支出 | 2万4,592円 |
| 実家に入れる生活費 | 4万円 |
| 消費支出 | 12万5,155円 |
実家暮らしの場合、家庭に入れるお金は家族と相談して決めることになります。仮に4万円を毎月家庭に入れるとしても、消費支出はおよそ12万5,000円。7万円ほどお金に余裕がある計算です。浮いたお金は貯金に回したり趣味に活用したりと、一人暮らしと比較して自由に使いやすいといえます。
3.2人暮らし
月給24万円で2人以上で暮らす場合は、世帯収入を上げましょう
月給24万円で2人暮らしをするとなると、現実的には厳しい生活を強いられます。生活費・家賃・食費に加え、突発的な出費や将来の備えまで考えると、節約だけでは限界があります。支出の見直しは大切ですが、心身への負担が大きくなることが考えられ、長期的に続けにくいのが現実です。
そこで、「世帯収入を上げること」が大切です。共働きや転職・副業・昇進などにより安定した収入源を確保することが、将来設計の土台になります。
また、賃貸で家賃を支払い続けるより、条件次第では住宅ローンを組んでマイホームを持つほうが、同等の支出でより良い住まいを手に入れられる場合もあります。ただし、住宅ローンには金利や返済負担、金利上昇といったリスクがあるため、マイホームの購入には十分な資金計画が不可欠です。
今後、子育てや教育費の負担が増えることも視野に入れ、ライフステージごとに「住まい」と「収入」のバランスをどう整えるかが重要です。不動産購入は「身の丈に合った判断」が何より大切です。
なお、下記のデータは「2人以上の世帯」を対象にしているため、2人暮らしの場合の消費支出のみを示すデータではありません。あくまで参考としてご覧ください。
| 項目 | 月平均額 |
|---|
| 食料 | 8万9,936円 |
| 住居 | 1万8,088円 |
| 光熱・水道 | 2万3,111円 |
| 家具・家事用品 | 1万2,788円 |
| 被服及び履物 | 9,985円 |
| 保険医療 | 1万5,348円 |
| 交通・通信 | 4万1,731円 |
| 教育 | 1万1,705円 |
| 教養娯楽 | 3万240円 |
| その他の消費支出 | 4万7,311円 |
| 消費支出 | 30万243円 |
データより、およそ30万円の生活費が掛かることが予想されます。居住地や世帯収入によっては節約すれば不可能ではないものの、「生活にゆとりがなくきつい」と感じる可能性があるでしょう。
4.子育てしながらの生活
月給24万円の場合、子育てをしながら生活レベルを保つのは厳しい可能性があります。子育てをする場合、2人暮らしで掛かる生活費に加えて、子どもの食費や衛生用品、医療費などが掛かるものです。将来を見据えて貯金をする必要もあるため、生活レベルを保つのが難しい恐れがあります。
また、出産や育児にあたっては、仕事を休んだりセーブしたりする場合もあるでしょう。将来的に子育てを考えているのなら、生活費の増加や収入減のリスクも考慮し、今のうちに収入を増やしておくのがおすすめです。
月給24万の場合にできること
月給24万円の場合、お金をしっかり管理すれば貯金をしたり大きな買い物をしたりすることも不可能ではありません。ここでは、手取り19万円でできることについて解説します。
貯金できる額
月給24万円で貯金をする場合、生活費や世帯構成によって適切な貯金額は異なります。たとえば、一人暮らしをする場合なら、先述したように消費支出はおよそ17万円です。平均程度に支出を抑えれば2万円ほど貯金できるほか、切り詰めればさらに貯金額を増やせる可能性があります。実家暮らしの場合も同様です。
反対に、2人暮らしや子育てを考えている場合は、生活を切り詰めなければまとまった額の貯金は難しい可能性があります。
自炊や通信費の見直しなどで支出を押さえる方法もある
貯金額を増やすには、自炊したり通信費を見直したりして支出額を抑えるのも方法の一つ。コンビニやスーパーのお惣菜は自炊と比較すると割高なこともあり、積み重なると大きな出費になりかねません。また、できるだけ安価なキャリアでスマートフォンを契約することも、節約効果を期待できるでしょう。
家の購入
月給24万円なら、家を購入できる可能性はあります。住宅ローンを利用することで、無理なく支払い計画を立てられるでしょう。
ただし、ローンを利用するには審査を通過する必要があります。世帯年収のおよそ8倍以上の価格の家を購入しようとしたり、転職したばかりだったりすると、審査にとおらない恐れがある点に注意が必要です。
車の購入
月給24万円で車を購入することも可能といえます。家と比較すると高い買い物ではないため、ローンの審査基準はそれほど厳しくない傾向があるようです。
車を購入する際の注意点については、以下のコラムで解説しています。
月給24万から手取りアップを目指す4つの方法
「月給24万円のままでは不安」「手取りを増やしたい」という場合は、昇進を目指したり副業に挑戦したりする方法があります。手取りアップを目指す主な方法を以下にまとめたので、今の収入に不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
月給24万から手取りアップを目指す方法
- 現在勤めている会社で昇進や昇格を目指す
- 副業を始めて本業以外でも収入を得る
- 知識やスキルを身につけて独立する
- 転職する
1.現在勤めている会社で昇進や昇格を目指す
月給24万円から手取りを増やすには、今の職場で昇進や昇格を目指すのが確実な方法といえます。仕事に必要なスキルを身につけたり仕事の幅を広げたりすれば、給与の査定にプラスに働き手取りアップにつながる可能性があるでしょう。
現職で昇進・昇格を目指す場合、評価面談のタイミングで上司に相談してみるのがおすすめです。昇格試験がある場合は案内してもらえるほか、意欲を積極的に示すことで評価につながる可能性があります。
ただし、昇進や昇格までには一定の時間が必要なため、「今すぐ手取りを増やしたい」という方にとってはもどかしさを感じることも。出世するために必要な心構えを知りたい方には、以下のコラムがおすすめです。
資格取得で手当を支給する会社もある
今の仕事に役立つ資格を取得すれば、資格手当を支給してもらえる可能性があります。手当の対象となる資格や支給額は企業によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
また、なかには資格取得のための支援制度を設けていたり、取得時に報奨金を支給したりする企業もあるようです。経済的に資格を取得できたり評価を得られたりするため、手当の有無とあわせて確認しておくことをおすすめします。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
2.副業を始めて本業以外でも収入を得る
できるだけ早く月給24万円から手取りを増やしたいなら、副業を始めるのも方法の一つです。短時間からできるアルバイトをしたり、クラウドソーシングで自分にできそうな仕事を始めたりと、副業にはさまざまなやり方があるのが特徴。ハンドメイドや動画編集作業など、得意なことを活かせる副業もあります。
ただし、企業によっては副業を禁止していたり、制限していたりすることも。事前に就業規則をよく確認し、本業に支障が出ない範囲で行うことが大切です。
3.知識やスキルを身につけて独立する
月給24万円から手取りを増やすには、知識やスキルを身につけて独立する方法もあります。企業勤めの場合は月給がある程度安定している一方で、頑張りや成果が月給に反映されにくいことも。独立すれば担当案件の数だけ収入を見込めるため、頑張りや成果次第で手取り額を増やせる可能性があります。
ただし、独立後に仕事を得るには自分から売り込む必要があり、事業が軌道に乗るまではまとまった収入を得られない恐れも。また、独立後は、クライアントとの連絡やスケジューリングはもちろん、事務作業や税金関係の手続きもすべて自分で行う必要があります。まずは副業として挑戦して向き不向きを確認したり、会社勤めのメリット・デメリットと比較したりして、よく考えて決断するのがおすすめです。
4.転職する
「今の会社で月給24万円以上は望めない」という場合は、手取りアップを実現できる会社へ転職することをおすすめします。経験やスキル、ポテンシャルを高く評価してくれる会社に転職すれば、ベースとなる基本給がアップしたり手当が支給されたりして月給が高くなる可能性があるでしょう。
また、適切な評価を受けられる環境に身を置くとモチベーションが高まりやすく、昇進や昇格といったキャリアアップに前向きになれるもの。仕事へのやりがいや充実感を得られたり、月給アップに向けてさらに意欲がわいたりと、好循環が生まれる効果が期待できるでしょう。
「月給24万では足りない」「転職して手取りを増やしたい」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、フリーターや既卒、第二新卒など、若年層に特化した就職支援を行っています。専任のキャリアアドバイザーが、一人ひとりの適性や希望を丁寧にヒアリング。取り扱っている求人のなかから、あなたに合った求人を5~6社厳選してご紹介します。ハタラクティブは未経験者を積極的に採用している企業の求人が充実しているため、経歴やスキルに不安のある方も安心です。
また、応募先の企業にあわせた応募書類の書き方や面接のアドバイスを行い、就職・転職活動を一貫してサポートします。サービスはすべて無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
月給24万や手取りに関してよくあるQ&A
ここでは、月給や手取りに関してよくある質問について、Q&A方式でお答えします。「月給24万の手取りはいくら?」「月給と月収の違いは?」といった疑問にもお答えしているので、ぜひ読み進めてみてください。
新卒で月給24万円の場合、手取り額は20万円ほどといえます。ただし、2年目以降は住民税が控除されるため、手取り額は19万円ほどに減るでしょう。
以下のコラムでは、それぞれ新卒の手取り額の平均と、税金や社会保険料の計算方法を解説しています。「新卒の手取りはどのくらい?」「手取りの計算方法を知りたい」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
月給は「基本給+固定手当」、月収は「基本給+固定手当+変動手当」です。固定手当とは住宅手当や資格手当など毎月一定の額を支払う手当、変動手当とは残業代や時間外手当など月によって変動する手当のこと。1ヶ月に支払われた総支給額を示す場合は、「月収」を使います。
基本給や月給、月収などの言葉の違いについては、このコラムの「基本給や月給・月収の違い」をご覧ください。
手取りアップを目指す場合、転職は有効な方法の一つです。今の経験やスキルを高く評価してくれたり、ポテンシャルを見込んでくれたりする企業に転職すれば、手取りが増える可能性はあるでしょう。ただし、給与だけを重視して転職を決めると、入社後にミスマッチを感じる恐れも。社風や求められる人物像なども丁寧に確認し、自分に合った会社を選びましょう。
就職・転職エージェントのハタラクティブでは、一人ひとりに合った求人を、キャリアアドバイザーが厳選してご紹介します。ぜひお気軽にご相談ください。