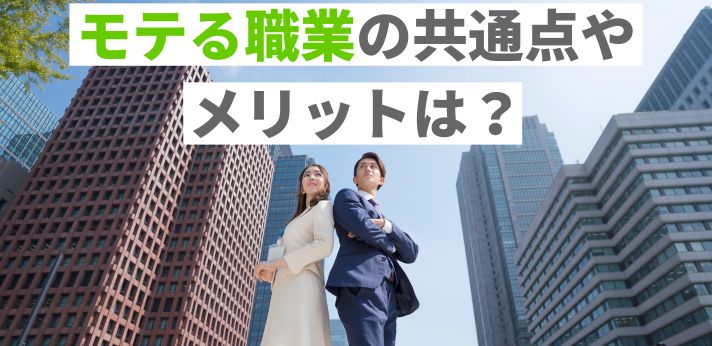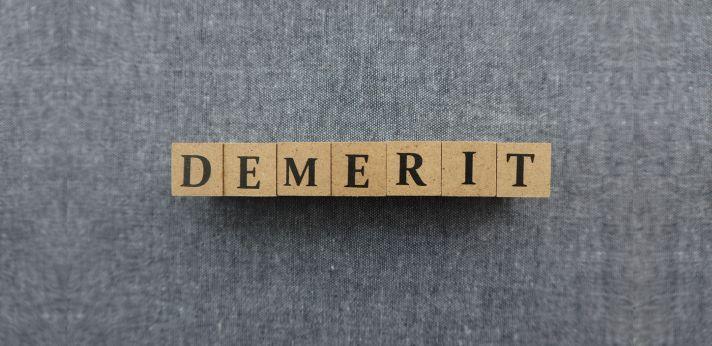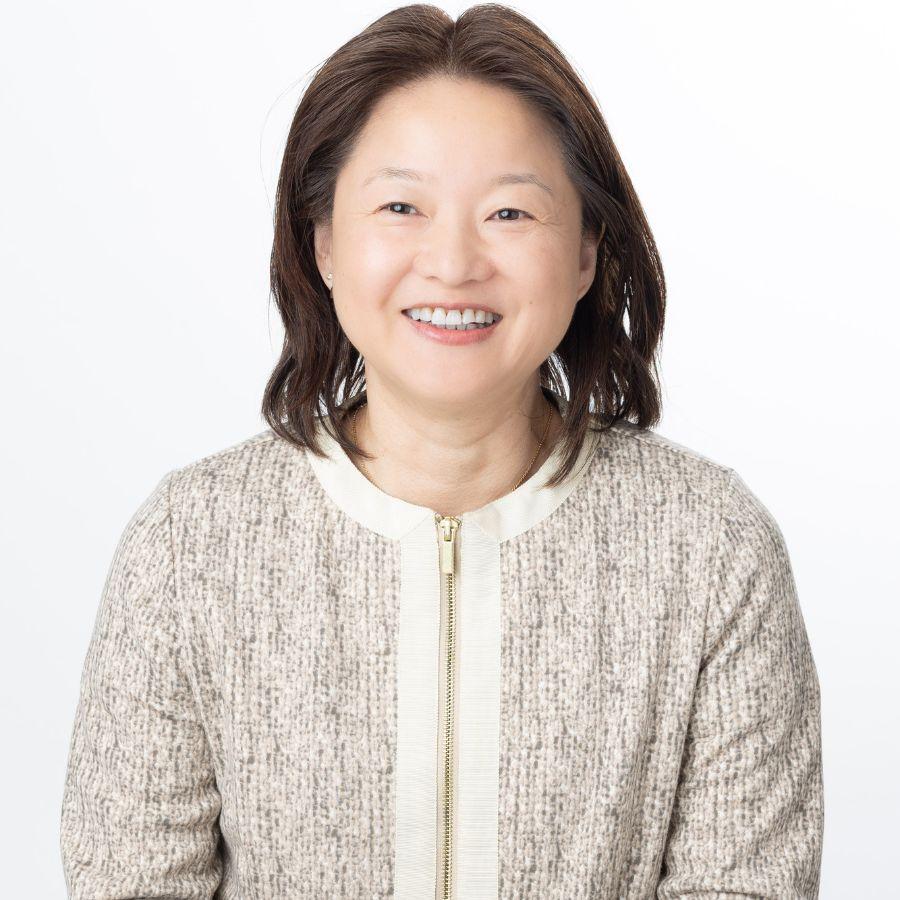ものづくりの仕事20選!主な種類や向いている人の特徴を紹介しますものづくりの仕事20選!主な種類や向いている人の特徴を紹介します
更新日
公開日
ものづくりの仕事は製造系や伝統工芸の職人など、幅広い種類がある
「成果が形に残る『ものづくりの仕事』に興味がある」「ものづくりに携わってみたい!」という思いがあっても、未経験から挑戦できるのか分からず一歩踏み出せない方もいるかもしれません。未経験から挑戦できるものづくりの仕事は複数ありますが、大切なのはそのなかから自分に合った仕事を見つけることです。
このコラムでは、ものづくりの仕事における代表的な職種や就職するメリットを解説。また、未経験から自分に合うものづくりの仕事を探す方法も詳しくご紹介しています。憧れのものづくりの仕事について理解を深め、仕事探しに踏み出しましょう。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
中小企業庁「ミラサポplus」
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
ものづくりの仕事の種類一覧
ここでは、代表的なものづくりの仕事を分野別にご紹介します。ものづくりの仕事に興味のある方は、どのような仕事があるのかを確認してみましょう。
1.製造系
製造系のものづくりの仕事には、金属の加工や溶接、設計技術者など、さまざまな職種が存在します。以下では、製造系で活躍する主なものづくりの仕事の特徴をまとめました。
製造系のものづくりの仕事
- 板金工・金属プレス工
- 溶接工
- プラントエンジニア
- 生産用機械組立
- 自動車組立
板金工・金属プレス工
板金工・金属プレス工とは、金属板を加工・成形する職業のこと。板金工は人の手で加工したり機械を操作したりする作業が多いため、一つひとつの仕事をじっくり進めます。
一方、金属プレス工は専用の機械を用いて多くの部品や製品を生産するため、早く仕上げられるのが特徴です。職業情報提供サイトjobtagの「金属プレス工」によると、腕時計やカメラといった精密機器から自動車のドアまで、大小さまざまな金属製品や部品の製造を行います。
どちらも就職のために特別な学歴や資格は問われにくく、未経験から挑戦しやすいでしょう。ただし、技術を習得するまでに時間が掛かる場合があります。
溶接工
溶接工は、金属を熱で溶かして接合する「溶接作業」を行う職業です。ビルや住宅などの建造物やパイプライン、発電設備などを作る際に活用されており、生活に関わる製品や部品の製造に直接携われる仕事といえます。
既出の資料「jobtag」の「溶接工」によると、溶接工も未経験や無資格から挑戦可能です。ただし、アーク溶接やガス溶接などを行う場合は定められた講習を修了する必要があります。実務を積みながらスキルアップできるため、体力や手先の器用さに自信のある方におすすめです。
プラントエンジニア
プラントエンジニアとは、「プラント」と呼ばれる石油や鉄といった製品を製造したり、廃棄物や水を処理したりする設備の基本設計や詳細設計などを行う仕事です。プラント設計には、工場を稼働させるために数多くの部品や装置が必要であり、それぞれの役割や機能に関する知識の習得が求められます。
jobtagの「プラント設計技術者」によると、大学や高専などの理工学部で専門知識を学んだ人が就業者に多いようです。設計にあたっては、ほかの分野の専門家やスタッフとの連携を取るためのコミュニケーション能力や、設計に使われるシステムやツールの知識なども求められます。
生産用機械組立
生産用機械組立は、金属の加工やプラスチック製品の生産、土木建設工事などに使用される機械を組み立てる仕事です。jobtagの「生産用機械組立」にあるように、同じ機械を大量に製造する場合はライン生産を行い、オーダーメイドで機械を作る場合は一人や少人数のチームを組んで製造します。機械の製造だけでなく、製造前の現地調査や組立後の調整・動作確認などを担当する場合もあるようです。
学歴や資格の有無に関わらず就業できる仕事であるものの、入社後にクレーンやフォークリフトの免許を取得する必要がある場合も。資格や免許取得の支援を行っている企業もあるため、求人情報をしっかり確認したうえで応募先を選ぶのが望ましいでしょう。
自動車組立
自動車の車体にドアやエンジンといった部品を設置し、組み立てるのが自動車組立の仕事です。多くの場合はライン作業で作業を行い、流れてくる車に担当している部品を取り付けていきます。
jobtagの「自動車組立」によると、近年は組立作業にコンピューターを使用することも。機械のサポートを受けながら正確に組み立てられるため、未経験から挑戦しやすいのが特徴です。研修を受けたり実務経験を積んだりすれば、管理者としてキャリアアップも目指せるでしょう。
2.建設系
建設系は、道路や学校などを造る建設工事のほか、マンションや住宅の建築工事、ダムやトンネルの土木工事といった仕事があります。以下は、建設系のものづくりの仕事として挙げられる職種の例です。
建設系のものづくりの仕事
- 建築設計技術者
- 大工
- とび職人
- 左官
- 建設・土木作業員
- CADオペレーター
建築設計技術者
jobtagの「建築設計技術者」によると、建築設計技術者とは、住宅や学校、商業施設といった建築物の設計を担当する仕事のことで、「建築士」とも呼ばれます。建物の用途や予算、立地といった情報の調査や顧客へのヒアリングなどを行い、要望を盛り込みつつ建物の構造やデザインを固めていくのが主な業務内容です。
就業するには高校や専門学校・大学の建築系学科で専門知識を学ぶ必要があります。また、一定以上の規模の建築物を設計するには、建築士の資格を取得しなくてはいけません。難易度の高い仕事ではあるものの、長く残る建物を設計できるやりがいのある仕事といえます。
大工
大工は、主に木造住宅の建築に携わる仕事です。のこぎりやカンナといった工具を使って、加工や組立などを行います。近年では、コンクリートや金属といった木材以外の資材を扱うことが増えているため、資材や工具についての幅広い知識や技術が求められるでしょう。
jobtagの「大工」によると、大工は学歴や資格などが不要なことが多く、工務店に就職したり棟梁に弟子入りしたりして働きながら技術を磨いていくのが一般的です。また、ハローワークのハロートレーニングをはじめとする職業訓練校に通うのも方法の一つ。建築士や木造建築士の資格を取れば、独立を目指すことも可能です。
宮大工
宮大工とは、寺社仏閣をはじめとする歴史的建造物や住宅の建築・修繕などを専門に手がけるものづくりの仕事です。日本に古くから伝わる「木組み」という技法を使い、釘や金物を使わずに建物を完成させます。ときには世界遺産や重要文化財の修復や建て直しを担うこともあり、日本のものづくり文化を後世に伝える重要な仕事といえるでしょう。
宮大工の仕事も一般的な大工と同様に、学歴や資格は問われにくいようです。宮大工として働くには、棟梁に弟子入りするか、大学や専門学校で学んだのちに工務店に就職して経験を積み、知識や技術を磨くのが一般的。仕事の性質上、建築学に加えて神道・仏教や日本文化への理解も求められるため、一人前の宮大工になるにはある程度の時間や努力が必要なようです。
とび職人
とび職人の主な仕事は、主に住宅やビル、高速道路などの工事に必要な足場や仮説構造物を管理すること。jobtagの「とび」によると、木造住宅の建築時に足場を組み立てる「建築とび」、中高層ビルの鉄骨や橋梁の組立など大型工事を手がける「鉄骨とび」などがあり、働く場所によって仕事内容はさまざまです。
とびは高所での作業が主になるため、高所への適性や事故を未然に防ぐための集中力、判断力などが必要といえます。学歴や資格に関わらず挑戦できる仕事ではあるものの、危険と隣り合わせの仕事のため、自分に適性があるかしっかり見極める必要があるでしょう。
左官
左官は、コテやローラー、専用の機械などを駆使して床や壁を塗り上げるのが主な仕事です。はがれたりひび割れたりしない丈夫な壁を作るために、いくつかの工程に分けて丁寧に塗り上げる必要があります。
jobtagの「左官」によると、左官は、大工と同じように工務店に就職して働きながら技術を身につけたり、職業訓練校で学んだりすることで就業が可能です。学歴や資格がなくても、現場でスキルアップすることで長く活躍できる仕事といえるでしょう。
建設・土木作業員
建設・土木作業員は、道路の建設や治水工事といった現場で、建設用の大型機械では対応できない繊細な作業を担当します。掘削やコンクリートの打込み、ブロックの運搬や芝張りなどの作業を、小型の機械や工具を使用して進めていくのが特徴です。
jobtagの「建設・土木作業員」によると、建設・土木作業員の仕事は学歴や資格にかかわらず挑戦できることが多く、就業前には工事の内容や作業時の規律・危険区域などに関する教育を受けられます。ブルドーザーやクレーンの資格を取ったり、技能講習を受けたりすれば業務の幅が広がるため、より活躍できるようになるでしょう。
CADオペレーター
jobtagの「CADオペレーター」によると、CADオペレーターとは、設計に用いるCADというソフトを駆使して建築物や機械の図面を作成する仕事のこと。顧客の要望や設計技術者の指示に基づき、詳細な設計図面を作り上げていきます。
作成した設計図面は、工事費用の見積作成や材料資材の調達だけでなく、完成後の改修にも役立つものです。建築業界以外にも、自動車や家具・家電など多様なメーカーに活躍の場があり、扱うものに特化したCADを使用することもあるようです。
就業に学歴や資格は必要ないものの、CADの知識があることは欠かせない要素の一つ。また、設計技術者の指示を正確に汲み取るコミュニケーション能力や読解力、設計に必要な論理的思考力や数学の素養なども求められます。
3.職人系
ものづくりの仕事における職人の仕事は幅広く、伝統工芸品や食品、楽器や陶芸などさまざまな分野で活躍しています。ここでは、代表的な職人として「食品に関する職人」と「伝統工芸品や日用品に関する職人」をチェックしてみましょう。
食品に関する職人
食品に関する職人には、すし職人や和菓子職人、パティシエ、ブーランジェなどが挙げられます。調理の技術だけではなく、食のスペシャリストとして旬の食材や道具の扱い方に関する知識も有しているのが特徴です。主に料亭や菓子店、レストランといった店に就職し、腕を振るっています。
食品を扱う場合、専門学校で専門的な知識や技術を習得してから就職するのが一般的。未経験からでは難しい側面もあるものの、個人経営の店などで修行してスキルを身につけることも可能です。
伝統工芸品や日用品に関する職人
日本の伝統工芸品や、家具や畳といった日用品に関する職人もいます。伝統工芸品とは、有田焼や信楽焼といった磁器・陶器、こけしや赤べこをはじめとする郷土玩具など、日本に古くから伝わる工芸品を総称したもの。海外で評判の高いものも多く、日本の重要な産業の一つです。
職人として働くには、工房に弟子入りして技術を学ぶのが主な方法といえます。一人前になるまで長い時間が掛かることも多いものの、技術を習得すれば高く評価される工芸品や日用品を生み出せるでしょう。
4.IT系
ものづくりの仕事には、IT系の仕事も含まれます。ここでは、主なIT系のものづくりの仕事をご紹介。IT業界でのものづくりに興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
システムエンジニア(SE)
また、「システムエンジニア(基盤システム)」はサーバーやパソコンといったITインフラの設計を行う仕事です。このように、関わる分野によって仕事内容や求められるスキルは異なります。
システムエンジニアになるにあたっては、学歴や資格を問われにくいようです。ただし、プログラミングやITインフラなどに関する基礎知識をもっていると、選考で有利になりやすいでしょう。
プログラマー
IT系のものづくりの仕事として、プログラマーも挙げられます。jobtagの「プログラマー」によるとプログラマーの仕事は、システムエンジニアの作成した設計書に基づいて、プログラムを作成することです。SEがシステム全体の設計や管理を行い、プログラマーが実際にコードを書いていくというように役割分担し、システムを創り上げていきます。
就職にあたって必要な学歴や資格はないものの、入社後にはOSの知識やプログラミング言語など、情報技術に関する知識・スキルの習得が不可欠です。IT技術は日々進歩しているため、常に最新の情報をキャッチアップしようとする知的好奇心や勤勉な姿勢も求められます。
5.クリエイティブ系
クリエイティブ系のものづくりの仕事は、デザイナーやゲーム制作など幅広く新しいものを作って提供する仕事を指します。下記では、クリエイティブ系のものづくりの仕事をまとめました。
クリエイティブ系のものづくりの仕事
- CG制作
- Webデザイナー
- ゲームクリエーター
- 製版オペレーター・DTPオペレーター
- インダストリアルデザイナー
CG制作
CG制作とは、コンピューターを使って絵や映像、アニメーションなどのCG(コンピューターグラフィック)を制作する仕事のこと。映画やテレビ番組、ゲームといったエンタメ作品だけでなく、建築や医療などの現場でも活用されており、近年活躍の場は広がっています。
jobtagの「CG制作」によると、就職に必要な学歴や資格はないものの、大学や専門学校でデザインやCGを学んでいると有利になりやすいことも。長時間作品に向き合うことが多いため、造形力やセンス以外にも集中力や根気強さ、チームで一つのものを作り上げていくコミュニケーション能力などが求められるでしょう。
ゲームクリエーター
ゲームクリエーターとは、家庭用ゲーム機やスマートフォン、パソコンなどのゲームソフトやアプリを制作する職業です。jobtagの「ゲームクリエーター」によると、主に「企画」「グラフィック」「プログラミング」「サウンド」担当に分かれ、分業制で一つのゲームを作り上げていきます。
担当によって仕事内容は大きく異なり、「企画」には発想力や創造力、「グラフィック」にはアイディアを絵として描き起こす描画力というように異なるスキルが必要です。また、「プログラミング」はコンピューター言語の知識や技術、「サウンド」は音楽技術などが求められます。
すべての職種に共通で求められるスキルとしては、コミュニケーション能力や協調性のほか、世の中の流行や新しいものへの好奇心・探求心も重要でしょう。
製版オペレーター・DTPオペレーター
製版オペレーター・DTPオペレーターは、コンピューターを使用して印刷物のレイアウトやデザインを考える職業です。文字や画像の位置やデザイン、色の調整などを行い、雑誌やカタログ、ポスターなどの印刷物を作り上げていきます。
jobtagの「製版オペレーター、DTPオペレーター」によると、就業時に特別な資格や経験は必要ないものの、デザインやDTP、写真などに関する知識があると有利になることも。また、デザイナーと意見をすり合わせたり、印刷所との連携を行ったりする必要があるため、コミュニケーション能力やスケジュール管理能力も重要な要素といえます。
インダストリアルデザイナー
自動車や家電製品、情報機器といった製品のデザインを決めるのが、インダストリアルデザイナーです。ユーザーのニーズや好みといった情報を収集し、スケッチや3Dプリンターなどを活用してデザインを進めます。
jobtag「インダストリアルデザイナー」によると、就業にあたり必須の学歴や資格はありません。しかし、大学・短大・専門学校などで、設計・デザインの専門知識を学んでから入職することが一般的でしょう。
インダストリアルデザイナーは、実現可能なデザインを提案する必要があるため、生産する工場のキャパシティや能力、素材や構造についての知識が求められます。また、造形力だけでなく、多角的な視点でデザインを突き詰める論理的思考力や分析力なども重要です。
Webデザイナー
Webデザイナーは、Webサイトの企画を立ち上げたりデザインを考えたりするものづくりの仕事です。顧客からWebサイトの目的や要望、イメージなどをヒアリングし、コンセプトを提案します。その後はスケジュールにあわせてデザインや機能などを考え、サイトを制作。昨今はインターネットの普及によって多くの企業や自治体がWebサイトを開設しているため、幅広く活躍できる仕事といえるでしょう。
job tagの「Webデザイナー(Web制作会社)」によると、Webデザイナーになるために学歴や資格が必要とされることは少ないようです。ただし、デザインやイラスト、デザイン作成ソフトの知識・技術があると有利になりやすいでしょう。
参照元
職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag
トップページ
自分に合うものづくりの仕事を見つけるには、職種よりも自分の適性を見つめよう
ものづくりの仕事はさまざまな職種や働き方、就職先があり、とても幅広いものです。たとえば、同じ溶接の仕事でも工場のなかで決められた溶接を繰り返す職場もあれば、現場に出かけていき、さまざまな形のものを溶接する職場もあります。
そのため、自分に合ったものづくりの仕事を見つけるためには、職種にこだわるよりも先に普段の自分の生活を振り返ってみましょう。外仕事が好きか、身体を動かすのが好きか、ずっと座っていても苦にならないかなど、自分の適性をしっかりと見極めるのが大切です。自分にとって働きやすい環境を事前に把握できていれば、自分に合った仕事を見つけやすくなるでしょう。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
製造系ものづくりの5つの仕事内容とは
ものづくりの仕事としてイメージしやすい製造系の仕事内容は、大きく5つに分けられるのが特徴です。それぞれの工程を知り、働き方のイメージをするのにお役立てください。
1.加工
製品の原材料をカットしたり、引き伸ばしたりして部品の形にしていくのが加工作業です。まずは仕入れた材料を検品し、キズや歪みがないかを確認します。次に、機械を使って部品を加工したり、ラベルを印刷したりして次の工程に進むのが一般的な流れです。
2.部品の組立
設計図に沿って部品を組み立てる人を「組立工」といいます。多種多様なメーカーの下請工場では、自動車を組み立てることもあれば、精密機器のものづくりを担当する場合も。担当する製品によって工程が異なり、求められるスキルにも違いがあるでしょう。
3.検品
完成した製品に不良品がないかチェックするのが検品です。キズやへこみ、異形のほか、動作確認のため試験も行います。不良品を見逃してしまうとクレームやリコールになってしまう恐れもあるため、企業の信頼を担う大事な仕事です。
4.塗装
塗装は、製品に色をつけるだけでなく、乾燥や水濡れから保護するための工程でもあります。自動車や飛行機の場合はロボットが塗装を行うため、機械オペレーションが主な仕事となるでしょう。家具の場合は、人の手でオイル塗装やウレタン塗装を行います。
5.出荷
倉庫から製品をピッキングし、梱包して出荷します。大規模な倉庫ではピッキングに時間が掛かるため、効率的に作業を進める工夫が必要です。重い製品を扱う場合は、フォークリフトを使う場合もあります。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
ものづくりの仕事とは?
「ものづくりの仕事」とは、技術を駆使して何らかの製品を生み出す仕事を指します。「ものづくり」と聞いてイメージしやすい製造系や職人系だけでなく、建設系やクリエイティブ系、IT系などの業種も幅広く含まれているのが特徴です。また、直接的にものを作る職種以外にも、企画・開発・マーケティングなど間接的にものづくりへ関わる職種も存在します。
ものづくりの仕事では、専門性の高さから知識や経験を問われる仕事もあれば、人材を教育していく観点から未経験者が活躍しやすい仕事もあるのがポイントです。この項を参考に、ものづくりの仕事として挙げられる産業や日本での動向について理解を深めましょう。
ものづくりの仕事における主な産業
ものづくりの仕事の範囲は広く、食品や繊維、木製品など、普段何気なく使用しているものや私生活を送るうえでなくてはならないものを生み出しています。以下は、総務省統計局の「経済センサス‐基礎調査 産業分類一覧」より、「製造業」として分類される産業を一部抜粋したものです。
- ・食料品製造業
- ・繊維工業
- ・木製品製材業
- ・家具装備品製造業
- ・パルプ製造業
- ・プラスチック製品製造業
- ・鉄鋼業
- ・業務用機械器具製造業
上記の一例を見ると、ものづくりの仕事は人々の生活に幅広く関わりがあることが分かります。それぞれの産業によって仕事内容や適性、必要なスキルなどは異なるため、仕事選びの際は多くの産業から自分に合ったものを選ぶことが大切です。
日本のものづくりの動向
日本のものづくりは高い技術力が評価されている一方で、人手不足が課題となっているようです。ここでは、日本のものづくり産業の動向について簡単にご紹介します。
需要が高い一方で人手不足が深刻
教育制度の充実化やデジタル化が進んでいる
また、デジタル化も注目すべきポイントです。同資料(p.23)によると、2024年の調査ではデジタル技術を活用しているものづくり企業は83.7%にのぼりました。
デジタル技術に特化した人材の新卒・中途採用の取り組みを行う企業も一定数あり、ものづくりそのものに求められる知識やスキルのほかに、デジタル技術への理解も必要になりつつあることが推察できます。
女性の活躍促進や学び直しの推進などの対策も取られている
ものづくり分野の人材育成強化に向け、女性の活躍促進や学び直しの推進などの対策も取られているようです。経済産業省の同資料によると、女性の活躍促進について、「女性がものづくりや理数系分野への関心を高めることができるような取組や、女性研究者などが自らの力を最大限に発揮できるような環境整備」が実施されています。
また、学び直しについては、「社会人の学び直しのための実践的な教育プログラムの充実・学習環境の整備」を実施。「一度は就職したけれどものづくりの仕事に挑戦したい」「ものづくりの仕事へキャリアチェンジを考えている」という方も、専門知識や技術を学んで再挑戦できる環境整備が進められているといえるでしょう。
ものづくりについて学べる機会の創出や男性・女性問わず能力を活かして働ける環境の整備など、人材確保や育成に向けさまざまな観点から改革が進められているようです。
日本のものづくりが注目されている理由を教えてください
ものづくりは社会と経済の発展に欠かせない要素のため
日本は資源が乏しい国のため、他国から原料を輸入し、それを工業製品として加工して輸出する「ものづくり」が外貨を稼ぐ手段のひとつです。幕末から明治、そして戦後など、日本はものづくりを基板とした輸出産業により大きく成長してきた歴史があります。つまり日本のものづくりは、国の産業の一つとして、経済を成長させるための重要な要素になっているのです。
また、近年では、世界的にデジタル化やAI化などが叫ばれており、IT系人材への注目度が高くなっています。しかし、IT系人材の育成を支えるためには、足元のものづくりの力も求められています。よって、昔ながらの製造系のものづくりが今も変わらず必要とされているのです。
ものづくりの仕事に就く6つのメリット
ものづくりの仕事は未経験から挑戦できる職種も一定数あり、段階を踏んで専門的な技術を習得できます。さらに、手に職をつけることで人材として市場価値を高められるため、雇用が安定しやすいでしょう。ここでは、ものづくりの仕事に就く6つのメリットを紹介します。
ものづくりの仕事に就くメリット
- 手に職がつくためどこでも働ける
- 学歴・経歴不問の求人が多い
- 雇用が安定していて仕事がなくなる可能性が低い
- ニーズが高く社会貢献できる
- 仕事の成果が形として見えるため達成感を得やすい
- 国からの支援がある
1.学歴・経歴不問の求人が多い
ものづくりの仕事では、学歴や経歴は問わない求人も一定数あるようです。理由としては、ものづくりの仕事は学歴よりも専門知識や技術が重視されやすく、実力主義の世界であることが考えられます。
また、後継者不足から学歴・経歴に関係なく応募できるよう、積極的に未経験者歓迎の求人募集を行っている企業もあるようです。
研修などの教育体制に力を入れている業界も多いため、経験を問わずチャレンジできるでしょう。ただし、選ぶ職種によっては、大学や専門学校、独学などで知識や技術を身につけたり、下積みで経験を積んだりする必要があることも。求人を探す際は、応募条件や資格の欄をしっかりと確認しましょう。
未経験から挑戦する場合も段階を踏んで成長できる
ものづくりの仕事は、段階を踏んでスキルを習得できる環境が整っている傾向にあります。
たとえば、自動車組立の仕事の場合、いきなり難しい作業や管理者としての業務を任されることはありません。自動車に関する研修や先輩のもとについて仕事を覚えるOJT制度を活用しながら、少しずつ業務に慣れていけます。先輩や上司が仕事の習熟度や適性などを見極めたうえで、新たな業務やポジションを任されることが一般的なため、無理なく成長できるでしょう。
2.手に職がつくためどこでも働ける
ものづくりの仕事は専門知識や高い技術が求められるので、手に職をつけられるのがメリットです。研修制度が充実していたり資格取得をサポートしていたりする企業も多く、努力を続けると徐々にスキルが身についていきます。高度な技術を習得すれば収入アップも目指せるうえ、転職や独立の道もひらけるでしょう。
また、手に職があるとブランクを経ても就職しやすく、離職後の再就職や定年後の再雇用にも有利に働く可能性があります。
スキルを身につけることでキャリアの選択肢が広がる
仕事をしながらスキルや資格を身につけられるものづくりの仕事は、キャリアの選択肢が広がりやすいのも魅力です。たとえば、製造ラインでのオペレーターや製品の組立担当者、検査作業員などは、最初は現場で実践的な知識・スキルを身につけます。
しかし、一度スキルを習得すれば、部下や機械の管理をする「マネージャー」や専門的なスキルや知識を極める「スペシャリスト」、幅広いスキルをもち多岐にわたる業務に対応する「ゼネラリスト」など複数の選択肢からキャリアを選べます。そのため、自身の適性やキャリアビジョンを考慮して働き方を選択できるでしょう。
ハタラクティブキャリアアドバイザー
後藤祐介からのアドバイス
3.雇用や収入が安定していて仕事がなくなる可能性が低い
ものづくりの仕事は社会的な需要から雇用や収入が安定しており、職を失う可能性が低いこともメリットの一つといえます。建築や土木、製造業など人々の生活に密接に関わる仕事が多く、市場が安定しているのが特徴です。
また、近年発達しているAIは一定数の職種を代行できるといわれているものの、ものづくりの仕事がAIによってなくなる可能性は低いといわれています。AIは決まった動きを正確に行うのは得意である一方で、新しいアイディアを生み出すことや、職人技といわれるような細かい作業をするのは難しいからです。社会情勢や新たな技術の発展で仕事内容が変化することはあっても、仕事がなくなる可能性は低いといえるでしょう。
ものづくりの仕事の平均年収
ここでは、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を参考に、2024年度のものづくりの仕事に当てはまる職種の収入から想定される年収を計算したものをご紹介します。また、データから計算した全職種の平均値もあわせてご紹介します。
| 職業区分 | きまって支給する
現金給与額(A) | 年間賞与その他
特別給与額(B) | 想定される年収額
(A×12+B) |
|---|
| 専門的・技術的職業従事者 | 40万3,100円 | 114万7,000円 | 598万4,200円 |
|---|
| 生産工程従事者 | 31万4,000円 | 78万1,600円 | 454万9,600円 |
|---|
| 建設・採掘従事者 | 34万3,300円 | 72万500円 | 484万100円 |
|---|
| 全職種平均 | 34万2,000円 | 80万9,200円 | 491万4,300円 |
|---|
上記より、ものづくりの仕事の年収はおおむね450~600万円ほどであると考えられます。なかでも、専門的・技術的職業従事者は給与・ボーナスともに高めといえるでしょう。
ただし、上記は統計をもとに計算したものであり、すべてのものづくりの仕事に当てはまるとは限りません。就職先を探す際は、一つひとつの求人の給与額や残業代の扱い、ボーナスの支給頻度や支給額の計算方法といった情報を確認することが重要です。
4.ニーズが高く社会貢献できる
ものづくりの仕事では、高速道路や商業施設・インターネットや自動車など、生活に欠かせない建造物や製品に携わります。ときには自分の関与した仕事により、生活の質や社会の利便性が大きく向上することもあるでしょう。
「誰かの役に立ちたい」という思いが強い方にとっては、「自分の仕事が人々の生活を支えている」と実感できる職業といえます。
5.仕事の成果が形として見えるため達成感を得やすい
ものづくりの仕事は、自分の作ったものが形として残りやすく、それに対する反応も得られやすいので、達成感を得られるでしょう。人々のポジティブな反応は、やりがいやスキルアップへの意欲にもつながります。
「どのようなものを実現すれば消費者が喜ぶのか」「どのような改善が求められるのか」を日々考えながら作業に反映できれば作品の質や評価につながるため、長期的な成長や活躍が見込める点も魅力です。
6.国からの支援がある
このように、ものづくりの仕事は国の支援により、大事な産業として守られているのがメリットといえるでしょう。
ものづくりの仕事に就くデメリット
ものづくりの仕事は長期間にわたってスキルを身につけることを前提としているため、どうしても下積み期間が長くなります。また、社会動向の影響を受けやすいのもデメリットといえるでしょう。
下積み期間が長い
ものづくりの仕事のデメリットとして、「下積み期間の長さ」が挙げられるでしょう。ものづくりの現場で一人前として認められるには、一定期間の経験を積む必要があります。
しかし、何をもって「一人前」とするか明確な基準が設けられていません。職種によっては年単位での修行や下積みが必要な場合もあり、「憧れた仕事に挑戦させてもらえない」「ずっと同じことをしている」といった不満やモチベーション低下を招く恐れもあるでしょう。
とはいえ、長い下積み期間を経て習得できるスキルは一生使えるもの。自身の市場価値を高めることにもつながるため、将来的な安定が期待できるでしょう。
社会動向に経営状況を左右されやすい
ものづくりの仕事は、社会動向の影響を受けやすいのが特徴であり、企業の経営状況を左右することも。感染症の流行や災害などで工場が稼働できなくなったり、紛争の影響で部材の輸送ができなくなったりすると、売上の減少につながります。自分や企業の努力では解決できない問題で経営状態が上下しやすい点は、デメリットといえるでしょう。
一方で、景気が良くなると、急激に需要が伸びて大きく売上を伸ばすことも。ものづくりの仕事へ就職・転職を検討する際は、社会情勢や業界の動向にも注目することをおすすめします。
緊張感のあるなかで仕事を進める場面もある
ものづくりの仕事は成果物のクオリティが重要視されるため、緊張感のあるなかで作業を進める場面が生じやすいでしょう。職種によっては危険と隣り合わせの業務もあるため、自分のペースで仕事を進めるのが難しい場合もあります。
職種によって携わる業務の内容は異なるため、仕事選びの際は「自分が働きやすい環境であるか」を確認することが大事です。
ものづくりの仕事に向いている人の特徴
ものづくりの仕事は、いずれの分野も忍耐強さやものを作ることに対する熱意が求められます。また、手先の器用さや想像力の豊かさも働くうえで役立つ強みといえるでしょう。
ものづくりの仕事に向いている人の特徴
- ものを作るのが好きな人
- コツコツと努力を積み重ねることが好きな人
- 想像力が豊かな人
- 細かい作業が得意な人
ものを作るのが好きな人
ものづくりの仕事には「制作が好き」「自分の手で作るのが楽しい」という情熱が欠かせません。
「ものを作るのが好き」という強い気持ちがあるからこそ、長い下積みやスキル習得までの道のりに耐えられるでしょう。「さらに良いものを作ろう」と技術を磨く原動力にもなり得ます。
手先が器用で細かい作業が得意な人
ものづくりの仕事には、手先の器用さや細かい作業への適性も求められます。職人系や製造系のものづくりの仕事では、手先を使う細かい作業が必要なためです。
ただし、検査やライン生産など、器用でなくてもできる仕事はあります。仕事によっては几帳面さや正確性のほうが重視されることもあるので、不器用だからと諦めず自分に向いている職種を探してみましょう。
コツコツと努力を積み重ねることが好きな人
コツコツと努力を積み重ねられる人も、ものづくりの仕事に向いている可能性があります。
ものづくりの仕事では、小さい部品の組立や製品の検査、細かいチェックなどコツコツと行う作業が多いためです。なかには同じ作業を繰り返す場合もあるため、「変化が少ない仕事も前向きに取り組める」といった強みがあると仕事に活かせるでしょう。
想像力が豊かな人
想像力の豊かさも、ものづくりの仕事の適性といえます。特に、新製品の開発や生産工程の改善といった想像力を必要とするクリエイティブな作業が求められる仕事では、想像力や発想力が活かせるでしょう。
ときには固定観念を取り払い、今までにない発想が求められる場合も。そのような仕事を面白いと思える人は、クリエイティブ系のものづくりに向いている可能性があります。
ものづくりの仕事にはどのような人が向いていますか?
自分のアイデアが形になることが嬉しい人に向いているといえます
「技術を磨き、自分の手で目に見えるものを作りたい」「チームの一員として、自分のポジションで力を発揮したい」という方は、ものづくりの仕事に向いているでしょう。興味のある分野で「好きなものを作りたい」という思いがある方は、興味の深い企業や業界での挑戦を検討してみてください。
また、アイデアを具体化することに関心がある方にも、ものづくりは適している可能性があります。この世にあるすべての製品は、誰かの頭のなかにあるアイデアやイメージを形にしたものといえるでしょう。たとえば、誰もが知る著名なスマートフォンも、何気なく使っているデスクやチェアも、企画者や設計者が原型を考案し製造現場が形にしたものです。
手を動かしたい方も、頭を動かしたい方も、ものづくりの世界ではともに活躍しています。DIYや料理、掃除など日常において、創意工夫しながらアイデアを形にすることが好きであれば、ものづくりの仕事に向いている可能性があるでしょう。
ものづくりの仕事に役立つ講習や資格
ものづくりの仕事は無資格の方も挑戦できますが、専門的な知識があると担当業務の幅を広げられるでしょう。ここでは、ものづくりの仕事に役立つ講習や資格を紹介します。
特別教育
講習の内容は法令によって定められており、修了することで小型ボイラーの取り扱いや最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転など、一定レベルの危険が伴う業務に携われるようになります。
技能講習
技能講習とは、特別教育よりもさらに危険度の高い業務に就く際に受ける必要がある講習のことです。厚生労働省が運営する「職場のあんぜんサイト 技能講習」によると、技能講習は都道府県労働局長に登録された機関が実施し、受講後は修了試験を受ける必要があります。
技能講習では、ガス溶接やフォークリフト、高所作業車などの技能について習得することが可能です。
国家資格
国家資格は、法律で指定された機関が実施する試験(国家試験)に合格、または国が認定した学校で要件を満たすことで取得が可能です。難易度が高い内容も含まれるものの、取得後はキャリアアップにつながる可能性があるでしょう。
以下に、ものづくりの仕事に役立つ国家資格の例をまとめました。
危険物取扱者
「危険物取扱者」は、ガソリンやアルコールといった、取り扱いに注意が必要な液体・個体・物質を業務で扱うために必要な国家資格です。甲種・乙種・丙種の3段階があり、最上段の甲種を取得すればすべての危険物を扱えます。
フォークリフト運転技能士
フォークリフト運転技能士は、工場や倉庫で荷物の積み下ろしや運搬に使われる車両を運転するために必要な国家資格です。重い荷物をパレットに積んで運ぶ際に使用します。
フォークリフト運転技能士には2種類あり、「1トン以上」は技能講習、「1トン未満」は特別教育で取得可能です。ものづくりの仕事のなかでも、主に製造系の工場に就職した際、この資格が必要になる可能性があります。
発破技士免許
発破技士免許とは、ダイナマイトを使って建物や岩石を崩す際に必須の国家資格です。場所の選定や火薬の量などを判断し、安全に発破を行うための専門知識を習得できます。
受験資格として6ヶ月以上の補助作業の経験、または発破実技講習の受講が必要です。建設系のものづくりの仕事で役立つ資格の一つといえます。
クレーン・デリック運転士免許
クレーン・デリック運転士免許は、荷物を持ち上げるクレーンやデリックといった機械の操縦に必要な免許です。つりあげ荷重が5トン以上のクレーンまたはデリックの場合は免許(国家資格)が必要ですが、1トン未満であれば特別教育を修了することで資格が得られます。
クレーンは工場や倉庫、建設現場などで使われるため、資格があれば就職先の選択肢が増やせるでしょう。
ウェブデザイン技能検定
ウェブデザインに関連する唯一の国家検定が、ウェブデザイン技能検定です。1級・2級・3級があり、誰でも受験できるのは3級のみ。2級は2年以上、1級は7年以上の実務経験が必要となります。
いずれの試験も学科と実技があり、さらに1級ではペーパー実技試験もあるため難易度は高めです。
デザイン系の求人では、「未経験可」とされているものでもデザインの基礎的な知識やデザイン制作ソフトのスキルが求められることも。ウェブデザイン技能検定に合格すれば専門知識・スキルがあるとアピールでき、評価につながる可能性があります。
クリエイティブ系のものづくりの仕事に興味がある方は、3級から挑戦してみるのも手です。
未経験から自分に合ったものづくりの仕事を探す方法
未経験から自分に合ったものづくりの仕事に就くためには、ものづくりに興味をもった理由や自分の強みを理解したうえで、適性に合う仕事を幅広く探すことが大切です。ここでは、ものづくりの仕事を未経験から目指す方法を紹介するので、就職・転職を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
1.ものづくりに興味をもった理由を明確にする
まずは、ものづくりに興味をもった理由を明確にしましょう。「なんとなくカッコ良さそう」「楽しそう」という漠然とした理由だけでは、就職後に目標が定まらなかったりミスマッチを感じたりするリスクがあるためです。
理由を明確にするためには、「なぜ魅力を感じたのか」「仕事のどの部分が楽しそうと思ったのか」というように、自分の考えや気持ちに対して「なぜ」を繰り返して深堀りしていく方法がおすすめ。そうすることで、「人々の生活を支える姿に刺激を受けたから」「自分の手先の器用さを活かせそうだから」のような具体的な理由が見えてきます。
ものづくりの仕事に興味をもった理由が明らかになれば、ものづくりの仕事で目指すべき目標や姿が明確になるでしょう。さらに、就職・転職活動で志望動機を考える際にも役立ちます。志望動機の作り方について、詳しくは「志望動機の作り方を解説!好印象な回答をするポイントとは」のコラムをご覧ください。
2.自分の強みや得意分野を把握する
ものづくりの仕事を目指す理由が明確になったら、自分の強みや得意分野を改めて振り返ってみることが大切です。いくら憧れている仕事であっても、強みや適性に合っていなければ入社後に馴染めなかったり、仕事を覚えるのが苦痛に感じてしまったりする可能性もあるでしょう。
一方、自分の適性や強みに合った仕事を選べば、仕事を覚えるスピードが早かったり、成果が出やすかったりするもの。そのため、自然とモチベーションアップにもつながる効果が期待できます。
たとえば、「精密機器や細かい部品の扱いが得意」であれば自動車組立、「豊かな想像力を活かして世の中に楽しいものを発信したい」ならゲームクリエーターなど、適性を軸に仕事を探してみましょう。
3.業界の情報や業務内容を調べる
自分に合ったものづくりの仕事に就くには、業界や企業の情報について丁寧にリサーチする必要があります。同じ業界でも、企業ごとに強みや特徴、社内の雰囲気などは異なるもの。企業理念や社風といった方向性が合わないと、入社後にミスマッチを感じる原因になりかねません。
また、業界や企業について詳しく調べることで、企業の求める人物像が把握できたり、選考で意欲をアピールできたりするなどのメリットもあります。
業界研究や企業研究では、業界に関連する雑誌やニュースをチェックしたり、企業のWebサイトやリクルートサイトを調べたりするのがおすすめです。雑誌やニュースでは業界全体の動向や経済状況が知れるほか、Webサイトでは企業理念や業績、仕事内容などが分かります。
また、企業の説明会や見学会に足を運んでみると、実際の仕事現場や職場の雰囲気を肌で感じられるでしょう。実際に働いている姿をイメージしやすくなるため、あわせて活用してみましょう。
無理せず長く続けられる仕事かどうかに着目してみよう
仕事を選ぶときは、「定年まで長く続けられそうか」という点も考慮することが重要です。ものづくりの仕事は、基本的に一つの業務に長く携わります。下積み期間も長いため、「いろいろな仕事に挑戦したい」「一つのことを極めるのが苦手」という場合、ミスマッチを感じて早期退職につながる恐れがあるでしょう。
「入社前の段階では適性が分からない」という場合は、紹介予定派遣やインターンの制度を活用したり、アルバイトから正社員登用を目指したりするのがおすすめです。働きながら適性を確認できるため、「失敗したくない」という方も安心して仕事を選べるでしょう。
4.自分なりのキャリアプランを立てる
挑戦してみたい仕事をいくつかピックアップできたら、自分なりのキャリアプランを立ててみてください。その仕事でどのようなスキルや経験を得たいのか、将来は現場で働きたいのかマネジメントに携わりたいのかなどを考え、将来なりたい姿を具体的に想像してみましょう。
たとえば、同じ大工の仕事でも「入職して実績を積み、二級建築士の資格を取って独立したい」「勤め先で親方になって、いずれは後進を指導したい」など、さまざまなプランが立てられます。キャリアプランを立てれば、そこから逆算して未経験からスキルを積むための道筋を考えることも可能なため、仕事探しの方向性が明確になるでしょう。
5.未経験歓迎の傾向にある職種を中心に探す
就職活動を有利に進めるためにも、「未経験歓迎」「経歴不問」などの条件の求人を中心に応募しましょう。先述したように、ものづくりの仕事には未経験からはじめられるものも多い一方で、建築士やデザイナーなど就職活動で知識や技術を問われる職業もあります。求人情報を確認する際は、企業側が求める人材の条件に注目して、「自分の経歴やスキルでも就業可能か」を把握しておきましょう。
ただし、求人サイトは量が多いぶん、自分に合った求人を見つけるのが難しくなりやすいもの。ハローワークや就職・転職エージェントなどの支援機関なら、スタッフやアドバイザーに相談しながら求人を探せます。
特にエージェントでは、丁寧なヒアリングを行ったうえで求人を厳選して紹介してくれるため、未経験での仕事探しに不安がある方におすすめです。
労働条件や働き方も考慮することが大切
ものづくりの仕事を長く続けるには、労働条件や働き方といった仕事内容以外の部分もしっかりチェックしておく必要があります。「家から職場まで1時間半掛かってきつい」「夜は早く寝たいのに夜勤がある」など働き方が自分に合っていないと、仕事が充実していても疲労やストレスの原因になりやすいためです。
求人票では、仕事内容のほかに以下の項目もチェックしておくと安心でしょう。
- ・勤務地
- ・職場環境
- ・就業時間や勤務形態(日勤のみ、夜勤ありなど)
- ・休日数や休暇制度
- ・残業の有無や平均の残業時間
- ・給与
- ・各種手当や賞与の有無
- ・教育制度や研修の有無
ただし、上記のすべての条件を満たす求人を探すのは難しいもの。優先順位が高いものを3~4つまで選び、どうしても譲れない条件を満たしている仕事はないか探してみましょう。
未経験からものづくりの仕事に就くための3つのポイント
未経験からものづくりの仕事を目指す場合は、以下のポイントを押さえて仕事探しをしてみてください。
【1】長期的な視点を大切に
ものづくりの仕事は専門的な知識や技術が求められるため、日々学び続ける必要があります。まずは、その仕事での「10年後」をイメージしてみてください。活躍している自分を想像し、着実に腕を磨いていく長期的な視点をもちながらものづくりの仕事を探すことをおすすめします。
【2】ロールモデルを見つけよう
ものづくりで活躍している人物をモデルに、検討する方法もあります。確かな知見が求められるものづくりの現場では、長く活躍している社員も多いようです。ホームページに、先輩の働き方や日常の様子を紹介している企業もあります。自分が「将来こうなりたい」という理想の社員を見つけましょう。
【3】プロのアドバイスを力に
転職エージェントやキャリアコンサルタントなど、キャリアのプロフェッショナルのアドバイスも役立ちます。ものづくりの仕事は多種多様で、あなたがまだ知らない企業や仕事が数多くあることでしょう。プロに相談することで得られる情報や気づきが増え、ものづくりの世界で活躍できるチャンスが広がります。
ものづくりの仕事探しは周囲や支援機関の力を借りるのがおすすめ
ものづくりの仕事のなかには未経験から目指せるものもあり、経歴に関わらず挑戦することは可能です。また、入職後に経験を積むことで一生もののスキルを身につけられるほか、社会や人々の生活に貢献できる魅力的な仕事といえます。
しかし、なかには「就職・転職活動の方法が分からず不安…」「未経験からできるといっても、自分にできるだろうか」などの不安や疑問を抱えている方もいるかもしれません。そのような場合は、就職・転職エージェントに相談してみるのがおすすめです。
就職・転職エージェントでは、一人ひとりに担当アドバイザーがつき、仕事探しから就職までを一貫してサポートしてくれます。自己分析に関するアドバイスや希望条件について面談で話し合ったうえで、あなたに合う求人を紹介してくれるでしょう。
エージェントの種類によって強みは異なるため、未経験からものづくりの仕事に挑戦したい方は、「未経験者歓迎」の求人を豊富に扱っている就職・転職エージェントを選ぶのがおすすめです。
「ものづくりの仕事に挑戦してみたい」「未経験の職種に転職したい」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブをご利用ください。ハタラクティブは、20代を中心とした若年層に特化したサービスを行っています。業界・職種を問わず、ポテンシャルや人柄を重視した企業の求人が豊富で、製造業や建築業、IT関連職をはじめとするものづくりの仕事も多く取り扱っています。
専任のキャリアアドバイザーが丁寧なカウンセリングでお悩みや希望を伺い、あなたの適性や強みに合った求人をご紹介。また、面接対策や応募書類の添削で選考通過率アップを目指せます。サービスはすべて無料のため、お気軽にご相談ください。
ものづくりの仕事に関するQ&A
ここでは、ものづくりの仕事に関する疑問やお悩みにQ&A形式でお答えします。「面白い仕事が知りたい」「求人が見つからない」などのお悩みにも回答しているので、ぜひ参考にしてみてください。
「変わった仕事」の定義は人により異なるものの、発想力や想像力を活かせるという意味ではデザイナーや建築士、CG制作の仕事などが挙げられるでしょう。また、「珍しい仕事39選!高収入&正社員として働ける職種や求人の探し方も紹介!」で紹介しているような切手デザイナーや動画クリエイターなどは、一般的な仕事とは業務内容が異なったり広く認知されていなかったりする「変わった仕事」といえます。
このコラムの「ものづくりの仕事の種類一覧」ではものづくりの仕事を多く紹介しているので、自分にとって面白いと感じられる仕事を探してみてください。
自己分析を行い仕事に求める条件を明確にすることで、自分に合う求人を探しやすくなります。一口に「ものづくりの仕事」といっても業界・職種は多岐にわたるため、「仕事内容」「給料」「職場環境」などさまざまな観点からマッチする求人を見極めるのが大切です。
1人での求人探しに自信がない場合は、就職支援サービスを活用する方法もあります。若手を対象とした就職支援サービスは「20代の就職支援には何がある?サービスや制度を詳しく解説!」のコラムで紹介しているので、ご覧ください。
企業の経営状況や業界の市場規模に注目して求人を選ぶことが大切です。ものづくりに携わる仕事は人々からの需要があるものの、社会の動きに経営が左右されやすい傾向があります。業界の動向に敏感になり情報収集することで、高収入の仕事を見極めやすくなるでしょう。
高収入の仕事に就くための仕事選びの基準は、「儲かる仕事の共通点は?年収アップを狙うならどの職業が良い?」のコラムで紹介しているのでご覧ください。
ものづくりの仕事に就きたくても求人が見つからないときは、就職・転職支援サービスへ相談するのがおすすめです。就職・転職支援サービスではキャリアアドバイザーが転職の悩みや希望条件を聞いたうえで、自分に合った求人を紹介してくれます。
ハタラクティブではスキルや経験にかかわらず挑戦できる求人をご紹介しているので、ぜひご相談ください。