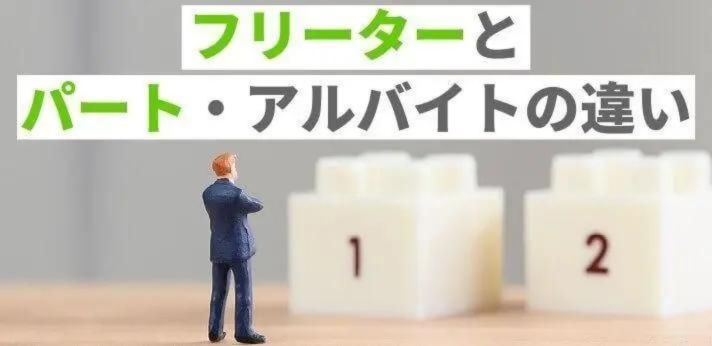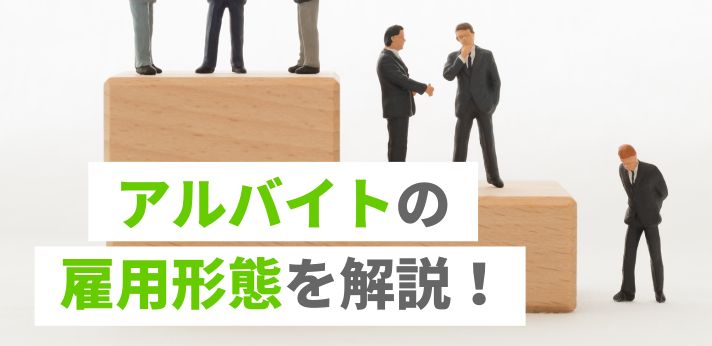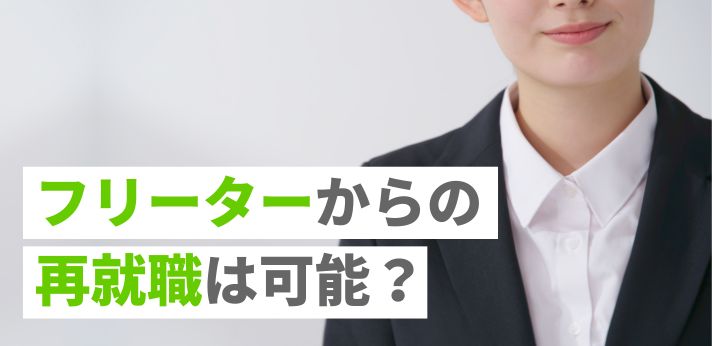フリーターとは?さまざまな働き方との比較や正社員就職のコツフリーターとは?さまざまな働き方との比較や正社員就職のコツ
更新日
公開日
フリーターとは、主にアルバイトで生計を立てている若年層を指す
「フリーターとはどんな働き方?」と気になる方もいるでしょう。フリーターとは主にアルバイトで生計を立てている若年層を指す言葉です。フリーターは自由度の高い働き方を実現しやすい一方で、年齢を重ねると安定性の面でデメリットが生じる可能性もあります。
このコラムでは、フリーターの定義やほかの働き方との違い、正社員就職のコツなどをご紹介。さまざまな働き方について知り、今後の働き方について考えるときの参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
フリーターとは
フリーターは、15~34 歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、以下の者の合計としている。
- ・雇用者のうち「パート・アルバイト」の者
- ・完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
- ・非労働力人口で、家事も通学もしていない「その他」の者のうち、就業内定しておらず、希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」の者
上記によると、働いていなくても、場合によってはフリーターと見なされることもあるようです。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
フリーターとほかの働き方との違い
この項では、フリーターとパート・アルバイト、派遣社員の違いについて説明します。以下の表でそれぞれの違いをまとめているほか、各見出しでも紹介しているので参考にしてみてください。
| 雇用形態や現在の状況 | 定義 | 雇用契約期間 | 特徴 |
|---|
| フリーター | ・15~34歳で男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者のうち、パートやアルバイトとして働いている人
・探している仕事や希望している仕事の形態がパートやアルバイトの人 | 有期 | ・働く時間や日数を選びやすい
・働いたぶんだけ稼げる時給制が一般的 |
| パート・アルバイト | 明確な定義はないものの、学業や本業がありパートやアルバイトとして一時的に働いている人 | 有期 | ・学業や本業がメイン
・勤務日数や勤務時間が限られやすく、週1~2日、3時間ほどの短時間で働く場合もある |
| 派遣社員 | 人材派遣会社と労働契約を結んだうえで、派遣先の企業で働く人 | 有期 | ・契約期間は派遣先によって異なり、数ヶ月から3年まで幅広い
・さまざまな職場を経験できる |
| 既卒 | 大学卒業概ね3年以内で、卒業後正社員就職を一度もしていない人 | ー | ・大学卒業後、フリーターやアルバイトとして働いている場合も既卒に含まれる |
| 第二新卒 | 新卒入社後概ね3年以内で、転職を考えている人やしようとしている人 | ー | ・大学卒業後に就職した会社から、3年以内での転職を考えている場合を指す |
| ニート | 15〜34歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない人 | ー | ・現在働いておらず、就業意欲もない場合を指す |
フリーターとパート・アルバイトの違い
フリーターとパート・アルバイトに法律上の違いはありません。とはいえ、アルバイト・パートは「学生や本業がある人」、フリーターは「主にアルバイトで生計を立てている若年層」を指すことが一般的なようです。
就職・転職市場では、世間的なイメージをもとに、採用区分や求人などで使い分けられることがあります。若い人材を確保したいと考える企業は、求人に「フリーター歓迎」「フリーター積極採用中」などの記載をする傾向にあるようです。
35歳以上は「高齢フリーター」と呼ばれることも
35歳以上のフリーターを、便宜上「高齢フリーター」と呼ぶこともあるようです。また、資料によっては「中年フリーター」と呼ばれることもあります。
先述したフリーターの定義には35歳以上は含まれていないものの、年齢に関わらずアルバイトで生計を立てている方もいるでしょう。そういった方を表す際に、「高齢フリーター」という言葉が使われています。
アルバイトをしている高校生や大学生はフリーターに含まれる?
アルバイトをしている高校生や大学生は、フリーターには含まれません。先述のとおり、フリーターは「15~34歳の卒業者」を指す言葉で、学業が本業である高校生や大学生は除外されます。
アルバイトとして雇われていても、それが本業でなかったり、家庭に入っていたりする場合は、一般的にフリーターとは見なされないようです。フリーターの定義については、「
【フリーター必見】就職して正社員になる方法・メリット・おすすめの職種を紹介!」で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
フリーターと派遣社員の違い
フリーターと派遣社員の違いは、雇用契約を結ぶ相手です。フリーターの場合は勤務先の企業と雇用契約を結びます。対して派遣社員の場合は、派遣元企業と雇用契約を結ぶのが特徴です。
フリーターと派遣社員の違いについては、「フリーターと派遣社員の違いとは?正社員をおすすめする理由も解説」で詳しく解説しているので、あわせてご一読ください。
フリーターと既卒や第二新卒の違い
既卒・第二新卒も、フリーターとは異なる意味をもつ言葉です。
既卒とは、「大学を卒業後概ね3年以内で、一度も就職をしたことがない人」を指します。大学卒業後に就職せずアルバイトで生計を立てている場合、就職市場では卒業後3年以内だと既卒、3年以上経つとフリーターと見なされるでしょう。
一方、第二新卒とは、「新卒入社後概ね3年以内で、転職を考えている・しようとしている人」を指します。第二新卒は新卒で入社した会社で正社員として働いている人を指すため、フリーターとは雇用形態の部分で違いがあるでしょう。
既卒と第二新卒については、「既卒と第二新卒の違いは?どちらが有利?定義やメリット・デメリットを解説」のコラムで詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
フリーターとニートの違い
フリーターとニートの大きな違いは、「仕事や就業意欲の有無」です。厚生労働省の「よくあるご質問について」によると、「15〜34歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない」人をニートとして定義しています。先述したように、フリーターの定義には「アルバイトやパートとして仕事を探している人」も含まれているため、この点がフリーターとニートの違いといえるでしょう。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
フリーターと正社員の違い
フリーターと正社員には、雇用期間や給与の支払われ方といった働き方の点に大きな違いがあります。ここでは、それぞれの違いを詳しく解説しているので確認してみましょう。
雇用契約期間
フリーターと正社員の違いとして、雇用契約期間の有無が挙げられます。フリーターは雇用契約期間が定められている「有期雇用契約」であるのに対して、正社員は雇用契約期間に定めがない「無期雇用契約」が基本です。正社員は長期的に安定して働きやすいのに対し、フリーターの場合は雇用元の方針や経営状況で契約終了となる恐れがあります。
給与形態
フリーターと正社員のもう一つの違いは、「給与形態」です。フリーターの給与形態は時給制や日給制が一般的で、勤務日数や時間によって1ヶ月あたりにもらえる給与が変動します。
一方、正社員の場合は基本的に月給制で、毎月もらえる金額が決まっているのが特徴です。そのため、祝祭日があっても1ヶ月でもらえる給与が大きく変わることはなく、安定した収入を得やすいでしょう。
フリーターの実情
ここでは、人口や年齢階級別の割合、支払い義務のある税金など、フリーターの実情をまとめました。「フリーターってどのくらいいるの?」「フリーターは税金を支払う必要がある?」と疑問をお持ちの方は、参考にしてみてください。
フリーターの人口は?
フリーターの人口は、2013年の182万人をピークに、2014年以降から減少を続けています。上記のデータをもとに算出すると、フリーターの人口は2014年から2023年にかけて約44万人減少していることが分かりました。2023年には前年比で約2万人増加しているものの、全体的に見ると減少傾向であるといえます。
近年フリーターが減っている背景には、少子高齢化や労働人口の減少、またそれによって企業の人手不足が顕著となり、正社員の採用のハードルが下がったことなどが挙げられるでしょう。
フリーターの年齢で多いのは?
同調査のデータをもとに、年齢階級別のフリーターの割合を以下にまとめました。
※男女計
| 年 | 15~24歳 | 25~34歳 |
|---|
| 2015 | 70万人 | 96万人 |
| 2016 | 63万人 | 91万人 |
| 2017 | 64万人 | 88万人 |
| 2018 | 61万人 | 83万人 |
| 2019 | 59万人 | 80万人 |
| 2020 | 59万人 | 78万人 |
| 2021 | 59万人 | 79万人 |
| 2022 | 56万人 | 76万人 |
| 2023 | 54万人 | 80万人 |
上記より、フリーターの方が多いのはいずれも25~34歳の年齢層であると分かりました。
ただし、15〜24歳のフリーター人口は2015年で70万人であるのに対し、2023年では54万人まで減少。また、25〜34歳のフリーター人口は2015年に96万人だったものの、2023年には80万人まで減っています。
フリーターの手取り月収
上記より、フリーターの40%近くが手取り月収「10~15万円未満」でした。「15~20万円未満」も合わせると約60%にのぼり、フリーターの過半数の手取り額が10万円台であることが分かります。
フリーターが支払う税金とは?
フリーターの場合も、所得税や住民税などの支払い義務があります。「所得税」は、毎年1月1日から12月31日までの間に、103万以上の所得があった場合に課せられる税金です。基本的に給与から天引きされますが、副業やダブルワークをして別途20万以上の収入がある場合、または勤務先で年末調整できない場合は、確定申告をして正確な所得を申告しなくてはいけません。
「住民税」は、居住している都道府県・市区町村に支払う税金で、年収が100万円を超えたら払うのが一般的です。ただし、支払い義務が生じる年収のラインや算出に用いられる税率には地域によって異なるため、注意しましょう。
住民税も給与から天引きされることが多いものの、そうでない場合は自治体から自宅に送付される納付書を使って、自分で振り込む必要があります。納付期限を過ぎると督促状が届く恐れもあるので、早めに振り込みましょう。
所得税や住民税については、「フリーターが払う税金とは?払い方や計算シミュレーションも紹介」のコラムで解説しています。所得税と住民税の計算方法や年収ごとのシミュレーションも行っているので、ぜひ参考にしてみてください。
フリーターとして働く3つのメリット
フリーターとして働くメリットとして、「働き方の自由度が高い」「仕事に対する責任が重くない」「休みを自由に取りやすい」の3つが挙げられます。
それぞれ以下で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
1.働き方の自由度が高い
フリーターは正社員に比べて自由度が高く、柔軟に働きやすい可能性があります。ハタラクティブの独自調査「若者しごと白書2025 1-2」によると、フリーターの平均労働日数や時間は以下の通りです。
上記より、「週3~4日」「4~6時間未満」など、フルタイムで働いていない方も一定数いることが分かります。アルバイトやパートはシフト制が一般的で、勤務日数や時間などは就業規定に合わせて自分で決めやすいもの。月収を上げたい場合はシフトを増やしたり、忙しいときは減らしたりして調整しやすく、自分にとって丁度良い働き方を実現しやすいのはメリットといえます。
また、職場によってはアルバイトやパートの掛け持ちも可能です。空いている時間をうまく使うことで効率的に収入が増やせるのも、フリーターとして働くメリットの一つでしょう。
2.仕事に対する責任が重くない
フリーターで働くメリットとして、正社員と比べて仕事に対する責任が重くない点が挙げられます。雇用期間に定めのあるアルバイトやパートは、短期間・短時間での就労を前提としているのが一般的。そのぶん責任の重い仕事を任されることは少なく、業務内容が限られています。
また、最終責任者は正社員となるので、仕事のプレッシャーや責任といった負担を抑えて働けるでしょう。
ただし、企業の経営や損失に関わるミスをしてしまった場合は、雇用形態に関わらず処分の対象になることも。勤務形態に関わらず、誠意をもって仕事に取り組むことが大切です。
3.休みを自由に取りやすい
フリーターは、正社員と比較して休みを取りやすいこともメリットの一つ。週5日・8時間労働であることがほとんどの正社員とは異なり、アルバイトやパートは希望のシフトに基づいて出勤日が決められます。そのため、「この週は月曜日を休みにしたい」「この週は3連休が欲しい」といった希望が通りやすいのが強みです。また、従業員数や仕事の状況によっては、シフトの増減や急な休みなど融通が利くこともあるでしょう。
フリーターとして働く7つのデメリット
フリーターのまま年齢を重ねると、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。以下でデメリットを7つ挙げて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
フリーターのまま年齢を重ねるデメリット
- 有期雇用のため解雇のリスクがある
- 非正規雇用のため社会的信用を得にくい
- 正社員と比べて専門的なスキルが身につきにくい
- 正社員の同世代と比べて収入に差が生じやすい
- 安定した収入を得にくいので貯蓄をしづらい可能性がある
- 年齢を重ねるほど就職が難しくなる傾向にある
1.有期雇用のため解雇のリスクがある
フリーターとして働く場合、有期雇用のため解雇のリスクがあり、雇用が不安定なことがデメリットの一つです。「フリーターと正社員の違い」で述べたとおり、フリーターは雇用契約期間が定められており、契約満了の際に更新してもらえない恐れがあります。
また、雇用元の方針や業績悪化で人材削減を行う場合、正社員よりもフリーターのような非正規雇用の従業員から解雇になるリスクがあるでしょう。
2.非正規雇用のため社会的信用を得にくい
フリーターとして働くデメリットとして、社会的信用を得にくいことも挙げられます。非正規雇用契約であることから「収入が安定していない」「解雇のリスクがある」と見なされ、社会的信用度が低く評価されやすいのが実情です。社会的信用度が低いままだと、賃貸契約やクレジットカードなどの審査に通りにくくなる恐れがあります。
3.正社員と比べて専門的なスキルが身につきにくい
フリーターは、正社員と比べて専門的なスキルが身につきにくいこともデメリットの一つです。先述したとおり、アルバイトやパートは短時間での就労を前提にしているため、スキルの身につくような責任の重い仕事は任されにくい傾向にあります。研修や教育の機会も正社員と比べると少なく、長く働いてもスキルアップに直結するような経験を積めない恐れがあるでしょう。
一方、正社員は無期雇用のため、責任ある仕事やプロジェクトを任されやすいといえます。また、独自のスキルアップ研修や勉強会を行っている企業も。仕事に深く携われる場面が多く、各分野の専門的なスキルや知識を身につけやすいでしょう。
4.正社員の同世代と比べて収入に差が生じやすい
フリーターで働くデメリットの一つとして、正社員として働く同世代との収入差が挙げられます。
厚生労働省が発表した「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」によると、正社員・正職員とそれ以外の平均賃金は以下のとおりです。
※「正社員・正職員以外」にはアルバイトやパートだけでなく、派遣社員や契約社員なども含まれます。そのため、フリーターのみを対象にした統計でない点に留意し、あくまで参考としてご覧ください。
| 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 |
|---|
| ~19歳 | 20万1,600円 | 17万9,400円 |
| 20~24歳 | 23万7,000円 | 19万7,300円 |
| 25~29歳 | 27万2,800円 | 21万9,600円 |
| 30~34歳 | 30万8,500円 | 22万1,900円 |
正社員・正職員は年代ごとにおよそ3万円ずつ平均値がアップしている一方で、それ以外の雇用形態では1万円前後の伸びに留まっていることが分かりました。結果的に、30~34歳の時点では平均で8万円以上の差が生じています。
アルバイトでは働いたぶんだけ収入を得られるため、20代前半までは正社員よりもフリーターの収入が多い場合もあるでしょう。しかし、正社員には年齢や成果に応じた昇給があるため、経験を重ねるごとに収入が上がりやすいのが特徴です。そのため、ずっとフリーターでいることにより、正社員として働く同世代と収入差を感じてしまうことがあるでしょう。
高卒・大卒のフリーターと正社員の収入差
なかには、高卒・大卒後の進路に悩み、フリーターの道を考えている方もいるかもしれません。以下は、厚生労働省の同資料をもとに、学歴ごとの正社員・正職員とそれ以外の収入をまとめたものです。
| 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 |
|---|
| ~19歳 | 20万0,800円 | 18万3,700円 |
| 20~24歳 | 22万1,600円 | 19万300円 |
| 25~29歳 | 24万9,100円 | 19万9,800円 |
| 30~34歳 | 27万3,700円 | 20万6,900円 |
参照:政府統計の総合窓口e-Stat「令和6年賃金構造基本統計調査 雇用形態、学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(正社員・正職員計)(正社員・正職員以外計)」
| 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 |
|---|
| ~19歳 | - | - |
| 20~24歳 | 25万1,800円 | 22万1,800円 |
| 25~29歳 | 28万5,300円 | 26万1,000円 |
| 30~34歳 | 32万8,500円 | 25万9,200円 |
参照:政府統計の総合窓口e-Stat「令和6年賃金構造基本統計調査 雇用形態、学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(正社員・正職員計)(正社員・正職員以外計)」
どちらも、同じ年代で比較すると正社員・正職員のほうが賃金が高いことが分かります。また、正社員・正職員は年齢を重ねるにつれ賃金が上がっている一方で、正社員・正職員以外は高卒が20万円前後、大卒が25万円前後で伸び悩んでいることが分かるでしょう。
35歳のフリーターと正社員の収入差
35歳以降になると、正社員・正職員とフリーターをはじめとする正社員・正職員以外の収入差はさらに広がると考えられます。以下は、35~39歳から55~59歳までの平均賃金を比較したものです。
| 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 |
|---|
| 35~39歳 | 34万0,300円 | 22万1,600円 |
| 40~44歳 | 36万6,800円 | 22万2,600円 |
| 45~49歳 | 39万0,500円 | 22万7,900円 |
| 50~54歳 | 40万3,700円 | 22万3,300円 |
| 55~59歳 | 42万400円 | 22万8,000円 |
フリーターをはじめとする正社員・正職員以外は、35歳以降の賃金が22万円ほどに留まっている一方で、正社員は年々賃金が上がっていることが分かります。もっとも平均賃金が高いのは、55~59歳の約42万円でした。
正社員の賃金が上がりやすいのは、アルバイトにはない昇給・昇格制度が影響していると考えられます。次の項で昇給・昇格について詳しく解説しているので、ぜひ読み進めてみてください。
5.安定した収入を得にくく貯蓄しづらい可能性がある
フリーターは正社員に比べて安定した収入を得にくいため、貯蓄をしづらいと感じる場合があるでしょう。先述のとおり、アルバイトは自由な働き方を実現しやすいぶん、働いたぶんの給与しかもらえません。また、経験を重ねても大幅な給与アップは見込みにくいでしょう。
そのため、長期的に節約したり計画的に貯金したりすればある程度の貯蓄は可能ですが、正社員に比べると貯金額が下がってしまいがちです。ライフプランの実現や、怪我や病気に備えたい方にとって、貯蓄をしづらい点はデメリットといえるでしょう。
6.年齢を重ねるほど就職が難しくなる傾向にある
年齢を重ねるほど就職が難しくなる傾向にあることも、フリーターのデメリットの一つ。フリーター期間が長引くほど、採用担当者から「正社員として働く気がないのでは」「正社員として仕事を続けられるだろうか」などの懸念を抱かれやすくなるためです。
厚生労働省の「平成30年若年者雇用実態調査の概要」によると、過去3年間に「フリーターを正社員採用する予定があった」と回答した事業所は全体の49.9%でした。そのなかで、実際にフリーターを採用した事業所は18.5%、その内15~34歳のみを採用した事業所は10.0%です。35歳以上になると6.4%になることから、フリーターの採用率は年齢が若いほど有利であることが分かります。
20代のうちはアルバイトやパートの掛け持ち、長時間のシフトで十分な収入を得られたとしても、年齢を重ねたときに同じ働き方ができるとは限りません。早めに就職活動を始め、雇用や収入が安定しやすい正社員を目指すのも一つの手です。
フリーターとして働く理由は人それぞれです。メリットとデメリットの両方を把握して、自分に合った働き方を選びましょう。次項では正社員ならではの利点を紹介しているので、今後の働き方を検討する際の参考にしてみてください。
フリーターから正社員を目指すなら早めの行動がおすすめ
フリーターから正社員を目指すなら、早めの行動がおすすめといえます。なぜなら、先述のとおりフリーター期間が長引くにつれ、意欲や志望度を疑問視されやすくなるためです。
また、未経験者を積極的に応募している企業では、キャリア形成の観点から年齢制限を設けていたり、柔軟性や伸びしろといったポテンシャルが期待できる若年層を中心に採用活動を行っていたりすることも。そのため、フリーターとして年齢を重ねてしまうと、求人の選択肢が狭まる恐れがあります。
できるだけ早く行動を開始すれば、上記のリスクを最小限に抑えたうえで、自分に合った仕事を目指しやすくなるでしょう。ハタラクティブでは未経験から挑戦可能な求人も豊富に扱っているので、就職活動の際はぜひご相談ください。
フリーターにはない正社員の5つの利点
フリーターにはない正社員の利点として、「雇用が安定している」「福利厚生が充実している」などが挙げられます。以下では正社員の利点について5つ挙げて紹介するので、確認してみてください。
フリーターにはない正社員の利点
- 雇用が安定している
- 昇給・昇格により収入がアップしやすい
- スキルが身につき職歴が評価されやすい
- 福利厚生が充実している
- 社会的な信用度が高くなる
1.雇用が安定している
正社員は期間の定めがない雇用形態のため、基本的に定年まで勤めることが可能です。企業の倒産や事業縮小などの予期せぬ事態や、終業規則に反する行為や犯罪といったよほどの事情がない限りは解雇されず、「いつ仕事がなくなるか分からない」という不安を回避できるでしょう。
2.昇給・昇格により収入がアップしやすい
正社員には昇給や昇格があることが多く、フリーターよりも収入がアップしやすいことも大きなメリットの一つです。また、できる仕事が増えて昇格したり資格を取得したりすると、役職手当や資格手当といった手当がつくこともあります。
一方、フリーターの場合、職場によっては時給が数十円昇給することはありますが、正社員のように数千円から数万円単位の大幅な昇給はないことが一般的です。
このコラムの「正社員の同世代と比べて収入に差が生じやすい」で述べたように、正社員は年齢層ごとにおよそ3万円ずつ平均賃金が上がっている一方で、正社員以外の雇用形態は1万円ほどに抑えられていました。あくまで平均賃金ではあるものの、正社員のほうが昇給を実現しやすいことが推察できるでしょう。
3.スキルが身につき職歴が評価されやすい
正社員として働き続けることで、担当する分野のスキルが身につきやすいメリットも挙げられます。企業によっては、教育や研修、資格取得支援などが充実しているため、社内の制度を利用してスキルを身につけることが可能です。また、正社員の職歴や身につけたスキル、経験などは転職をする際にも評価される可能性があります。
4.福利厚生が充実している
福利厚生が充実していることも正社員の利点の一つです。企業によっては、各種手当や休業補償、自己啓発支援などの充実した福利厚生が適用されます。福利厚生の種類は企業によって異なり、豊富な企業では、住宅手当やレジャー割引といった生活面でのサポートも受けられるでしょう。
ただし、多くの企業では、福利厚生の対象者を正社員としているようです。アルバイトやパートに福利厚生が適用される場合もありますが、正社員に比べるとその範囲は限定される傾向があります。
5.社会的な信用度が高くなる
フリーターから正社員に就職すると安定した収入を得やすく、社会的な信用度が高まる傾向にあります。賃貸契約やクレジットカード、各種ローンの審査などに通りやすくなるのがメリットです。また、正社員は毎年の収入予想ができるため、結婚や住宅購入といったライフプランも立てやすくなるでしょう。
フリーターを続けるか正社員になるか悩んだときの考え方
フリーターでいることに漠然とした不安を感じつつも、「今の働き方が丁度良い」と悩んでいる方もいるかもしれません。フリーターを続けるか正社員になるか悩んだときは、以下を参考にしてみてください。
フリーターを続けるのが合っている場合
将来やりたいことが決まっていて目標のために時間を使いたい方は、フリーターの働き方が合っている可能性があります。フリーターは正社員と比べると自由な時間が多く、自分の都合に合わせた働き方が実現可能です。そのため、「芸能活動をしたい」「資格の勉強に時間を使いたい」という場合は、フリーターのほうがプライベートの活動と両立しやすいと感じやすいでしょう。
正社員になるほうが合っている場合
「生活を安定させたい」「ライフプランを叶えたい」という方は、正社員の働き方が合っている可能性があります。「フリーターにはない正社員の5つの利点」でも紹介したように、正社員として働くことで雇用や収入が安定し、経済的な不安が軽減されたり将来の見通しを立てやすくなったりするでしょう。
働き方を選ぶうえで大切なことは、自分の将来を長期的に考えて「自分にとって何が最善か」を考えることです。それぞれの選択のメリット・デメリットをしっかりと検討し、後悔しない選択をしましょう。
期限を設けてフリーターを続けるのも手
どちらか決めきれない場合は、期限を設けてフリーターを続け、一定期間経ったら正社員就職を目指すのも手です。たとえば、「今年度いっぱいはプライベートの活動を重視して、その後就職を目指す」「×月までに結果が出なかったら正社員になる」というように、具体的に設定してみましょう。
また、期限から逆算して今やっておきたいことや、就職に向けてやるべきことを整理しておくこともポイント。やりたいことのやり残しや後悔を防げるほか、就職活動を計画的に進めるためにも役立ちます。就職活動は数ヶ月掛かることもあるので、その期間も考慮しつつ、できるだけ細かく計画を立ててみましょう。就職活動に掛かる時間ややり方については、「
就活の時間配分は?自己分析・企業研究にかかる期間や面接の長さを解説!」のコラムで解説しています。
フリーターから正社員になるための準備
フリーターから正社員を目指すためには、なぜ正社員を目指すのかを明確にすることから始めましょう。そのうえで、自己分析でやりたいことや得意分野を洗い出したり、企業・業界研究を行ったりすることが大切です。この項で紹介している順番で準備を進め、就職活動を前向きにスタートしましょう。
1.フリーターから正社員を目指す理由を言語化する
まずは、なぜフリーターから正社員を目指そうと思ったのかを明確にします。正社員を目指す理由は面接で良く聞かれる質問であるのと同時に、自分に合った就職先を見つけるためのヒントにもなるためです。
理由を言語化するときのコツは、できるだけ具体的に考えること。「飲食店のアルバイトをするなかで店舗経営に興味が湧いたから」「さまざまなアルバイトを経験したことで自分は××をやりたいと分かったから」というように、きっかけや考えの変化も盛り込んで言葉にしてみましょう。
反対に、「フリーターよりはお金が稼げそうだから」「なんとなく今の仕事に飽きたから」などの漠然とした理由では、面接で意欲や本気度を評価してもらいにくくなってしまうことも。また、入社後に「思ったより稼げない」「向いていないかも」といったミスマッチが生じる恐れがあります。
2.自己分析でやりたいことや得意分野を洗い出す
次に、自己分析で自分のやりたいことや得意分野をより詳しく分析しましょう。自己分析とは、過去の経験から自分の得意・不得意や好き嫌いなどを洗い出す作業です。丁寧に自己分析を行うことで、自分自身の適性や価値観、仕事に求めることが明確になる効果が期待できます。
「自分を客観視するのが苦手」という方は、他己分析もあわせて活用してみましょう。他己分析とは、友人や家族といった身近な相手に質問し、第三者の視点で自分の長所や短所を教えてもらう作業のこと。自分では気づけなかった長所や適性を知れる可能性があるため、ぜひ行ってみてください。
アルバイトで得た経験やスキルを深掘りしてみよう
自己分析をする際には、アルバイトで経験したことを深掘りしてみるのがおすすめです。
「なぜそのバイトを選んだのか」「業務のなかで何が得意だったのか」「どのようなことにやりがいを感じたのか」などをリストアップして深掘りしてみましょう。自問自答を繰り返すことで、自分の仕事に対する価値観や向き合い方が見えてくることもあります。
また、自己分析を行う際は、自分のことを客観的に捉えて深堀りすることもポイント。「アルバイトで失敗ばかりしている」「いいところが一つもない…」とマイナスに偏った考え方をしてしまうと、自分のことを正しく評価できないためです。「
自己分析で自己嫌悪に陥ったときの対処法を解説!」のコラムを参考に、「欠点ばかりに目を向けない」「短所を長所に置き換えてみる」ことを意識して自己分析をしてみましょう。
3.企業・業界研究を行う
自己分析で自分の強みや価値観を明確にできたら、企業・業界研究を行いましょう。企業や業界の社風や働き方、他社と比較した際の立ち位置などを詳しく調べ、自己分析の結果と照らし合わせることで、長く働ける企業を見つけるきっかけになり得ます。
4.フリーターからの就職活動でよく聞かれる質問の対策を行う
フリーターからの就職活動では、新卒の場合とよく聞かれる質問の傾向が異なります。そのため、考えられる質問を想定し、ある程度話す内容を考えておくことが大切です。
企業の不安を払拭するために前向きな伝え方をしよう
面接では、前向きな伝え方を意識して回答するのも大切なポイントです。企業はフリーターの人材に対し、「正社員の責任ある仕事を任せて良いのか」「長く続けられるのか」といった点で不安を抱いていることも。そういった不安を払拭し、「この人と働きたい」と思ってもらうためには、前向きな姿勢を見せる必要があります。
たとえば、フリーターから正社員を目指す理由を聞かれたら、「アルバイト経験を活かして店舗経営に携わりたいと思ったから」というように意欲が伝わる内容にしましょう。反対に、「親に急かされたから」「本当はやりたくない」など受け身や消極的な姿勢を見せてしまうと、良い印象を与えられない恐れがあります。
フリーターから正社員を目指す方法
フリーターから正社員を目指す方法として、「若手を求める企業に応募する」「正社員登用登用制度を活用する」などが挙げられます。また、就職前に働き方や企業情報をよく知ってから慎重に検討したい場合は、紹介予定派遣制度や就職支援サービスを活用するのも手です。
以下でそれぞれ解説しているので、正社員への就職を検討している方は参考にしてみてください。
若手の人材を求めている企業に自分で応募する
若手の人材を求めている企業に自分で応募することで、フリーターからの正社員就職を実現できる可能性があります。厚生労働省の「令和6年版 労働経済の分析-人手不足への対応-第Ⅱ部第1章 人手不足の背景」によると、2010年以降の人手不足は「全産業的にかつ全国的に広がりをもって人手不足が生じており、職業間の差や地域差もこれまでよりも小さい」のが特徴のようです。
このことより、さまざまな業界で人手不足が進んでおり、そのぶん若手人材や未経験者を積極的に募集している企業も一定数あると考えられます。
若手人材や未経験者を中心に応募している企業は、ポテンシャルを評価してもらいやすく未経験から挑戦しやすいでしょう。また、入社後の教育体制が充実している傾向があり、初めての仕事も徐々に慣れていける可能性があります。
未経験者歓迎の求人を探すときは、求人サイトだけでなく、フリーターや既卒向けの就職・転職エージェントを活用するのがおすすめ。さまざまなサービスを活用することで、数多くの求人を比較検討できます。
エージェントについてはこの項の後半で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
正社員登用登用制度を活用する
フリーターから正社員を目指す方法の一つとして、正社員登用制度の利用が挙げられます。正社員登用制度とは、アルバイト・パートや契約社員などの非正規雇用の従業員を正社員雇用に切り替える制度です。慣れ親しんだ職場で働けることがメリットといえます。
ただし、正社員登用制度を導入していなかったり、制度はあるものの実績がなかったりする企業もあり、正社員登用制度は必ず活用できるものではないのが実情です。希望する際は、制度の有無や条件、実績を確認しておきましょう。
紹介予定派遣を活用する
紹介予定派遣とは、企業が派遣労働者を直接雇用する前提で、一定期間を派遣社員として試用する制度です。その後、企業と本人の双方が合意すれば直接雇用となります。働きながら職場の雰囲気を知れる点が紹介予定派遣を活用するメリットです。しかし、必ずしも正社員として採用されるとは限らないことに注意しましょう。
知り合いに紹介してもらう
フリーターから正社員就職を目指すなら、知り合いに仕事を紹介してもらうのも方法の一つ。知り合いから職場の様子や仕事内容について詳しく聞けるほか、普段の自分の様子を知っている相手なら、第三者の目線から適性や相性を判断してもらえる可能性があります。
ただし、入社後に万が一ミスマッチが生じた場合、「紹介してもらったのに辞めづらい」と精神的な負担を感じることも。「縁故採用ってなに?メリット・デメリットとは」のコラムでメリットとデメリットを紹介しているので、参考のうえ慎重に判断することが大切です。
就職・転職支援サービスを活用する
フリーターから就活する際は、就職支援サービスを活用するのも一つの手です。ハローワークや就職・転職エージェントでは、担当者のアドバイスを受けられたり求人を紹介してもらえたりするため、どのように就活したら良いか悩むフリーターの方におすすめといえます。
以下ではハローワークと就職・転職エージェントについて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は国が設置する公的機関で、無料で職業紹介を受けられます。ハローワークは全国の都道府県に設置されているため、地元企業はもちろん全国各地の求人を検索可能です。
また、「わかものハローワーク(わかもの支援コーナー、わかもの支援窓口)」でも、担当者による個別支援を受けられます。正社員を目指す34歳以下の方が対象のため、該当するフリーターの方は利用を検討してみると良いでしょう。
就職・転職エージェント
就職・転職エージェントは民間の企業が提供するサービスで、専任のキャリアアドバイザーが求職者に合った求人を紹介してくれます。
また、書類の添削や面接練習などの選考対策を受けることも可能です。面接日程の調整といった企業とのやりとりを行ってくれるエージェントもあるので、初めて正社員を目指して就活するフリーターの方も安心して利用できるでしょう。
「フリーターから正社員になれる自信がない」「就職活動のやり方が分からない」という方は、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブはニートやフリーター、既卒、第二新卒など、若年層向けに求人紹介や選考対策などのサービスを実施しています。
専任のキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングを実施し、一人ひとりの適性や希望に合わせて求人をご紹介。業界や職種を問わず未経験から挑戦可能な求人を豊富に扱っており、そのなかからあなたにぴったりの求人を5~6社厳選します。
また、選考対策や内定獲得・入社後のアフターフォローなども行い、初めての正社員就職を徹底的にサポート。サービスはすべて無料でご利用いただけます。就活で迷っている方、自分にできる仕事があるか知りたい方は、お気軽にご相談ください。
フリーターに関するお悩みQ&A
ここではフリーターの方のよくあるお悩みにQ&A方式でお答えします。一人暮らしに関する質問にもお答えしているので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
フリーターとは簡単にいうと、正社員ではなくパート・アルバイトの仕事で生計を立てている人のことです。正社員と違い、雇用期間が定められており、給与形態も時給制や日給制が一般的です。ただし、学生や主婦・主夫でアルバイトで働いている人は、フリーターには含まれません。
フリーターについての詳細は、このコラムの「フリーターとは」をご確認ください。
フリーターを続けることが不安な方は、正社員を目指すのがおすすめです。フリーターから正社員になることで、雇用が安定したり昇給やボーナスを望めたりして、雇用・収入面での不安が軽減される可能性があります。
フリーターから正社員を目指す方法については、「フリーターから正社員になるには?就職活動の基本や受かりやすい職業を紹介」のコラムで詳しく説明しているので、あわせてご一読ください。
フリーターでい続けることは決して悪いことではありません。しかし、年齢を重ねていくうちに就職の難易度が上がったり、同世代の正社員と収入に差が開くことが考えられます。また、今後起こり得るライフイベントに備えて、貯蓄が難しくなる恐れもあるでしょう。
フリーターを続けるメリットやデメリットを、「フリーターの末路とは?生活に与える影響や回避に向けた就職のコツを紹介」のコラムで解説しているので、参考にしてみてください。
可能ですが、生活が厳しくなる恐れがあります。このコラムの「フリーターとして働く7つのデメリット」で述べたとおり、フリーターは大幅な昇給や賞与がないため、貯蓄が難しいと感じやすいでしょう。一人暮らしには家賃や食費、光熱費などさまざまな費用が掛かるため、「生活費はまかなえても貯蓄ができない」という状況に陥る場合もあります。
一人暮らしでゆとりのある生活をしたいなら、フリーターを続けるよりも正社員就職を目指すことがおすすめです。フリーターから正社員を目指すなら、就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。