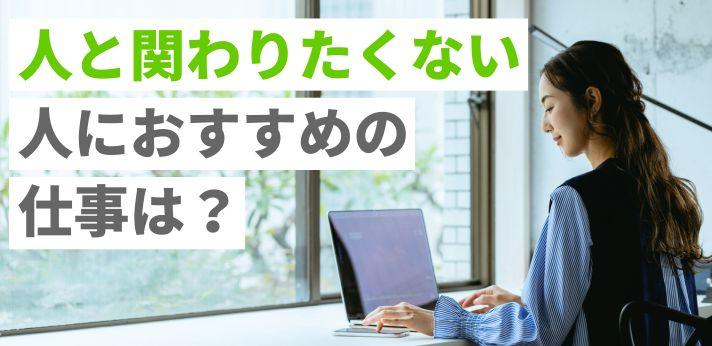ホワイトカラーとは?主な職業・仕事の探し方・ブルーカラーとの違いを紹介ホワイトカラーとは?主な職業・仕事の探し方・ブルーカラーとの違いを紹介
更新日
公開日
ホワイトカラーとは「白い襟」を意味し、オフィスでの業務に従事している人を指す言葉
「ホワイトカラーとは何のこと?」と疑問に思う方もいるでしょう。ホワイトカラーとは、白のワイシャツを着る仕事を指し、事務職・研究者・弁護士などの職業が当てはまります。
このコラムでは、ホワイトカラーの具体的な職業や特徴、抱える問題点などについてまとめました。また、ホワイトカラーとブルーカラーの違いや、ほかのカラーについても紹介しているので、これから就活を行う方はぜひ参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
ホワイトカラーとは
ホワイトカラーとは、企業のオフィスで事務系や販売系の業務に従事している労働者を指す言葉です。医師や弁護士、教師といった知的労働者も含まれ「ホワイトワーカー」とも呼ばれます。
ホワイトカラーの意味・由来
ホワイトカラーの「カラー」とは、英語の「color(色)」ではなく「collar(襟)」のこと。つまり、ホワイトカラーの意味は「白い襟」であり、「ホワイトカラーの仕事」は白のワイシャツを着る仕事を指す言葉といえます。事務職や販売職に就く人々の多くが、白い襟付きのシャツを着ていることが「ホワイトカラー」という言葉の由来です。
ホワイトカラーと似た意味の言葉として、「サラリーマン」が挙げられます。直訳すると「給料をもらう人」という意味ですが、一般的に「民間企業に勤め、事務系の仕事に従事する人」と位置づけられることがほとんどです。そのため、ホワイトカラーと意味が近い言葉として考えられるでしょう。
ホワイトカラーの具体的な職業例
| 分類 | 職種:職業 |
|---|
| 事務 | 一般事務:営業事務、経理事務、総務事務、人事事務、受付
秘書:社長秘書、役員秘書、グループ秘書
データ入力:データ入力オペレーター |
|---|
| 営業・企画 | 営業:法人営業、個人営業、ルート営業、新規開拓営業
企画:経営企画、商品企画、マーケティング企画、広報
マーケティング:Webマーケター、SNSマーケター、広告運用者 |
|---|
| 管理・専門 | 経理・財務:経理、財務、会計士、税理士
人事:人事企画、採用、労務、教育研修
総務:総務、ファシリティマネジメント
法務:企業法務、弁護士、弁理士 |
|---|
| 技術・研究 | 研究開発:基礎研究、応用研究、製品開発
システムエンジニア:SE、プログラマー、ネットワークエンジニア
Webデザイナー:Webデザイナー、UI/UXデザイナー
コンサルタント:経営コンサルタント、ITコンサルタント、戦略コンサルタント |
|---|
| 医療・福祉 | 医療事務:医療事務、病院の受付
専門職:薬剤師、臨床検査技師、保健師、心理士社会福祉士、ソーシャルワーカー |
|---|
| 教育 | 教員:幼稚園教諭、小・中学校教員、高校教員、大学教員
塾講師:塾講師、予備校講師 |
|---|
| 金融 | 銀行員:窓口業務、融資担当、投資運用担当
証券アナリスト:証券アナリスト、ファンドマネージャー
保険:保険外交員、保険事務 |
|---|
| 公務員 | 行政事務系:企画、広報、経理、人事、総務、法務、税務、住民サービス
福祉、環境、教育、文化、防災、都市計画
技術系:建築士、土木技師、情報システム担当、農業技術者、科学技術者、研究員
専門職:司書、学芸員、裁判官、検察官、警察官や消防官の事務・管理職、公立学校の教員 |
|---|
上記のほかにも、研究者や販売スタッフ、接客スタッフ、記者、ライターなどの仕事もホワイトカラーとして挙げられます。
ホワイトカラーの歴史
ホワイトカラーとは、19世紀後半のアメリカで、肉体労働者である「ブルーカラー」と対比して使われ始めた言葉です。歴史的に見ると、産業革命以降、事務作業や管理業務の需要が高まり、スーツや白いシャツを着てデスクワークをする人々が増加した背景があります。20世紀に入ると、企業規模の拡大とともに事務職や管理職がさらに細分化・専門化され、ホワイトカラーは社会の中核的な存在となっていきました。日本でも、高度経済成長期に第三次産業が発展したことにより、ホワイトカラーの仕事が増加した経緯があります。
しかし、近年は情報技術の発展やグローバル化により、ホワイトカラーの働き方や役割も大きく変化しているのが現状です。IT化による業務効率化やAIの登場などが、今後のホワイトカラーに影響を与える可能性があるでしょう。
詳しくは、このコラムの「
ホワイトカラーが抱える3つの問題」で後述するのでご覧ください。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
ホワイトカラーの職業に見られる3つの特徴
先ほど紹介したホワイトカラーの仕事には、主に以下の3つの特徴があるといえます。「ホワイトカラーの仕事に就職したい」という方は、入社後のギャップを防ぐためにもそれぞれの特徴を押さえておきましょう。
ホワイトカラーの職業に見られる特徴
- 頭脳労働である
- デスクワーク中心の業務が多い
- 賃金が高額であることが多い
1.頭脳労働である
ホワイトカラーの特徴として、知的な精神労働を行う点が挙げられます。ホワイトカラーの仕事は体を動かす作業よりも、専門的な知識や技術を駆使して業務を進めることが多い傾向です。
また、知識や技術を身につければ長く働けるというわけではなく、勉強を常に続ける必要があるのも特徴の一つ。たとえば、医療分野の研究やグラフィックの技術は常にアップデートされているほか、サービスや商品を取り巻く市場の動向や流行も日々変化しています。顧客の要望に応えるために、絶えず勉強を重ねる必要があるでしょう。
ホワイトカラーに求められる能力
ホワイトカラーに求められる能力は、職種・職業によって異なります。たとえば、事務職であればパソコンスキル、営業職であればコミュニケーション能力が求められる傾向です。ただし、パソコンスキルやコミュニケーション能力は、業界や職種を問わず役立つスキルでもあります。ホワイトカラーの仕事をしたい方は、身につけておいて損はないといえるでしょう。
2.デスクワーク中心の業務が多い
ほかのカラーに比べてデスクワーク中心の業務が多いのも、ホワイトカラーの特徴です。デスクワークの業務の場合、作業場所は屋内であることが基本のため、屋外で現場作業をする仕事よりも安全に働けるでしょう。
ホワイトカラーは対人業務が多い傾向がある
ホワイトカラーの仕事は、対人業務が多い傾向にあります。販売職や営業職では顧客の求めるサービスや商品を提案したり問い合わせに対応したりするほか、事務職では電話やメールで取引先とのやり取りを任されることもあるでしょう。また、業務を進めるにあたって上司や同僚とのコミュニケーションも求められます。
これらの業務では「相手が何を求めているのか」「どう感じているのか」を理解し、そのうえで適切な言葉や行動を選ぶことが重要です。そのため、高度な知識やスキルだけでなく、状況を把握する力や、感情に配慮しながら柔軟に対応する力が必要とされる仕事だといえます。
3.安定した賃金が得られることが多い
ホワイトカラーは、一般的に安定した賃金が得られる傾向にあります。屋外で行われる仕事の一部では、天候やそのときどきの環境によって仕事の進み具合や成果物の納品状況が大きく異なるため、収入が大きく変動する恐れも。一方、ホワイトカラーの仕事の多くはオフィスや店舗といった屋内で進められるので、成果が天候や環境に左右されにくい傾向です。また、企画立案やデータ分析のように個々の成果が明確な形で見えにくい業務も多々あります。このように、ホワイトカラーは生産性や成果に直接的な影響を与えにくい仕事のため、安定した賃金を得やすいといえます。
ただし、職業によって賃金は異なるため「ホワイトカラーだから高収入を狙える」という先入観で求人を選ぶのは避けましょう。ホワイトカラーの仕事の賃金については、このコラムの「賃金の平均値や伸び率が異なる」で後述するので参考にしてみてください。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
ホワイトカラーの職業が抱えやすい3つの問題
ホワイトカラーの職業は肉体労働が少ないため働きやすい一方で、長時間労働やメンタルヘルスへの影響といった問題も挙げられます。問題点も把握したうえで、ホワイトカラーの仕事に就くかどうか決めることが大切です。
ホワイトカラーが抱える3つの問題
- 過重労働になる可能性がある
- メンタルヘルスへの影響が懸念される
- ロボットやAIに仕事を奪われる可能性がある
1.過重労働になる可能性がある
ホワイトカラーが抱える問題のひとつとして、「過重労働」が挙げられます。ホワイトカラーの仕事は取引先や顧客とのやりとりが生じる場合もあり、予想外の時間外労働が発生したり、デスクワークのため長時間労働のハードルが下がりやすかったりすることも。また、ホワイトカラーの仕事のなかでも「企画立案」「顧客対応」といった業務は終わりが見えにくく、「結果的に働き過ぎていた」ということもあるようです。近年はリモートワークによって仕事のオンオフを切り替えにくくなっていることも、過重労働のリスクの一つと考えられます。
2.メンタルヘルスへの影響が懸念される
メンタルヘルスへの影響も、ホワイトカラーの仕事の問題点として挙げられるでしょう。厚生労働省の「職場におけるメンタルヘルス対策の状況」によると、労働者が仕事に不安やストレスを感じる主な原因は、以下のとおりです。
| 項目 | 割合 |
|---|
| 仕事の質・量 | 43.4% |
|---|
| 仕事の失敗、責任の発生等 | 35.9% |
|---|
| 対人関係(セクハラ・パワハラを含む) | 26.2% |
|---|
| 会社の将来性 | 23.1% |
|---|
| 顧客、取引先等からのクレーム | 21.9% |
|---|
| 役割・地位の変化等(昇進、昇格、配置転換等) | 16.2% |
|---|
| 雇用の安定性 | 11.8% |
|---|
| 事故や災害の体験 | 3.6% |
|---|
| その他 | 12.5% |
|---|
ホワイトカラーは顧客や取引先とコミュニケーションを取る機会が多く、クレームや要求に対応しなければならないことも。また、ホワイトカラーの仕事は、1人に対して課される業務量や責任が大きく、精神的負担が掛かりやすいといわれています。ホワイトカラーの業務は上記のストレス要因と関連性がある場合が多く、働き方や職場環境によってはメンタルヘルスに影響を及ぼすリスクがあるでしょう。
3.ロボットやAIに仕事を奪われる可能性がある
ホワイトカラーの仕事は、ロボットやAIに奪われる恐れがあるといわれています。データの打ち込みや分析などの業務は、ロボットやAIが得意とする分野だからです。また、近年は文章や画像、映像を生成できるAIが注目を浴びていることもあり、将来的にAIがホワイトカラーの幅広い分野で人間に代わって活躍する可能性があります。
ブルーカラーとは?ホワイトカラーとの違い
ブルーカラーとは、肉体労働者を指す言葉です。「白い襟」という意味であるホワイトカラーに対し、ブルーカラーは「青い襟」を意味し、生産現場で働く人の青い作業着を表しています。
| 業種 | 職種:職業 |
|---|
| 製造 | 生産・製造職:組立、加工、検査、溶接、旋盤、プレス
メンテナンス職:設備保全、修理工 |
|---|
| 建設 | 建設・土木職:大工、左官、とび職、配管工、電気工事士、重機オペレーター
舗装工:道路の舗装作業 |
|---|
| 運輸・物流 | 運転・運搬職:トラック運転手、バス運転手、タクシー運転手、フォークリフトオペレーター
倉庫管理職:倉庫作業員、ピッキング作業員 |
|---|
| 農業・林業・漁 | 生産・栽培職:農業従事者、酪農家、林業作業員
漁業従事者:漁師 |
|---|
| 清掃・保守 | 清掃職:ビル清掃員、ハウスクリーニング
設備管理職:施設警備員、ビル設備管理員 |
|---|
| 飲食 | 調理・サービス補助職:調理補助、皿洗い、清掃係 |
|---|
上記のブルーカラーの仕事と、このコラムの「ホワイトカラーの具体的な職業例」で先述したホワイトカラーの仕事は異なることが分かるでしょう。具体的な職業のほか、「働き方」「身に就くスキル」「賃金」といった点もカラーによって異なります。以下で、ホワイトカラーとブルーカラーの違いについて詳しく解説するので、仕事選びに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
働き方が異なる
ホワイトカラーとブルーカラーでは、働き方が異なります。先述のとおり、ホワイトカラーとはオフィスで仕事を行う労働者のこと。業務の多くをオフィスや店舗のなかで行うため、肉体的な負担は少ないといえます。
一方、ブルーカラーは建設現場や農地といった野外で業務に当たったり、自動車や重機を運転したりする業務が主です。体力を活かせるという大きな強みがあるものの、ホワイトカラーに比べると肉体的な故障や事故が起きやすい環境にあるといえます。
ブルーカラーの「3K」「3D」とは?
ブルーカラーの「3K」とは、「きつい」「汚い」「危険」という、日本の肉体労働の現場にありがちな労働環境のネガティブな側面を指す言葉です。一方、「3D」は「3K」を英語で表現したもので、「Dirty(汚い)」「Dangerous(危険)」「Demeaning(きつい/屈辱的)」の頭文字を取っています。
これらの言葉は、労働者が感じる身体的・精神的な負担や、衛生面・安全面での課題を表したもの。特に、製造業や建設業といった現場作業を伴う職種において、懸念されやすい傾向にあります。近年では、働き方改革などで改善の動きも見られるものの、ブルーカラーの仕事に「3K」「3D」のイメージを抱く方は一定数いるようです。
身につく知識や技術が異なる
ホワイトカラーとブルーカラーの違いとして、身につく知識や技術の違いも挙げられるでしょう。ホワイトカラーの場合、対人能力や論理的思考力といったポータブルスキルや、その仕事に関連する専門的な知識を習得できます。ただし、企業によってやり方や細かいルールが異なることもあるようです。
一方、ブルーカラーの仕事に就くと、その分野で広く活躍できる専門知識や技術を習得できます。たとえば、建築関係の仕事であれば建築や塗装、インフラ整備といった技術、タクシーやトラックのドライバーであれば運転技術などが挙げられるでしょう。ブルーカラーの仕事をとおして得た知識や技術は、関連する業界や職種で活かせることも多く、長く活用できる可能性が高いといえます。
転職の難易度が異なる
ホワイトカラーとブルーカラーでは、転職活動の難易度が異なることがあるようです。ホワイトカラーの場合、先述したようなポータブルスキルや仕事に関する専門知識を得られます。営業職や販売職といった仕事なら、基本的な仕事の進め方や求められる能力は変わらないことが多いため、アピールしやすいでしょう。
しかし、仕事によっては能力を客観的に説明することが難しかったり、以前の勤務先と転職先で仕事の進め方が異なったりするため経験を活かしきれない場合もあります。
それに対し、ブルーカラーの仕事で求められる専門的な知識やスキルは、同じ業界・職種で広く活かせることが多いでしょう。資格や経験業務によって能力を客観的に証明しやすく、転職活動でアピールしやすいといえます。
また、ブルーカラーの仕事は人手不足が続いているため、比較的採用されやすいという側面も。将来的に長く活躍できる可能性が高く、「手に職をつけたい」という方におすすめです。
賃金の平均値や伸び率が異なる
ホワイトカラーとブルーカラーの初任給に大差はありませんが、平均賃金はホワイトカラーのほうが高く、賃金の伸び率はブルーカラーのほうが高い傾向があります。賃金について、以下で詳しく見てみましょう。
初任給に大きな違いはない
高卒の初任給を見てみると、ホワイトカラーとブルーカラーで大きな差は見られません。ここでは、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」を参考に、初任給が含まれる年代の平均賃金についてまとめました。ただし、あくまで年代ごとの統計のため、参考としてご覧ください。
| ホワイトカラーが多く見られる産業 | 平均賃金(~19歳) | 平均賃金(20~24歳) |
|---|
| 情報通信業 | 20万400円 | 24万9,100円 |
|---|
| 卸売業、小売業 | 19万9,700円 | 23万600円 |
|---|
| 金融業、保険業 | 18万3,900円 | 25万500円 |
|---|
| 不動産業、物品賃貸業 | 20万4,200円 | 25万9,600円 |
|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 19万5,400円 | 24万5,300円 |
|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | 19万4,600円 | 22万1,000円 |
|---|
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 20万100円 | 22万4,500円 |
|---|
| 教育、学習支援業 | 18万8,300円 | 23万2,500円 |
|---|
| 医療、福祉 | 19万9,000円 | 24万4,000円 |
|---|
| 複合サービス事業 | 18万8,200円 | 21万3,500円 |
|---|
| ホワイトカラーの平均 | 19万5,380円 | 23万7,060円 |
|---|
上記の表から、ホワイトカラーの仕事が多数見られる産業の平均賃金は、19歳以下で19万5,380円、20~24歳で23万7,060円と分かります。
一方、ブルーカラーの仕事の平均賃金は以下の表のとおりです。
| ブルーカラーが多く見られる産業 | 平均賃金(~19歳) | 平均賃金(20~24歳) |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採 取業 | 21万2,500円 | 26万7,400円 |
|---|
| 建設業 | 20万3,600円 | 23万8,900円 |
|---|
| 製造業 | 19万8,100円 | 21万6,800円 |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 20万4,200円 | 24万4,400円 |
|---|
| 運輸業、郵便業 | 20万4,500円 | 23万4,900円 |
|---|
| ブルーカラーの平均 | 20万4,580円 | 24万480円 |
|---|
上記の表から、ブルーカラーの仕事が多数見られる産業の平均賃金は、19歳以下で20万4,580円、20~24歳で24万480円。ホワイトカラーの平均賃金は、19歳以下で17万9,100円、20~24歳で22万円であり、カラーによる差は大きくないといえるでしょう。ブルーカラーの仕事のほうがやや平均賃金が高い理由としては、業務においてより専門的な知識・スキルが必要な業務を行う場合が多いからと考えられます。
平均賃金はホワイトカラーのほうが高い産業が多い
平均賃金は、ホワイトカラーのほうが高い産業が多い一方で、低めの産業も見受けられる傾向にあります。下表は、厚生労働省の厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」のデータをもとにした、ホワイトカラーとブルーカラーの平均賃金です。
| ホワイトカラーが多く見られる産業 | 平均賃金 |
|---|
| 情報通信業 | 39万1,000円 |
|---|
| 卸売業、小売業 | 34万3,600円 |
|---|
| 金融業、保険業 | 41万600円 |
|---|
| 不動産業、物品賃貸業 | 37万1,600円 |
|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 40万1,800円 |
|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | 26万9,500円 |
|---|
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 28万5,700円 |
|---|
| 教育、学習支援業 | 37万6,200円 |
|---|
| 医療、福祉 | 30万6,400円 |
|---|
| 複合サービス事業 | 30万6,900円 |
|---|
| ホワイトカラーの平均 | 34万6,330円 |
|---|
| ブルーカラーが多く見られる産業 | 平均賃金 |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採 取業 | 37万2,300円 |
|---|
| 建設業 | 35万2,600円 |
|---|
| 製造業 | 31万8,600円 |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 43万7,500円 |
|---|
| 運輸業、郵便業 | 30万4,700円 |
|---|
| ブルーカラーの平均 | 35万7,140円 |
|---|
ホワイトカラーの一つである「金融業、保険業」は、ホワイトカラーに分類した産業のうち最も平均賃金が高く、41万600円でした。そのあとは「学術研究、専門・技術サービス業」が40万1,800円、「情報通信業」が39万1,000円、「教育、学習支援業」が37万6,200円と続きます。ホワイトカラーのなかでも、研究や教育、通信情報業といった専門的な知識が必要な産業や、営業職が多くインセンティブを得やすい金融業、保険業などが賃金が高い傾向にあるといえるでしょう。
一方で、専門的な知識や技術が求められないことが多いサービス業や飲食業などは、全体と比較しても賃金が低いという結果でした。産業や職種によって賃金に大きな差があることが推察できます。
それに対して、ブルーカラーの仕事は賃金が30万以下の産業はなく、一定の賃金を得やすい傾向にあることが分かるでしょう。特に、「電気・ガス・熱供給・水道業」の平均賃金は43万7,500円で、全産業で最も高い数値でした。
賃金の伸び率はブルーカラーのほうが高い
賃金の伸び率は、ホワイトカラーよりブルーカラーのほうが高い傾向にあります。以下は、厚生労働省の厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」をもとに作成した、ホワイトカラーとブルーカラーの賃金の伸び率の表です。
| ホワイトカラーが多く見られる産業 | 20~24歳の賃金
(A) | 50~54歳の賃金
(B) | 賃金の伸び率
(B-A)/A |
|---|
| 情報通信業 | 24万9,100円 | 48万5,200円 | 94.78% |
|---|
| 卸売業、小売業 | 23万600円 | 41万6,300円 | 80.53% |
|---|
| 金融業、保険業 | 25万500円 | 49万6,600円 | 98.24% |
|---|
| 不動産業、物品賃貸業 | 25万9,600円 | 43万1,900円 | 66.37% |
|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 24万5,300円 | 47万9,800円 | 95.6% |
|---|
| 宿泊業、飲食サービス業 | 22万1,000円 | 30万5,300円 | 38.14% |
|---|
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 22万4,500円 | 31万6,700円 | 41.07% |
|---|
| 教育、学習支援業 | 23万2,500円 | 43万6,800円 | 87.87% |
|---|
| 医療、福祉 | 24万4,000円 | 32万6,400円 | 33.77% |
|---|
| 複合サービス事業 | 21万3,500円 | 36万9,600円 | 73.11% |
|---|
| ホワイトカラーの平均 | 23万7,060円 | 40万6,460円円 | 71.46% |
|---|
| ブルーカラーが多く見られる産業 | 20~24歳の賃金
(A) | 50~54歳の賃金
(B) | 賃金の伸び率
(B-A)/A |
|---|
| 鉱業、採石業、砂利採 取業 | 26万7,400円 | 42万600円 | 57.29% |
|---|
| 建設業 | 23万8,900円 | 40万7,500円 | 70.57% |
|---|
| 製造業 | 21万6,800円 | 37万4,400円 | 72.69% |
|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 24万4,400円 | 55万6,500円 | 127.7% |
|---|
| 運輸業、郵便業 | 23万4,900円 | 32万7,800円 | 39.55% |
|---|
| ブルーカラーの平均 | 24万480円 | 41万7,360円円 | 73.55% |
|---|
上記から、ホワイトカラーでは、伸び率が60%以上の産業と40%以下の産業の二極化していることが分かります。ブルーカラーでは、「運輸業、郵便業」が39.55%、「鉱業、採石業、砂利採 取業」が57.29%であるものの、ほかの産業は70%以上の伸び率を記録。特に、「電気・ガス・熱供給・水道業」は127.7%の伸び率と、全産業で最も高い数値でした。
両者の違いは目立たなくなってきている
ホワイトカラーとブルーカラーでは「働き方」「賃金」といった点で違いがあるものの、近年は技術の発展や賃金の平準化が影響し、両者の差は目立たなくなってきているようです。また、若いうちに転職活動を始めたり、在職中の経験や身につけたスキルを活かせる仕事を選んだりすれば、ホワイトカラーとブルーカラーどちらであっても転職成功の可能性はあるといえます。
そのため、仕事選びの際は「ホワイトカラーのほうが危なくなくて楽だから」「ブルーカラーのほうが転職しやすいから」という決め方は避け、将来を見据えたうえで自分のやりたいことや適性に合うかどうかを考えることが大切です。「やりたいことがはっきりとしない」「自分の適性に合う仕事が分からない」という場合は、自己分析をしたり就職・転職エージェントに相談したりしてみてください。
ホワイトカラー・ブルーカラー以外の「〇〇カラー」
ここまで解説してきた「ホワイトカラー」と「ブルーカラー」のほかにも、さまざまなカラーの仕事が存在します。以下で、ホワイトカラーとブルーカラー以外の6つのカラーを紹介するので、仕事選びの参考にしてみてください。
グレーカラー
グレーカラーとは、「ホワイトカラーにもブルーカラーにも当てはまらない」もしくは「両方の性質をあわせもつ」業務を担当する労働者を指す言葉。「頭脳労働」「肉体労働」と明確に分類されない業務が該当します。たとえば、工場における管理職や保安職の従事者がその一例です。
また、エンジニアの仕事は、ホワイトカラーではなくグレーカラーと分類されることもあります。たとえば、客先に常駐したりさまざまな現場に足を運んだりするエンジニアは、ホワイトカラーとブルーカラーどちらの性質も備えているでしょう。長時間パソコンと向かい合う集中力や体力が必要な点や、ブルーカラーの業界と似た構造をもっていることから、「ホワイトカラーといいきれない」という意見もあるようです。
IT業界の「3K」とは?
IT業界での「3K」とは、従来の「きつい・汚い・危険」とは異なる、IT業界特有の労働環境を指すことが多いようです。IT業界の3Kに明確な定義はありませんが、主に「きつい・帰れない・給料が安い」といった言葉を指します。
また、3Kに「休暇が取れない・規則が厳しい・化粧がのらない・結婚できない」の4Kを足して、7Kと表現される場合も。「3K」「7K」と聞くとネガティブな印象を抱いてしまいがちですが、IT業界で働くことには「柔軟に働きやすい」「知識やスキルを身につけられる」といったメリットもあります。「
IT業界の仕事」のコラムでIT業界の仕事についてまとめているので、気になる方はぜひご一読ください。
グリーンカラー
グリーンカラーとは、自然環境の保全や保護に携わる労働者を指す言葉です。具体的には、地熱や風力、太陽光などを活用したクリーンエネルギーに関わる従事者や、林業の従事者などが該当します。
メタルカラー
メタルカラーとは、ものづくりに関する高度で熟練された技術を駆使して業務を行う技術職や職人などを指す言葉です。具体的には半導体や自動車などの製造業を指します。
シルバーカラー
シルバーカラーとは、高齢者福祉に関わる労働者を指す言葉のこと。「シルバー」は襟の色ではなく、高齢者を指す言葉からきています。デイサービスや老人ホームといった介護施設や訪問介護の職員、高齢者向けの治療やリハビリを行う医療サービスに従事する医師や理学療法士などが対象です。
ピンクカラー
ピンクカラーとは、保育士や看護師、ハウスキーパーといった職業を指す言葉。元々は女性の従事者が多いという理由からピンクと名づけられました。
ゴールドカラー
ゴールドカラーとは、組織に所属せず、高い技術や知識を武器にキャリアを形成していく人を指します。また、研究職やコンサルなど、企業に雇用されていても専門知識やマネジメント力を活かして自立した活躍をしている労働者は、ゴールドカラーに分類されるようです。
自分に合ったカラーの見極め方
仕事を探すなかで、「どのカラーの仕事が自分に合うのだろう…」と悩む方もいるでしょう。自分に合う仕事を見つけるには、仕事について調べるだけでなく、「自分の適性や強みを知る」という作業も重要。漠然としたイメージや「やってみたい」という気持ちだけで仕事を選ぶと、入社後のミスマッチにつながりかねないからです。
自分自身の強み・弱みや適性、価値観を知るためにも、まずは自己分析を行いましょう。これまでの社会人経験だけでなく学生時代の経験も振り返り、「なぜ頑張れたのか」「なぜ苦手に感じていたのか」といった感情の動きや行動の理由を分析する方法がおすすめです。
「一人で自己分析をするのは難しい」と感じる場合は、家族や友人といった第三者に意見をもらってみるのも手でしょう。客観的な意見を得られるため、新たな発見を得られる可能性があります。「自己分析の方法をご紹介!就活や転職に役立てよう」のコラムを参考にしながら、自分自身の適性を見極めてみましょう。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
ホワイトカラーエグゼンプションとは
ホワイトカラーエグゼンプションとは、労働時間ではなく成果で評価する制度のこと。日本では、ホワイトカラーエグゼンプションのことを「高度プロフェッショナル制度」ともいいます。
制度を導入する目的
ホワイトカラーエグゼンプションを導入することで、企業の生産性向上と、労働者の創造性や専門能力を最大限に引き出すことが可能です。時間を基準に賃金が決められる場合、作業のスピードが早く能力が高い人ほど決められた時間内で多くの仕事量をこなすことになります。すると、「自分より仕事量が少ない人と同じ給料なのは納得できない」といった不満が生じやすいでしょう。
一方、ホワイトカラーエグゼンプションを導入して仕事の成果で評価される場合は、このような不満は生じにくいといえます。「もっと仕事を頑張って収入アップやキャリアアップを目指そう」と仕事への意欲が高まったり、仕事に意欲的な従業員が増えて企業の生産性が上がったりする効果も期待できるでしょう。
対象となる主な仕事と条件
ホワイトカラーエグゼンプションは、すべての仕事が対象となるわけではありません。また、対象となる条件も決められています。以下で、ホワイトカラーエグゼンプションの対象となる主な仕事と条件について詳しくみていきましょう。#高度の専門的知識等を必要とする職種が対象
- ・金融商品の開発業務
- ・金融商品のディーリング業務
- ・アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
- ・コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)
- ・研究開発業務
上記の対象業務は、「高度の専門的知識等を必要とする」「従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」という性質のもと規定されています。
専門知識を有し一定の年収を得ていることが条件
同資料によると、対象労働者の条件として以下のように決められています。
- ・書面等による合意に基づき職務の範囲が明確に定められている労働者
- ・「1年間に支払われると見込まれる賃金の額が、『平均給与額』の3倍を相当程度上回る」水準として、省令で規定される額(1075万円を参考に検討)以上である労働者
簡単にまとめると、ホワイトカラーエグゼンプションは「年収が1,075万円以上かつ高度な専門知識などを有する労働者」が対象です。
メリット・デメリット
ホワイトカラーエグゼンプションのメリット・デメリットを以下の表にまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|
・成果を出せば仕事を終了できる
・残業時間が長いほど賃金が上がる不公平感がなくなる
・就業時間内に仕事を終わらせようという意識が芽生えやすくなる | ・残業代が発生しない
・業務内容によっては就業時間内に終わらせることが難しく、精神的な負担になる場合もある
・個人主義的な考え方が浸透しやすく、チームプレーがしにくい可能性がある |
|---|
効率的に働いたとしても、仕事内容や能力によっては残業時間が発生する場合もあり得ます。そうしたときに残業代が出ない点はデメリットといえるでしょう。また、成果によって評価させることから個人主義な思考に陥りやすいことも、仕事を進めるなかでデメリットと感じる可能性があります。
一方で、「残業代が出ないから仕事を早く終わらせよう」と心掛ける労働者が増えるでしょう。効率的に業務を進める力を磨けること、効率的に仕事を行い生産性を高めることで企業に評価されやすいことは、ホワイトカラーエグゼンプションのメリットです。
また、一人ひとりの生産性が高まることは企業にとっての大きなメリットになり得るため、ホワイトカラーエグゼンプションは労働者側、経営者側のどちらにもメリットがあるといえます。
ホワイトカラーエグゼンプションと裁量労働制の違い
ホワイトカラーエグゼンプションと裁量労働制は似ている制度ですが、残業代の有無において違いがあります。先述したように、ホワイトカラーエグゼンプションの場合は残業代が発生しません。一方、裁量労働制では残業代が発生します。
裁量労働制については、「
裁量労働制を適用できる職種は?他の制度との違いや残業代についても解説」のコラムで詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
自分に合うホワイトカラーの仕事を見つけるコツ
ここでは、自分に合うホワイトカラーの仕事の見つけ方をご紹介します。「ホワイトカラーの仕事ならなんでもいい」と考えて仕事を選ぶと、「仕事内容が自分の適性や保有スキルに合わなくてつらい」と後悔してしまう恐れも。入社後につらい思いをしないためにも、以下の方法を参考にしながら仕事選びを進めましょう。
メリット・デメリットを把握する
ホワイトカラーの仕事に就きたい場合は、メリット・デメリットを踏まえたうえで、入社後の働き方を想像してみるのがおすすめ。そうすることで、入社後にミスマッチに気づいて後悔したり、早期離職したりするのを防げます。以下に、ホワイトカラーのメリット・デメリットをまとめたので参考にしてみてください。
| メリット | デメリット |
|---|
・肉体労働が少ない
・室内での業務が多い
・賃金が安定している傾向
・年齢を重ねても仕事を続けやすい | ・過重労働になりやすい
・精神的な負担を感じる場合がある
・ロボットやAIに仕事を奪われる可能性がある |
|---|
ホワイトカラーの仕事は、肉体労働や屋外での仕事が少ないため、年齢を重ねても働きやすいでしょう。また、このコラムの「3.安定した賃金が得られることが多い」で説明したように、賃金が比較的安定している点もメリットといえます。
しかし、ホワイトカラーの仕事は精神的な負担を感じることがあったり、過重労働や将来的に機械に仕事を代替されてしまったりする可能性があるデメリットも。このコラムの「ホワイトカラーの職業が抱えやすい3つの問題」をよく確認したうえで、自分にホワイトカラーの仕事が合うかどうかを見極めることが重要です。
ブルーカラーの仕事に就くメリット・デメリット
ブルーカラーのメリットとして、仕事を通して専門的な知識やスキルを身につけられることや、その知識・スキルが転職をする際に評価されやすいことが挙げられます。一方で、肉体労働になりやすい点や、3K(きつい・汚い・危険)の特徴が見られる場合もあるのはデメリットといえるでしょう。
なお、ブルーカラーにおける肉体労働や仕事環境は、技術の進歩によって改善されつつあります。起業ごとに仕事内容や働く環境は異なるので、ブルーカラーの仕事に興味がある場合は企業研究を入念に行うことをおすすめします。
自己分析をして客観的に自分を理解する
就職・転職に向けて仕事探しをする際は、自己分析をしっかりと行いましょう。自己分析をとおして自分への理解を深めることで、自分に合う仕事や企業を見つけやすくなります。自己分析を行う際は、以下の項目を洗い出してみてください。
- ・自分の強み・弱み
- ・身につけたスキル
- ・持っている資格
- ・興味関心のあること
- ・希望する働き方(固定制かシフト制か、休日の曜日、リモートワークがいい、など)
上記のなかでも、自分の強みや弱みについて考えるときは、過去の自分の経験を振り返るだけでなく、他者に聞いてみるのもおすすめ。自分では気づかなかった側面を知れることもあり、より客観的な自分像を把握できます。身近に自分について聞ける相手がいない場合は、ハローワークやエージェントを利用して、自己分析を手伝ってもらうのも手です。
自己分析ができたら、先述したホワイトカラーのメリットデメリットを踏まえ、自分が希望する働き方ができるか考えてみましょう。
業界・職種への理解を深める
「自分にはホワイトカラーの仕事が向いている」と判断できたら、業界や職種について詳しく調べてみてください。同じホワイトカラーの仕事であっても、職業によって向き不向きはあると考えられます。自分に合う業界・職種は何かを明確にし、そのなかからホワイトカラーの仕事を選べば、入社後のミスマッチや早期離職を防げるでしょう。
業界について調べる際は、「業界図鑑」をお役立てください。業界ごとに、仕事内容や特徴、具体的な職業などをまとめています。
企業研究をして自分との相性を見極める
自己分析や業界・職種について調べたあと、自分に合うホワイトカラーの仕事が定まったら企業研究を行いましょう。同じ職業でも企業によって仕事内容や働き方は異なるため、企業研究を怠ってしまうと「自分が想像していたホワイトカラーの仕事じゃなかった」という事態に陥る恐れも。「企業研究のやり方を解説!調べることや就職・転職活動への活かし方も紹介」のコラムを参考にしながら企業研究を行い、自分が理想とするホワイトカラーの仕事かどうかを見極めることが重要です。
社風の見極め方
自分に合う仕事を探す際は、社風についてもチェックしておくのがおすすめ。せっかく自分に合うホワイトカラーの仕事に就いたとしても、社風が合わなければ「居心地が悪い」「働きにくい」などのストレスになり得ます。場合によっては、モチベーションが続かずに早期離職につながる恐れも。こうした事態を防ぐためにも、以下の方法で社風を調べ、企業の価値観や働き方が自分と合致するかどうかを見極めることが大切です。
- ・OB/OG訪問
・会社のWebサイトで情報を集める
・会社説明会に参加する
・業界研究をする
・企業規模を参考にする
上記の方法の詳細は、「
社風のリサーチ方法を複数紹介!自分に合う会社の見つけ方とは」のコラムで紹介しています。ぜひご一読ください。
就職・転職エージェントに相談するのも手
「自分に合うホワイトカラーの仕事を見つけられない」「この仕事が自分に合っているのか分からない」という場合は、就職・転職エージェントに相談するのも一つの手です。エージェントの多くは、求人紹介のほかにも就職・転職に関する悩み相談や、自己分析のサポートを実施しています。また、企業の内情を教えてくれることもあるので、仕事内容や働き方、社風について知ることも可能です。
「ホワイトカラーの仕事に興味がある」「自分に合う仕事を見つけたい」という方は、若年層の求職者を対象とした就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。専任のキャリアアドバイザーが行う丁寧なヒアリングや1分程度で行える適職診断の結果をもとに、一人ひとりの適性や希望に合う仕事をご紹介します。
また、自己分析や応募書類の作成のサポート、面接練習なども実施。就職・転職に関する悩みも相談可能なので、不安を解消しながら就職活動を進められるのが魅力です。ハタラクティブが提供しているサービスはすべて無料でご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
ホワイトカラーに関するQ&A
ここでは、ホワイトカラーについてよくある質問と回答をまとめました。ホワイトカラーの仕事に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
ホワイトカラーとは、主にオフィスに出社して勤務する仕事や、従事する労働者を指します。ホワイトカラーの特徴は、「頭脳労働や対人業務が多い」「比較的安全に業務が行える」など。ホワイトカラーの概要については、このコラムの「ホワイトカラーとは」をご参照ください。
「ホワイトカラーの仕事がなくなる」といわれるのはなぜですか?
「ホワイトカラーの仕事がなくなる」といわれているのは、データ入力や文書作成といった定型業務や単純作業が、将来的にAIによって自動化される可能性があるためです。将来性のある仕事に就きたいという方は、「10年後もなくならない仕事とは?特徴や代表的な職種を紹介!就職のコツも」のコラムで具体的な職業や特徴などをまとめています。仕事探しの参考にしてみてください。
ホワイトカラーとブルーカラーのどちらを選ぶべきですか?
自分の適性に合ったほうを選びましょう。考えるのが好きならホワイトカラー、体を動かすのが好きならブルーカラーといった単純な選び方でなく、自己分析を通じて自分の適性をじっくり考えることが大切です。ホワイトカラー、ブルーカラーというのはあくまで仕事の傾向であり、世の中の多様な職種は、その2つのどちらかにはっきり分かれているわけではありません。
自分について理解を深めるためには、「自己分析が大事!『やりたいこと探し』の方法とは」のコラムを参考にしてみてください。
ホワイトカラーには具体的にどんな職業がありますか?
ホワイトカラーは主にデスクワークや頭脳労働を行う職種です。具体的には、事務職や営業職、研究職、弁護士、コンサルタントなどが挙げられます。ホワイトカラーの職業については、このコラムの「ホワイトカラーの具体的な職業例」で分かりやすく表にまとめているので、ぜひご覧ください。
このコラムの「自分に合うホワイトカラーの仕事を見つけるコツ」を参考に、ホワイトカラーのメリット・デメリットや自分の適性を踏まえたうえで仕事を探しましょう。なかなか自分に合う仕事を探せなかったり、本当に子の仕事が向いているのか分からなくて不安だったりする場合は、就職エージェントのハタラクティブにご相談ください。専任のキャリアアドバイザーが、仕事探しや書類添削など、転職活動を幅広くサポートします。