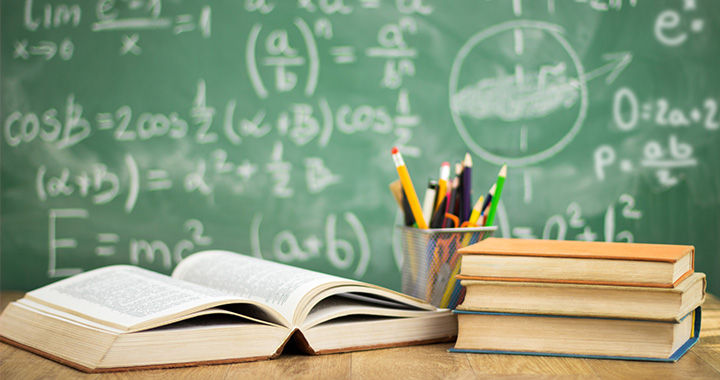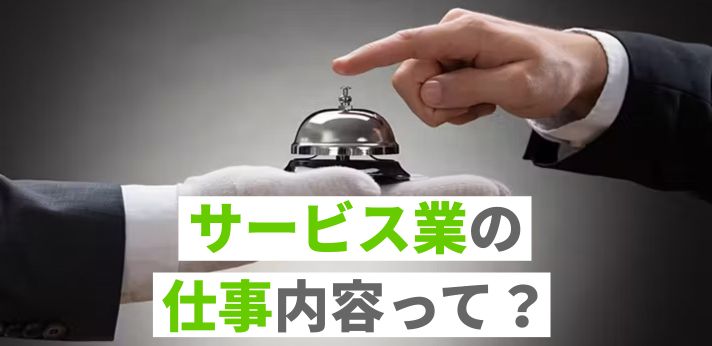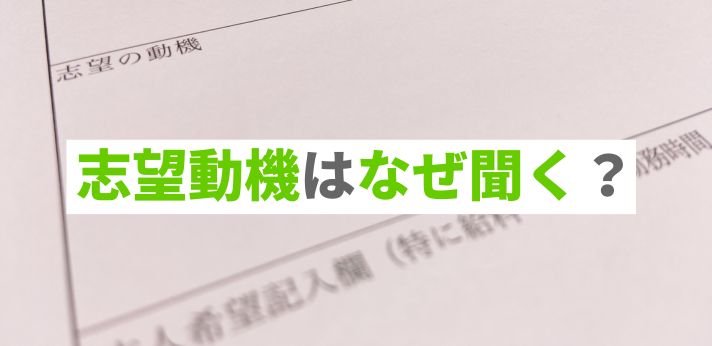インフラ業界とは?主な職種一覧や向いている人の特徴、将来性などを解説
更新日
公開日
インフラ業界には、エネルギー・生活・交通・空間などの分野がある
「インフラ業界にはどのような仕事があるのか」「どのような人に向いているのか」と、疑問に思う方もいるでしょう。インフラ業界はエネルギーや生活、交通、空間など、人々の生活を支える分野を担っており、社会に欠かせない存在です。
このコラムでは、インフラ業界の分野や職種、将来性などをご紹介します。インフラ業界に向いている人の特徴や年収事情もご紹介するので、インフラ業界に挑戦するか迷っている方は、ぜひご覧ください。
あなたの強みをかんたんに
発見してみましょう!
あなたの隠れた
強み診断
こんな人におすすめ
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
- 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方
ハタラクティブは、スキルや経歴に自信がないけれど、就職活動を始めたいという方に特化した就職支援サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。
※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
インフラ業界とは
インフラ業界とは、人々の社会生活の基盤を支えているサービスを提供する業界のことです。インフラ業界は、電気やガス、水道、交通、通信など、生活や経済活動を行うためになくてはならない部分を担っています。「エネルギー」「生活」「交通」「空間」などに分かれているのが特徴です。
| 業界概要 | 人々の生活や産業活動を支える、道路や鉄道、電力、ガス、水道、通信といった社会基盤を整備・維持・管理する。公共性が高く、経済や安全保障の面で重要な役割を担う。 |
|---|
| 平均年収 | 552万円 |
|---|
| 具体的な職種 | ・電気工事士
・ガス技術者
・インフラエンジニア |
|---|
| ポイント | ・生活基盤を支える常に需要がある業界のため、将来性がある
・社会の安定に貢献する公共性の高い仕事であり、景気の影響を受けにくい安定性がある
・計画的に物事を進められる人に向いている |
|---|
電気やガス、水道といった「生きるために必要なサービス」のほかにも、移動や運輸、報道、教育、医療などもインフラ業界に含まれることがあります。インフラ業界は、日々の生活を送るためのライフラインを支えている分野といえるでしょう。
インフラ業界で働くやりがい
インフラ業界で働くやりがいは、社会への貢献度が高いことです。電気・ガス・水道・通信などの生活基盤を支えることで、「人々の生活に不可欠なサービスを供給している」という強い使命感や社会を支えている実感を得られます。
また、専門的な知識や技術を得られることが挙げられます。たとえば、エネルギー分野であればエネルギーの取り扱いや供給に関する知識、航空分野であれば保安業務に関する法的知識や整備の技術などです。知識や技術が身につくほどやりがいにつながりやすいほか、待遇改善も期待できるでしょう。
専門的なスキルや知識を身につければ、転職やキャリアアップがしやすいため、自分が思い描いたキャリアプランを実現しやすいといえます。以下のコラムでは、専門性の高い職業について紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
インフラ業界の大変なところ
インフラ業界の大変さには、「責任の重さ」「体力的なつらさ」「上下関係の厳しさ」などが挙げられます。具体的にどのようなデメリットがあるか確認していきましょう。
ミスが許されず責任が重く感じる
インフラ業界の社会貢献度の高さや専門性はやりがいにつながる一方で、責任が重いという大変さもあります。ミスが許されないことからルールが厳しく、仕事への姿勢が問われるでしょう。
仕事に対して責任感をもつ大切さや、プレッシャーに打ち勝つ方法について気になる方は以下のコラムもぜひ参考にしてみてください。
職種によっては体力的にきつい
職種によっては夜勤があったり、立ち仕事だったりして体力的に大変な場合もあることが、インフラ業界のデメリットといえます。たとえば、道路関係の職種であれば、車通りの少ない深夜帯の業務が多くなるでしょう。想像していたよりもハードワークで、精神的にもつらいと感じることが大変だと感じる場合もあるようです。
上下関係に厳しい場合がある
インフラ業界では伝統を重んじる企業もあり、そういった企業の場合は上下関係が厳しいことも考えられます。インフラ業界は安定しているため、歴史の長い企業が多いのも特徴の一つ。古くからのルールを遵守している企業も存在するので、年功序列の落ち着いた社風が苦手な場合はデメリットに感じることもあるでしょう。
インフラ業界で働く大変さを乗り越えるためには、「人々の生活を守る」「社会を支える」といった使命感やプロ意識をもつことが重要です。以下のコラムでは、仕事への責任感や使命感をもつ大切さをまとめているので、ぜひご覧ください。
インフラ業界で働くメリット
インフラ業界は安定感があり、ワークライフバランスも取りやすいのが魅力です。また、人々の生活に欠かせない事業なので、社会に貢献できることがやりがいになるでしょう。
業界全体に安定感がある
インフラ事業は人々の生活に必要不可欠なサービスを展開しているため、ほかの業界と比較して景気に左右されにくく安定感があります。また、行政と連携して行う事業もあり、仕事がなくなる可能性は低いでしょう。
給与体系が明確なことが多い
インフラ業界には、長く勤めるほど給与が上がる年功序列制度を採用している企業も多いため、勤務期間が長くなるごとに給与アップが見込めるのも魅力の一つです。インフラ業界のなかには、元々国営だった大企業も少なくありません。給与体系が明確であれば、キャリアプランも考えやすいでしょう。
手当や福利厚生が充実している
インフラ業界には、住宅手当や扶養手当といった福利厚生が充実している傾向があります。転勤のある会社では社宅が用意されていたり、自社の交通サービスが割安で利用できたりするなどのメリットもあるようです。
ワーク・ライフ・バランスが取りやすい
インフラ業界に属する企業では、私生活とのバランスが取りやすいようです。厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況_1労働時間制度_(4) 年次有給休暇(p.8)」によると、「電気・ガス・熱供給・水道業」の年次有給休暇の平均取得率は70.7%となっています。スケジュール通りに進める仕事が多いことから、有給休暇の取得率が高いといえるでしょう。また、繁忙期やトラブル発生時を除けば、定時で帰れる傾向にあるようです。
まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 向いている仕事あるのかな?
- 自分と同じような人はどうしてる?
- 資格は取るべき?
実際に行動を起こすことは、自分に合った働き方へ近づくための大切な一歩です。しかし、何から始めればよいのか分からなかったり、一人ですべて進めることに不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、プロと一緒に、自分にぴったりの企業や職種を見つけてみませんか?
インフラ業界の代表的な4つの分野
ここでは、インフラ業界の中心的な分野である「エネルギーインフラ」「生活インフラ」「交通インフラ」「空間インフラ」について、それぞれ紹介します。インフラ業界のなかで、どの分野を志望するかを決める際の参考にしてみてください。
1.エネルギーインフラ
エネルギーインフラは、人々の生活に欠かせない電気・ガス・石油の供給に関する分野です。エネルギーインフラには、「電気業」「ガス業」「石油業」などの業種があります。エネルギーインフラ業は、発電や燃料の調達・供給などを行い、一般家庭や企業、施設などへ安定的に供給するのが主な役割です。
災害時には素早い復旧が求められるなど、生活に密接した分野といえます。国内でのエネルギー自給率は低く、発電やガスの製造に欠かせない石油や天然ガス、石炭などは海外からの輸入に頼っている状態です。
経済産業省「令和6年度エネルギーに関する年次報告」によると、日本のエネルギー自給率は2023年度時点で15.3%とほかの国と比較して低い水準となっており、エネルギーの安定供給(自給率の向上)と脱炭素化を同時に進めることが課題となっています。
エネルギー供給においては、安全性(Safety)を大前提とし、自給率(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)を同時達成する「S+3E」への取り組みが一層重視されています。
また、地球温暖化対策として、CO2を含む温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に向けた取り組みも不可欠です。
電気業
電気業は、一般家庭やオフィス、工場などに電気を供給する業種です。主に、「発電」「送電」「拝殿」「販売営業」の4つに分かれています。地域の電力会社や民間の発電会社、電気小売事業者などが該当するほか、再生可能エネルギー事業者(風力発電、太陽光発電など)も代表的な企業といえるでしょう。
ガス業
ガス業の主な役割は、海外から輸入したガスを家庭やオフィスなどに供給することです。都市ガスとプロパンガスの2種類があり、都市ガスは地下の供給管を通して供給され、プロパンガスはガスボンベによって供給されるという違いがあります。都市ガスとプロパンガスの違いによって代表的な企業も異なるため、志望先の企業がどちらを取り扱っているか調べておくと良いでしょう。
石油業
石油業は、大きく「開発事業」と「元売事業」の2つに分かれています。開発事業は石油や天然ガスの開発を行う業種です。元売事業は原油を加工して商品化する業種で、LPガスやガソリン、灯油、アスファルトなど、その加工先は多岐にわたります。
石油業界については、以下のコラムでも詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
2.生活インフラ
生活インフラは、水道や通信に関する分野です。エネルギーインフラと同様、社会生活に広く浸透し、欠かせない分野といえます。
水道業
人々が使用する水を水道管や専用の施設を利用して管理・供給するのが水道業です。家庭で使用する水は浄水、工場で使用する水は工業用水道に分けて供給します。汚水や雨水を処理する下水業も水道業の一つです。また、水道のシステムや設備を設計する仕事を請け負っている企業もあります。
情報通信業
電話やインターネットを快適に利用できるように、回線や整備を管理するのが情報通信業です。固定電話やパソコン向けの「固定通信」、携帯やスマートフォンなど屋外や移動中のインターネット利用を可能にする「移動体通信」、インターネット上の不正侵入を防ぐ「IPS」などのサービスを提供します。
スマートフォンやパソコンが日常に欠かせないのはもちろん、企業が業務でインターネットを使うことも多いため、より良い通信環境を確保するためにニーズが高い業種です。情報通信業に関する仕事については、以下のコラムで詳しく解説しています。
3.交通インフラ
交通インフラは、鉄道や航空など、人や物の移動に携わる分野を指します。仕事や帰省、観光などの交通アクセスや、物流を支える分野です。
鉄道業
鉄道業は、鉄道で人や物を運ぶサービスを行っています。一般の乗客を輸送するのが在来線や新幹線、物流会社を顧客として商品を輸送するのが貨物輸送です。鉄道会社には、公営や民営、モノレール、新交通システムなどがあります。
国土交通省「令和7年版国土交通白書(第3節 産業の活性化)」によると、鉄道業は、新型コロナウイルス感染症の影響により旅客輸送量が大幅に減少し、回復途上にあります。特に、地方鉄道においては、人口減少や利用者の行動変容により経営環境の厳しさが増しています。
そのため、安全確保を大前提としつつ、自動運転や無線式列車制御システムなどの技術導入による生産性向上とコスト削減が課題となっています。人材確保に向けては、外国人材の受け入れや動力車操縦者試験の受験資格の見直しも進められています。
鉄道業に属する企業のなかには、将来の人口減少による本業の伸び悩みを見越して、周辺事業の強化を行っているところも少なくありません。たとえば、観光スポットや駅ビル、レジャー施設など鉄道以外の事業を手がけている企業もあるようです。
鉄道業については、以下のコラムで情報をまとめているので、ぜひご覧ください。
航空業
航空業は、旅客機の運航や貨物輸送を行います。実際に旅客機の運行や貨物輸送を行う「航空会社」のほか、空港の管理や運営を担い、物販や飲食を提供する「空港運営会社」も航空業です。空港のなかには、国が滑走路を管轄し、旅客ターミナルは民間企業が管轄する体制を取っているところもあります。
4.空間インフラ
空間インフラは、国や地方自治体などが提供する公共施設や港湾施設の維持や管理を担う分野です。たとえば、公共施設では学校や図書館、市役所、港湾施設では防波堤や灯台などが空間インフラに当たります。施設の多くは国や地方自治体が管轄しており、仕事内容や業務量が比較的安定しているのが特徴です。
公共・湾岸施設管理業
公共施設管理業は、公共施設の維持管理を行います。なお、公共施設のなかでも寺社仏閣をはじめとした文化財は空間インフラには含まれず、観光インフラに含まれるのが特徴です。湾岸施設管理業は、沿岸部にある水門や排水機場、橋や堤防などの維持管理を行います。
災害時に使用されることが多いため、人々が安全に暮らすために常日頃の維持管理業務が欠かせません。老朽化による劣化や損傷が原因で事故が発生しないよう、責任感のある仕事が求められる仕事といえるでしょう。
IT業界・サービス業界もインフラ業界に関連する
インフラ業界に関連する業界として、IT業界とサービス業界が挙げられます。IT業界では、システムの企画・開発・保持を担当。情報通信業に関連するシステムを構築するため、インフラ業界の企業活動を行ううえでも欠かせないといえるでしょう。
目に見える形がない「サービス」を展開しているサービス業界は、航空会社や鉄道会社など、さまざまなインフラ企業に関連します。たとえば、旅客機の利用者を増やすために旅行代理店を経営したり、観光を盛り上げるためにテーマパークやホテルの運営を行う企業と連携したりと、多角的にインフラへ関わることが可能です。
IT業界とサービス業の詳細は、以下のコラムをご覧ください。
あなたの強みをかんたんに発見してみましょう
「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。
こんなお悩みありませんか?
- 自分に合った仕事を探す方法がわからない
- 無理なく続けられる仕事を探したい
- 何から始めれば良いかわからない
自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。
まずは所要時間30秒でできる診断に取り組んでみませんか?強みを客観的に把握できれば、進む道も自然と見えてきます。
インフラ業界の具体的な職種一覧
インフラ業界には、業種ごとに特徴的な専門職種があります。ここでは、分野ごとに代表的な職種を紹介するので、自分の適性ややりたいことに合った仕事がないか探してみましょう
エネルギー(電気・ガス・石油)に関する職種
インフラ業界のなかでも電気・ガス・石油のエネルギーインフラには、共通する職種があります。ここでは、大きく「技術系職種」と「事務系職種」の2つに分けて紹介するので、参考にしてみてください。
技術系職種
技術系職種は、エネルギーの製造・供給、製造設備のメンテナンスなどを行う仕事です。エネルギーの製造・供給をする際は、発電所などの設備を運転し、安定供給の維持・管理を目指します。ガスは製造、石油は精製して供給しますが、電力は大量に貯蔵できないため、季節や時間帯における使用量を考慮したうえで発電する必要があるのが特徴です。
製造設備のメンテナンスでは、エネルギーの製造設備の保全・保守を行うほかに、現場での電気やガス設備の点検・修理なども業務に含まれます。エネルギーインフラは24時間供給しなければなりません。事故があると社会的な影響は甚大になるため、メンテナンスは社会を支える重要な仕事といえるでしょう。
事務系職種
事務系職種には、エネルギー製造のための資材調達や広報や人事などを行う一般事務、顧客への営業などがあります。資材調達では、海外企業との価格交渉を担うでしょう。ガスの場合は、地下資源の採掘や調査を行うこともあります。
営業職は電気やガス、石油など、自社が提供するエネルギーを利用してもらうために顧客に売り込む仕事です。一般家庭や法人を対象とし、自社が提供するサービスの説明や顧客のニーズに合わせた提案が求められるため、技術に関する知識や積極的に勉強する姿勢が必要になります。
営業職では、基本的に必須とされる資格はありません。とはいえ、たとえば電力会社であれば、電気設備の工事や取り扱いの際に必要な「電気工事士」などの資格をもっていると、顧客との信頼関係を築きやすくなるでしょう。
営業職に求められるスキルや向いているタイプについては、以下のコラムで詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
鉄道に関する職種
鉄道に関わる職種は、大きく「現業職」「技術職」「総合職」の3つの職種に分けられます。以下で、それぞれの職種の役割や仕事内容を確認してみましょう。
現業職
駅務員や車掌、運転士として現場で働く人たちは一般的に「現業職」と呼ばれています。前線に立ち、鉄道の安全な運行や、事故などトラブルへの対処を担う役割です。
「駅務員」とは、窓口や改札口、ホームでのお客さまへの応対を行う職種です。ホーム上や路線上の安全確認、運転手への進行・停止やドア開閉の合図、列車の着発時のアナウンスなども行います。また、自動券売機や定期券の売上管理なども役務員の仕事です。お客さまとの関わりが多いため、相手の話を聞き、要求を読み取る力や分かりやすく説明する力などが求められるでしょう。
「車掌」は、列車に乗務し、お客さまが安全・快適に目的地に到着できるようサポートする仕事です。乗客の乗車完了や到着時の列車の位置確認のうえ扉の開閉、車内での精算業務や乗車券の販売、照明や冷暖房装置の調節、車内トラブルへの対応などの業務があります。また、停車駅や到着時刻および乗り換え案内のアナウンスなども車掌の仕事です。
「電車運転士」は、運行計画に基づき、乗客を乗せた列車を目的地まで安全に運行する仕事です。路線に応じた速度調整や路線の状態に配慮してダイヤ通りに運転し、時間通りの発着を目指します。
電車運転士になるには、鉄道会社に入社後に駅務員や車掌の経験を積み、所定の試験に合格するのが一般的です。電車運転士となったあとも、日々の運行において運転技能を磨いたり、非常時の訓練を定期的に受けたりするなど、スキルの向上や迅速で冷静な判断力を培うことが求められます。
技術職
鉄道に関わる技術職は、車両の保守・点検・管理・信号通信整備といった鉄道の安全に関わる業務を行います。路線や踏切、トンネルなどのメンテナンスを行うのも鉄道技術職の仕事です。
たとえば、鉄道車両のメンテナンスには、ブレーキやドア、電気を取り込むためのパンダグラフ(集電装置)などが正常に動くかを確認したり、各機器や部品を車両から取り外して状態をチェックしたりする業務があります。また、線路の確認・補修、トンネルや橋りょうのメンテナンス、自然災害対策に対する工事といった設備強化も鉄道技術職の仕事です。
総合職
鉄道会社の総合職は、鉄道の運行計画や運行状況の確認など、現業職の牽引を担います。企業によっては駅や列車内でのサービスの考案や総務、営業などの事務系の仕事を行うこともあるようです。
運行管理の仕事は遠隔操作による信号の表示やポイントの切り替え、より良いダイヤの計画などを通して、お客さまに便利で快適な鉄道を利用してもらえるよう努めます。
鉄道では現業職からキャリアアップする傾向にある
鉄道分野では、駅員や車掌、運転士などの現業職としての経験を経て、能力に応じて列車のスケジュールや運行状況などを管理する「運行管理」の仕事に進むのが一般的です。その後のキャリアとして、季節や曜日、時間などから乗降客のニーズを分析し、最適な運転計画を作成する「運転計画」の仕事を担当する流れがあるようです。
航空に関する職種
ここでは、航空会社の主な職種を3つご紹介します。航空会社の仕事に興味がある方は、参考にしてみてください。
パイロット
パイロットは、地上の航空管制官と無線で通信を行いながら飛行機を操縦し、お客さまや貨物を目的地まで安全に運ぶ仕事です。専門知識と技術が必要とされるため、厳しい訓練を受け操縦する機体に応じたライセンスを取得できた人のみがパイロットになれます。
入社後しばらくは、搭乗手続きや乗り継ぎ案内などの地上勤務を行うのが一般的。その後、所定の訓練を受けて20代後半から副操縦士となって飛行経験を積み、30代後半~40代前半にかけて機長へと昇格するようです。
客室乗務員(CA)
客室乗務員(CA)は、旅客機に搭乗してサービスと保安の役割を担います。お客さまを座席に案内したりシートベルトの着用を促したりといった通常業務のほか、緊急時は状況に合わせたアナウンスや避難指示を行い、お客さまが機内で安全・快適に過ごせるようにサポートするのが主な業務です。また、飲食物の機内販売も行います。
採用基準は各航空会社によって異なりますが、募集要項にTOEICスコアなどの英語能力や、視力や体力などの身体的基準が設けられている場合もあります。客室乗務員の仕事に興味がある方は、求人サイトや企業のWebサイトなどで募集要項を確認しましょう。
航空整備士
航空整備士は、航空機の整備・点検を行う仕事です。仕事内容には、空港に降りたった飛行機が再び安全にフライトできるよう日常的に行う「ライン整備」や、一定の飛行時間を越えた場合に時間をかけて念入りに行う「ドッグ整備」などがあります。
国内線の場合は全国、国際線の場合は海外の空港に配置される可能性が考えられるでしょう。フライト時間外に作業を行う必要があるため、勤務は交代のシフト制となります。
通信に関する職種
通信インフラの分野からは、インフラエンジニアやフィールドサービスエンジニアなどの専門職が挙げられます。以下で詳しく確認してみましょう。
インフラエンジニア
インフラエンジニアは、サーバーやネットワークの設計・運用・保守など、ITインフラ全般に関ります。サーバーの運用や保守などを行う「サーバーエンジニア」や、ネットワークの設計や保守などを行う「ネットワークエンジニア」などを総称して「インフラエンジニア」と呼ぶようです。
ネットワークエンジニアについては、以下のコラムで解説していますので、参考にしてみてください。
フィールドサービスエンジニア
フィールドサービスエンジニアは、顧客の元に赴き、自社製品の納入や設置、軽工事、ソフトウェアのインストール、メンテナンスなどを行います。トラブルの的確な把握や適切な対応ができる技術力、コミュニケーション能力などが求められるため、エンジニアとしての「キャリアパスの入口」といわれる職種です。
研究開発職
研究開発職は、より快適で安定したネットワークを提供できるように新しい技術を開発し、実用化を目指します。通信業界では、AIや6G、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)などを含む、XR(クロスリアリティ)などの研究が進められているようです。
インフラ業界に向いている人の特徴
インフラ業界の仕事は社会生活を支える役割を担っているため、責任感のある人やコミュニケーションが得意な人などに向いているでしょう。以下で詳しく解説します。
インフラ業界に向いている人の特徴
- コミュニケーションが得意な人
- 忍耐力がある人
- 社会貢献をしたい人
- 論理的思考力があり物事を分析できる人
- グローバル化に対し苦手意識がない人
コミュニケーションが得意な人
鉄道会社の駅務員や航空会社の客室乗務員など、担当する業務によってはお客さまと関わる機会が多いため、コミュニケーション能力は必須です。また、ヒューマンエラーを防ぐためにも、職場の人たちと積極的にコミュニケーションを取る必要があります。そのため、コミュニケーションが得意な人はインフラ業界で活躍しやすいでしょう。
就職や転職活動におけるコミュニケーション能力の重要性や鍛え方については、以下のコラムで詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
忍耐力がある人
インフラ業界で働くには、忍耐力が必要不可欠です。インフラ事業は安定供給が求められるため、難しい仕事でも最後までこなさなければいけません。トラブルが発生すれば、解決するまで残業することもあるでしょう。
業種によっては、繁忙期は激務になる可能性もあります。忍耐力に自信がある人はインフラ業界に向いているでしょう。
社会貢献をしたい人
「仕事で社会に貢献していると実感したい」「人の役に立つ仕事がしたい」という方は、インフラ業界がおすすめです。ハタラクティブの「若者しごと白書2024 02 現在の仕事について(p.17)」によると、仕事でやりがいを感じることを回答した正社員は、「人の役に立つこと」が15.6%で最多でした。このことから、仕事を通して誰かに貢献したいと考える人は多いようです。
インフラ業界ではエネルギーや交通、通信など、日々の生活に欠かせない分野を担っています。そのため、「社会や人の役に立っている」と感じられる機会が多く、やりがいをもって仕事に取り組めるでしょう。
論理的思考力があり物事を分析できる人
インフラ業界のなかでも特に技術職として働く人には、論理的思考力が求められることもあります。論理的思考力とは、物事を分析し、筋道を立てて説明できるスキルのこと。インフラ業界でいうと、トラブルの原因を探って素早い対応をしたり、求められている新しいサービスを考えたりといったことに役立ちます。
グローバル化に対し苦手意識がない人
インフラ業界では、海外企業とやりとりする業種もあるため、グローバル化への苦手意識がない人に向いている可能性があるでしょう。海外企業へサービスを提供する場合、多様性への理解が必要とされます。グローバル社会で働ける耐性がある人は、インフラ業界の適性があるでしょう。
英語スキルが必要とされるグローバル企業に興味がある方は、以下のコラムもあわせてご覧ください。
インフラ業界の平均年収は552万円
インフラ業界の平均年収は552万円です。国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の令和6年の平均年収は478万円とされています。
インフラ業界は、平均を上回る給与水準であり、とくに専門知識を要する職種においては、インフラ業界の平均年収よりも高くなる可能性もあるでしょう。
インフラ業界の将来性
インフラ業界は、電気・ガス・水道などの生活基盤を支える業界のため、常に一定の需要があり、将来性は高いと言えます。しかし、インフラの老朽化対策や、少子高齢化による人手不足が喫緊の課題です。
これらの解決のため、DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率や新技術の導入が加速しています。また、脱炭素化やエネルギー安定供給といった社会の要請に応えるための事業転換や、再生可能エネルギー関連の技術開発・投資も進んでおり、これらの分野で成長が見込まれます。
インフラ業界で役立つスキル
インフラ業界への就職・転職に役立つスキルとして、主に専門技術と安定供給を支えるポータブルスキルが挙げられます。技術職では、建設・土木系ならCADスキルや施工管理の知識、電気・エネルギー系では電力系統の知識や電気主任技術者などの資格知識、情報・通信系ではネットワーク技術やセキュリティ知識が重要です。
これに加え、社会の基盤を支えるため、安全性への強い意識と責任感、トラブル時に原因を特定する論理的思考力、チームで連携するコミュニケーション能力が不可欠といえるでしょう。
インフラ業界に就職・転職するための5つの方法
「インフラ業界への就職・転職を考えているものの、何から始めて良いか分からない…」とお悩みの方もいるでしょう。ここでは、インフラ業界で働くための方法を紹介します。就職・転職活動の際にぜひ参考にしてみてください。
インフラ業界に就職・転職するための方法
- 1.自己分析を行う
- 2.インフラ関係の最新知識を調べる
- 3.インターンシップに参加する
- 4.求人サイトを利用する
- 5.就職・転職エージェントを活用する
1.自己分析を行う
インフラ業界に興味があり、就職・転職したいと思っている場合は、自己分析から始めてみるのがおすすめです。興味がある分野やこれまでの経験、得意なことなどを自己分析で把握すれば、自分に合う仕事が見つけやすくなります。インフラ業界にはさまざまな業種があるため、どのような業種・職種が向いているのかを、自己分析で判断しましょう。
以下のコラムでは、自己分析のやり方について解説しているので、ぜひご覧ください。
2.インフラ関係の最新知識を調べる
インフラ業界の最新技術に興味をもち、情報を仕入れることも大切です。再生可能エネルギーやIoTなどの情報を集めておけば、入社後もその知識を仕事に活用できるでしょう。
情報収集は、インターネットや新聞などで行えます。インフラ業界に関連するニュースを積極的に確認しておくと面接にも役立つでしょう。
3.インターンシップに参加する
興味のある業種や企業を見つけている場合は、インターンシップに参加してみるのも手段の一つです。インターンシップに参加することで企業の詳しい情報を知れたり雰囲気がつかめたりするため、入社後のミスマッチが減りやすくなります。
また、現在働いている方の生の声が聞けるのもインターンシップのメリットです。インターンシップは企業のWebページで案内されていることがあるため、一度調べてみると良いでしょう。
4.求人サイトを利用する
求人サイトを利用して、インフラ業界の求人を探してみる方法もあります。求人サイトを利用すれば、勤務地や給与などの希望条件を選んでインフラ関連の仕事を検索できます。スマートフォンやパソコンで調べられるので、隙間時間を活用できるのもメリットです。
5.就職・転職エージェントを活用する
効率的にインフラ業界への就職・転職を目指す場合、希望条件に合う求人探しや選考に向けた準備が必要なため、エージェントの活用が有効といえるでしょう。就職・転職エージェントでは、専任のアドバイザーが希望条件に沿った求人を紹介してくれます。
希望の働き方や仕事選びに迷っている場合も、適性に合った求人紹介やアドバイスをもらえるため、ミスマッチ防止にも有効です。選考に向けて応募書類の添削や面接対策も行ってくれるため、一人での選考対策が不安な方や、プロのアドバイスを取り入れたい方は活用してみましょう。
「インフラ業界が気になるけど、やめとけと言われて不安…」という方もいるかもしれません。インフラ業界は「全国で整備を行う必要があるため転勤が多い傾向にある」「保守的な傾向がある」「人口の減少に影響を受ける可能性がある」といった理由から、「やめとけ」といわれることもあるようです。
しかし、これらの条件が合うかどうかは人によって異なります。自分がインフラ業界に適性があるかどうかを分析したうえで、検討してみると良いでしょう。判断材料の一つとして、このコラムの上部にある適職診断もおすすめです。およそ1分の短時間で自分にどのような仕事が合っているか診断できるため、適職が分からないという方は試してみてくださいね。
ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス
インフラ業界の志望動機例
「インフラ業界が気になるけど、志望動機の書き方が分からない」という方もいるでしょう。ここでは、未経験者の場合と経験者の場合に分けて、志望動機の書き方のコツをご紹介します。
業界未経験者の例文
未経験者の志望動機では、「なぜインフラ業界なのか」「インフラのなかでもなぜその業種なのか」といった点がポイントになります。単に「社会貢献がしたい」といった理由では、採用担当者に「インフラ業界でなくても良いのでは」と思われてしまう可能性があるため、将来の夢や目標とあわせて明確な理由を伝えましょう。そのうえで、応募先企業を選んだ理由を述べます。
貴社の「安全・安定供給」を最優先とするインフラ事業に強く共感し、未経験ながら貢献したく志望いたしました。前職で培った論理的思考力は、トラブル発生時の原因究明や工程管理に役立つと確信しています。特に、社会インフラを支える責務を理解し、安全性への強い意識を持って業務に取り組みます。未経験の分野ですが、脱炭素化やDXが進む業界の変化を成長の機会と捉え、専門知識を迅速に習得することで、貴社の安定的なサービス提供に貢献したいと考えております。
未経験者は専門知識やスキルをアピールできないため、意欲や将来性といったポテンシャルをアピールすると良いでしょう。志望動機の作り方や注意点は、以下のコラムを参考にしてみてください。
業界経験者の例文
経験者の志望動機は、前職を辞めた理由と、応募先企業を選んだ理由をつなげましょう。たとえば、「前の会社は既存事業の維持に力を入れており、新しい事業へ挑戦する機会がありませんでした。貴社は新しい市場を開拓することに力を入れているため、志望いたしました」といった志望動機が考えられます。
私は前職で培ったITインフラ構築・運用経験を活かし、貴社のDX推進に貢献したく志望いたしました。前職では大規模ネットワークの設計・セキュリティ強化プロジェクトを主導し、CCNA/CCNPの資格を取得しています。社会基盤を担う貴社インフラの安定性とセキュリティを強化することが、私の最大の目標です。貴社であれば、私の専門性と、現場の課題を解決してきた経験を最大限に活かせると確信しております。入社後も最新技術を積極的に学び、インフラの最適化を通じて貴社の競争力強化に貢献します。
また、前職で身につけたスキルを応募先企業でどのように活かせるかをアピールすることも重要です。業界研究・企業研究をしっかりと行い、どのようなスキルをどのような事業で活かせそうかを志望動機に織り交ぜましょう。
企業研究の仕方については、以下のコラムで解説しています。
インフラ業界で正社員を目指すならエージェントがおすすめ
インフラ業界は、電気やガス、水道、交通、通信など、人々の生活や経済活動を行うためになくてはならない部分を担っている業界です。エネルギーの安定供給(自給率の向上)や脱炭素化といった課題を抱えているものの、エネルギーや交通、通信といった社会の根幹を支える業界のため、今後も安定的な需要が見込まれます。
転職・就職エージェントのハタラクティブは、フリーターや既卒、第二新卒といった若年層に特化した支援を行っています。専任のキャリアアドバイザーが丁寧なヒアリングを行い、一人ひとりに合った求人情報を厳選してご紹介。人柄やポテンシャルを重視する企業の求人を扱っているため、経歴に不安のある方も安心です。
また、応募書類の添削や模擬面接といった選考対策や、企業とのやり取り代行といったサポートも実施。全面的なサポートを受けながら、自信をもって就職活動を進められるでしょう。仕事での適性が簡単に分かる「適職診断」もご用意しております。サービスの登録・利用はすべて無料のため、まずはお気軽にご相談ください。
インフラ業界に関するFAQ
ここでは、インフラ業界に関する疑問をQ&A方式で解消します。代表的な職種や将来性についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
文系出身だからといって、インフラ業界への就職が不利ということはありません。マーケティング力・語学力・対人能力などがあれば、インフラ業界にある営業職や事務職、客室乗務員といった仕事に活かせるでしょう。
ただし、設計や研究開発といった専門職では、理系出身者が有利になる場合もあるようです。文系に向いている傾向にある仕事については、以下のコラムで情報をまとめているので、参考にしてみてください。
未経験からインフラ業界を目指すときのポイントはある?
未経験でインフラ業界を目指す際は、就業意欲や積極性、働くうえでの将来性などをアピールすることが重要です。業種ごとに求められる人物像を把握し、方向性にマッチする人材であることを伝えましょう。就職・転職エージェントのハタラクティブでは、相談者一人ひとりに専任のアドバイザーがつき、就活を全面サポートします。1人でインフラ業界を目指すことに不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
インフラ業界は、女性も活躍できます。航空会社のCAやIT系の技術者、鉄道業界の車掌など、幅広い仕事で女性の活躍が見られるので、男女比率も参考に挑戦してみるのがおすすめです。
インフラ業界に興味がある女性の方は、どのような分野のどのような職種が自分に合っているのか、その仕事で何を成し遂げたいかを考えたうえで検討してみると良いでしょう。自分に合う仕事が分からない方は、以下のコラムもぜひ参考にしてみてください。
インフラ業界の営業の仕事内容について教えてください。
インフラ業界の営業職は、主に法人や自治体を対象とするBtoBビジネスが中心です。仕事内容は、電気・ガスなどのエネルギー供給契約の提案、鉄道や道路などの大規模な建設プロジェクトの受注、通信ネットワークのソリューション提供など多岐にわたります。
営業職について、詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。